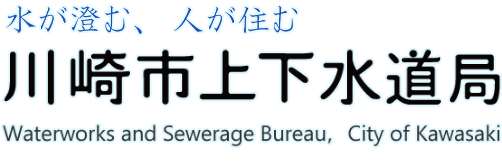第64回水道週間 川崎市小・中学生作品コンクール 入賞作品 作文の部
- 公開日:
- 更新日:
小学校低学年の部
特選: 該当者なし
準特選: 川崎市立平間小学校 2年 上地 諒
水を大切に
ぼくは毎日夜おふろに入ります。ぼくは体をあらった時には、シャワーもつかいます。ぼくは、体をあらう時にすこしシャワーであったまってしまいます。しらべたらシャワーは1分間に10ℓの水をつかうことがわかりました。あったまるためにシャワーを出しっぱなしにするとそれだけたくさんの水をつかってしまいます。だから、おふろのおゆであったまればいいと思いました。
おふろのおゆをためると1回で200ℓの水をつかうこともわかりました。たくさんの水なので大切にしないといけないと思います。お父さんとお母さんはおふろの水をせんたくする時につかっています。それでものこった水はそのまますててしまっているそうです。もっとほかにつかえることがないか考えてみました。たとえばうえきの水やりにつかったり車や自てん車をあらう時につかったりよごれたサッカーボールをあらったりくつやうわばきをあらう時につかったりすれば、おふろのおゆもむだにならないと思いました。
あとはぼくが水をたくさんつかう時は学校や家で手をあらう時です。しらべたら30びょう出しっぱなしにすると6ℓの水をつかうそうです。石けんをながす時だけ水をつかってあらっている時はながしっぱなしにしないことが大切なんだなと思いました。ぼくはこれまで水のむだづかいはしていないと思っていました。でもすこし考えただけでいくつもむだづかいをしていることに気がつきました。小学校でSDGsをべんきょうしています。その中にも水を大切にしようという目ひょうがあります。むだづかいをすこしでもなくして水を大切にしたいと思います。
準特選: 川崎市立東高津小学校 2年 北里 大駆
水があるからできること
ぼくは、夏休みに「みずをくむプリンセス」という本を読みました。
読んでみると、ジージーという女の子が、まい日とおくまで大きなつぼをもって、水をくみに行くお話でした。アフリカの人たちは、まい日みんな水をくみに行って、とても大へんそうでした。せかいでは、六人に一人がきれいな水をのめないでくらしていると知っておどろきました。
ぼくには、サッカーせんしゅになるゆめがあります。夏休みも、まい日すいとうに、たくさんの水を入れて、れんしゅうに行っています。とてもあついので、コーチに、水をこおらせたペットボトルも、もってくるように言われています。れんしゅう中には、なん回も水をのんで、れんしゅうがおわってからは、シャワーもあびるし、ユニホームをせんたくします。ぼくのサッカーのれんしゅうには、たくさんの水をつかいます。だけど、アフリカでは、そんなふうにはできません。ぼくがサッカーのれんしゅうを、こんなにできるのは、日本だからです。
アフリカのみんなも、いつか水をかんたんにのめる国に、なってほしいです。せかいのみんなも、元気よくくらせて、すきなことが、たくさんできるといいなと思いました。だからぼくは、水を大切にして、あたりまえのことにもかんしゃして、元気いっぱいにすごしたいです。
入選: 川崎市立平間小学校 2年 岩𦚰 悠真
きれいだなお水
ぼくは、水は大せつだと思った。どうしてかというと、きれいだし、おいしいからです。
水は生きていく上で大じです。なにかをそだてる上でも水は大せつです。あとは、シャワーするときつかうし、おかしつくるときもつかうし、おちゃにすることもできます。
生かつだけに、大じなのでは、ありません。生きものをかうときとか、花やしょくぶつをそだてるのにも水はとても大せつです。たとえば、水中の中の生きものが水がないとしんでしまったり、しょくぶつをそだてるときも水をあげないとかれてしまったりしてしまうので水はとても大切です。水をつかわないのに、ジャージャーだしっぱなしにしていると水のむだになってしまいます。水はいつも大じにつかいたいと思います。水をむだにしないようにするには、だしっぱなしにしないし、つかうときは、つかうぶぶんだけつかうとかくふうをしていきたいと思います。
入選: 該当者なし
入選: 該当者なし
入選: 該当者なし
入選: 該当者なし
小学校中学年の部
特選: 該当者なし
準特選: 川崎市立菅小学校 3年 井山 結太
水をまもろう
ぼくは、テレビでむ人島からだっ出する番組がすきです。その番組を見ていると、のむための水をとても苦ろうしてさがしたり、よごれた水をのめるくらいまできれいにするのに時間がかかったりしていることがよくあります。ぼくは、そんな風に時間をかけて水をさがしたり、にごった水をのんだことがありません。家でも学校でも、水道のじゃ口をひねると、とうめいできれいな水がたくさん出てきます。お風ろの水も、トイレの水も、にごっていません。だから、のみ水をほんの少し手に入れるためだけに、あんなにも時間と手間がかかって大へんなのは、む人島だからなんだろうなと思っていました。
でも、それはちがっていました。この前、こども新聞を読んでいたら、
「地球のための十七の目ひょう」
というのがあって、その目ひょうの一つに、
「安全な水とトイレを世界中に」
と書かれていました。のめる水が近くになくて、遠くまでくみに行かなければならない人がいて、世界でくらすおよそ七十六おく人のうち、安全なのみ水を手に入れられない人は二十おく人い上もいるそうです。そんなにたくさんの人がお水でこまっているなんて知らなかったので、ぼくはビックリしました。お母さんのお手つだいでお水をくみに行ったことはあるけど、近くのスーパーで、ボタンをおしたら出てくるお水をボトルに入れただけです。たったそれだけのことでも、自分ががんばった気持ちでいたけど、毎日朝早くから遠くまで水をくみに行くため学校に通えなかったり、手に入るお水もきれいじゃなくて、でもそんなお水でものむしかなくて、びょう気になる人もいると知って、水道からきれいな水が出てくるのは、当たり前のことじゃないんだと思いました。
お水を大切にするにはどうしたらいいか、考えてみました。まずは、いつもお風ろに入る時や手をあらう時にお水を出しっぱなしにしてしまうことが多いので気をつけます。よごれた水をたくさんながしてしまうとお水も自ぜんもよごれてしまうので、たくさんせんざいを使わないようにしたり、食べ物やのみ物をのこさないようにがんばります。あと、川や海や自ぜんがよごれないように、ゴミもへらせるようにしたいです。
お水がきれいになると、心も体も自ぜんもきれいになれる気がします。一人ひとりができることからはじめて、みんなで力を合わせてきれいな水をまもっていけたらいいなと思いました。
準特選: 該当者なし
入選: 川崎市立向小学校 4年 関 真一朗
すばらしい水道技術を世界へ
蛇口からは、いつでも衛生的でおいしいお水が出てきます。のどがかわいた時、手を洗いたい時、シャワーをあびたい時など、使いたい時は、いつでもお水を使うことができます。水道のおかげで、豊かな生活が送れていることに感謝しています。
水道が整備されているからこそ、いつでも水分をとることができ、入浴によって体を衛生的に保ち、健康的な生活を送ることができるのです。
また、水道のおかげで、大地がうるおい、農業や畜産業などが行われ、豊かな恵みがもたらされています。
それでは、世界に目を向けると、どうでしょうか。まだ、アフリカや中東など多くの地域で、生きるために充分なお水を確保できず、毎日たくさんの命が失われています。
中東のアフガニスタンでは、ここ何世紀も起きたことのない大干ばつが起きています。大地は干上がり、ひびわれています。お水がないため、作物を育てることもできず人々や動物たちは飢えに苦しんでいます。井戸もかわき切って、命をつなぐお水を飲むこともできません。そのため毎日多くの命が失われています。その惨状を知り、医師の中村哲さんは、アフガニスタンの人々命を守るために、アフガニスタンに用水路を作る計画を立てました。現地の人々と協力して、土を掘り、山から石をかついで運び、ほとんど手作業で用水路を作っていきました。
中村哲さんの強い意志が、アフガニスタンの人々の心を動かし、協力者が増えていきました。地道な活動は続き、十二年で二十七キロメートルの用水路を作ることができました。この用水路で一六〇〇〇ヘクタールの土地がうるおい、お水のおかげで、人々は農業を再開し、約六十万人の命が支えられています。
しかし、これは、アフガニスタン全人口の二%です。川崎市の高い水道技術をアフガニスタン全土に、更に周辺地域に広めて頂き世界の人々や動物たちが水不足に苦しむことなく、豊かな水の恩恵を受け、命をつないでいかれるよう、心から願っています。
私達の命を守ってくれている水道に改めて感謝し、お水を大切にします。
入選: 川崎市立稗原小学校 4年 松本 陸
ありがとう水
「水がないとこまる」というけいけんを今までしたことがなく、考えたこともありません。あさおきてからよるねるまでの間、トイレやおふろ、はみがき、手あらいなどいろいろなばめんで何もいしきせず水をつかっています。ほかにもいえではせんたく、そうじ、りょうり、花やサボテンの水やりでもつかいます。大すきなバスケをしているときもよくのみます。いっぱいのみそして水はいつでもどこにもあるとおもっていました。ぼくはまえにアフリカの子どもがとおくの川や池にまいにちあるいて生るための水をくみにいくというテレビを見ました。ぼくが学校でじゅぎょうをうけたり、友だちとあそうでいる時、バスケをしているときにアフリカの子は大変な思いをしているのことだと思っていました。でも、とおい国のことだと思っていました。だけど同じ日本で大地しんやさいがいによって水がつかえなくなりかぎられた水を大切につかうようすをニュースで見ました。とてもおどろきしょうげきでした。この二点が、水について考えるきっかけになりました。ぼくたちのくらしを支えているだけでなくいきものや植物のいのちにもかかわっています。さらにはいつもたべる米ややさいをつくるためにもひつようとなっています。水がないと多くのことがなりたたないということ、大きなやくわりをもっているということに気付きました。水がなければ、ぼくたちはいきていけないということにもっと目をむけなければならないとおもいました。「出しっぱなしにしないで、水をだいじにしなさい」とよくおかあさんにいわれてきたことが、いまりかいできます。たいせつな水だからです。いままでなにもかんがえずにあたりまえのようにつかってきた水は、あたりまえにつかえるものではなく、むげんにあるとおもっていた水はかぎりあるきちょうなものです。それを不自由さをかんじることなくひつようなときにあたりまえのようにつかえるかんきょうせいかつしてこれたことにまずはかんしゃしたいです。そして、これからさき、このありがとうのかんきょうをつづけていくために、広げていくために、水のむだづかいをしないなと小さなことでもつみかさねていきたいです。
「水、ありがとう」のきもちを土台にして、みらいに水をつなげていく行いをしていこうと心につよくきめました。
入選: 該当者なし
入選: 該当者なし
入選: 該当者なし
小学校高学年の部
特選: 該当者なし
準特選: 川崎市立川崎小学校 5年 出本 紗英
きちょうな水を大切に使おう
私は、水は全ての生き物や植物、生活に必要だと思います。
例えば動物だったら、たくさん水を飲むと成長して人間のいやしになったり、食べ物になったりします。私もハムスターを飼っています。そのハムスターは毎日たくさん水を飲んでいます。そうしたら、前まで小さくて赤ちゃんみたいだったのに今では手の甲くらいまで大きくなりました。それに生活の中でも、おふろに入ったり、歯をみがいたり、料理にだって水は必要です。もし生活に使う水がきたなかったりしたら、体をこわしてしまいます。
私も、学校の授業の体育の時間、暑い中走るので、すぐに水筒の中の水がなくなってしまい、のどがからからになって困っていました。だからキレイな水がたくさん必要なのです。
では、どのようにしたら水を大切にできるでしょうか。
一つ目はむだ使いをしない事です。例えば、おふろに入っている時や歯をみがいている時など、水を出しっぱなしにしない工夫です。
二つ目は、油がついた、お皿の油をそのまま水で流さない事です。油がついたお皿を洗う時は、一度ティッシュなどでふいてから洗う工夫をします。
三つ目は食べ物を大切にする事です。野菜や果物一つ作るためには、たくさんの水を使います。例えばメロンで、一つ作るために四百十七リットルもの水を使います。それにきらいな人が多いトマトも、一つ作るだけで十六リットル使います。食べ物を大切にする事は、水を大切にする事とつながります。
水は、私達を支えてくれています。水がないと生活できません。水は人間や動物などの生命や生活に必要な物です。
私はこの学習を通し、一人一人が水を大切にする工夫を意識し、行動にした方がいいと思いました。一人だけが意識していても、みんなで協力しなくては意味がありません。だから、小さな工夫でも一人一人ができることをしていきたいと思います。それと、食べ残しをなくしたいです。私が今まで食べ残した物にふくまれている水を全部あわせたら何十ℓになると思います。なので食べ残しをへらし、食べ物を育てるために使った水をむだにしないようにしたいです。一人でやるのではなく、みんなで意識し、協力し、水を大切にしたいです。
準特選: 該当者なし
入選: 川崎市立川崎小学校 5年 島田 紅空
生活に欠かせない水
水は、植物・動物・生活に欠かせない大切なものだと思います。
例えば、日常生活で料理をします。もし、水がきたなかったら体をこわしてしまったり、ご飯がおいしくありません。そもそも、水がなかったら、作れるご飯が少なくなってしまい、楽しい給食の時間がつまらない給食の時間になってしまいます。植物にだって水は大切です。もし、植物にあげる水がなくなってしまったら、栄養が足りなくて、植物は育ちません。
もし、このコロナ禍で水がなくて手を洗えなかったら、感染リスクが高まり危険です。私は手が洗えなくて困った事があります。公園で遊んでいるときに、水道がなくて手が洗えず、おかしが食べれなくて、困りました。そのため、遠い場所まで行って、手を洗わないといけなかったため、大変でした。
私は水があってよかったと思った事があります。友達とおにごっこをしていた時のどがカラッカラッになりました。そして、水を飲んだら、体全身がうるおいました。もし、水がなかったらと思うと、楽しくおにごっこを再開できなかったと思います。
私は学校で、SDGsについて知りました。その中の目標六の安全な水とトイレを世界中にという目標があります。『安全な水』と書いてあるから、まだ世界のどこかで安全な水が使えていないのだと思いました。安全な水が使えないと、水を飲んで命を落とすこともあるので、安心して水が飲めないと思いました。
前に読んだ本で、水をくみに行くために、学校にも行けずに、毎日何時間もかけているのです。このことから、水は学校に行く時間をけずってまでするほど大切なのだと思いました。
この目標を達成するためには、浄水場や下水場、それをつなぐ水道管を作ればきれいな水が行きとどくと思います。しかし、広い土地・費用・時間がかかるので今困っている人を救えません。だから、広い土地で費用がかからず作業の時間が短い井戸を作ればきれいな水がすばやく行きとどいて、みんなの笑顔が増えると思いました。
水がないと、植物が育たない、その植物を食べる草食動物が減り、またそれを食べる肉食動物が減ってしまいます。そうすると人間が食べる物がなくなり飢え死にしてしまいます。
水は、植物・動物・生活に欠かせない大切なものです。
入選: 該当者なし
入選: 該当者なし
入選: 該当者なし
入選:該当者なし
中学校の部
特選: 該当者なし
準特選: 川崎市立玉川中学校 3年 奥山 輝
「身近な多摩川の恵み」
私の家は多摩川の下流、そこから徒歩五分ほどのところにある。広々とした河川敷もポイントとなり、両親がここへの引っ越しを決めたそうだ。
河川敷ではサッカーの練習、飛行機とばし、土手を飽きることなく上り下り。川の様子を見ながらの散歩もよくした。その時々によって水の量が変化していることや、季節によって草花の種類が変化していること、また大雨の後はペットボトルやポリバケツ、果ては地域名の書かれた看板のようなものまで、ありとあらゆるものが流れてきていることが印章に残っている。なかでも最も印章に残っているのは、鳥が増水して勢いの増した川で激流下りを楽しんでいたことだ。台風によって茶色の大量の水に辺りがおおわれ、木々も水中から生えているような姿になっている異常な川。流れを遊びとして利用している鳥たち。それらは水の怖さを象徴しているように感じられる濁流と、水の豊かさを象徴しているように感じられる水鳥の遊びが一つの視界の中で強く対比されているように思われ、すでに数年前のことになってはいるが、今も強く記憶に残っている。
私の母校である下沼部小学校には、有吉づつみのなごりの段差があり、家の近くの公園には有吉堤竣工から百年記念の石碑がある。これらは昔の例だが、今でも治水に関する工事をしている所をよく見かける。昔も今も、多くの人が関わることで、洪水などの災害に怯えることなく、安心して川とともに生活することができているのだと感じる。
小学校高学年の時、普段サイクリングなどに利用している多摩川が、どこからどのように始まるのか、気になった。インターネットで調べたところ、最初の一滴は山梨県の笠取山にある、水干というところにあると分かった。そして、中一のGWに、ついに現地へ行くことになった。
そこは、よく手入れされた明るい森といった感じの所で、登山道のそばには常に小川が流れていた。水源地のため、水道局が管理しているとのことで、情報の詰まった案内板もあちらこちらに設置されていた。それらの一つに、大正時代の水源地の様子として、裸山の写真があった。焼畑を原因とする山火事などによって裸山が広がり、少し雨が降っただけでも山崩れや洪水が度々発生したので、苗木を植え手入れをしつづけ、今ある森林を取りもどした、とあった。大切な水源を守るための地道な努力が、普段の豊かな生活につながっているのだと感じた。
登山口から多摩川最初の一滴、水干までの標高差は六百メートル弱。もう五月だというのに、あたりは冷えていて、雪もまだ少し残っていた。驚いたことに、最初の一滴はつららになっていて、そこから十数秒おきに水滴が垂れていた。これが多摩川のはじまりと思うと、たった一滴の水が集まって普段見ているような雄大な流れになることに、水の力強さ、豊かさを感じた。
いつも私の飲んでいる水は、相模湖、津久井湖、丹沢湖、宮ヶ瀬湖、四つの湖からのもので、多摩川からのものではないそうだ。ただ、どの湖の水もはじめの一滴から川になって注ぎ込んでいることを思うと、森の整備、水道パイプの保守、河川の開発など、実にさまざまな人の力によって、便利できれいな水を使えていることを強く実感させられる。
昔は多摩川も泡だらけで、そばには近寄りたくないほどだったと聞くが、今では憩いの場になっているのには、大変な水質改善への努力があったのであろう。
大切な水、自分でもできる節水や、水を汚さない工夫などを通して、限りある豊かな水資源を大切にしていきたい。
準特選: 川崎市立柿生中学校 3年 馬淵 咲希
笑顔を増やす安全な水
五・八億人。この数字は、世界で安全な水を手に入れることができない人の人数を表します。さらに、一日に八百人もの子どもが汚れた水や不衛生な環境が原因で命を落としています。
給水設備が整っていない地域の中には川や池などの飲用に適さない水源に頼るしかないところも多く、その水は多くの場合、泥や細菌が混ざっているため、浄水処理をしないまま飲むと抵抗力の弱い子どもは伝染病にかかってしまいます。また、手に入る水の量が少ないため、生活環境を清潔に保てなく、さまざまな病気に感染しやすい状況にあります。
私たちの現在の生活では蛇口をひねると安全な水が出てくることが当たり前になっています。そのため、安全な水がない生活を想像したことがないかもしれません。しかし、これは現実に起こっている問題です。水の供給は公衆衛生と生活環境を改善するために不可欠な社会インフラです。水は、生命や健康の維持から、農業、工業などの経済活動まで、人々のあらゆる営みの根幹に関わっているのです。そのため、世界中の人々が協力してこの問題に向き合わなくてはなりません。
そこで、持続可能な開発目標SDGsでは、「すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する」という目標を掲げています。この目標達成への取り組みを通して、改善された給水設備を利用できる人口は増えましたが、一方で、未だ四・三五億人が保護されていない湧水・浅井戸を利用し、一・四四億人は、河川や池の水を利用しています。
日本では、水道に関する、今から五十年後、百年後の将来を見据えた当面の間の取り組みを示した新水道ビジョンを策定し、このビジョンにおける三つの理想像の一つである、「水道サービスの持続」では、「国際展開」の取り組みが掲げられており、SDGsの目標達成に貢献しています。
具体的には、ODA活動として、技術協力、無償や有償の資金協力を行い、衛生施設の整備などによる安全な飲料水の供給と基本的な衛生の確保や、食糧増産を目的とした農業用水の安定的利用のための支援などをしています。さらに、水に関連する災害の被害軽減のための予警報システムの確立もしています。
このような取り組みを通して、きれいで安全な水を手に入れることができる環境が整えられるのです。完成した給水設備に触れ、現地の人々はどのような思いを抱くでしょうか。驚き、楽し気に何度もポンプを押す子ども。ポンプからきれいな水があふれる様子を興味深々に見入る子ども。うれしそうに手酌で水を口に運ぶ、何人もの子どもたち。その子どもたちの様子を、優しいまなざしで見守る大人たち。幸せに満ちた人々の姿が思い浮かびます。きれいで安全な水を得た人々の表情は笑顔と希望であふれていることでしょう。きれいで安全な水には、人々の笑顔を増やす力があるのです。
私たちも、豊かな生活を送るには、きれいで安全な水が必要不可欠だということを今、改めて深く考えてみることが大切だと思います。今生活している何気ない日々は、たくさんの人の努力や物などによって成り立っていることを理解し、感謝し続けていくことが大切なのではないでしょうか。
入選: 川崎市立玉川中学校 3年 石川 柚奈
これからの未来に向けて
私たちは当たり前のように「安全できれいな水」を使っています。水は、生活用水・農業用水・工業用水に分類出来ます。私は、私たちの一番身近にある、生活用水を例に考えてみました。
私たちは家や学校などの蛇口をひねり、安全できれいな水道水を使って生活しています。でも、これは当たり前の生活なのでしょうか。二〇一六年から始まった、持続可能な開発目標、SDGs17の目標の一つには、「安全な水とトイレを世界中に」があります。この目標では、誰もが安全な水を安く利用できるようにすることなどがターゲットになっています。なぜなら、世界の四人に一人の割合できれいな水を使えなく、また汚れた水などが原因で起こる下痢により、毎日約八百人の子どもたちが亡くなっているからです。なぜ、このようなことになってしまうのか、調べ考えてみました。
エチオピアに住んでいる「十三歳の少女」の一日では、六時三十分から四時間、暑い道のりを歩き、水汲み場に着きます。そこで水を汲み、顔を洗い、洗濯をします。帰りも四時間歩き、家へ着く頃には午後四時近くになっています。これだけ歩いても、一日で水を汲む量は一人当たりたった五リットル未満だそうです。それだけでなく、その水の中には細菌などが含まれ、汚染されています。また、彼女が水汲みにかける時間は毎日八時間。私たちが学校に通っている時間とさほど変わりません。それなのに毎日、炎天下の砂漠を歩き続けなければならないのです。
私たちは同じ地球で生活しているのに、なぜこんなにも生活が違うのでしょうか。それは、環境の違いにあります。私たちの住んでいる国、日本には、ダムや浄水場、配水管など安全できれいな水を使える環境が整っています。しかし、エチオピアに住んでいる「十三歳の少女」の身の回りには、安全できれいな水どころか、トイレさえもありません。あるのは、細菌などに汚染された水だけです。そのため、どんなに汚染されていてもその水を飲むしかありません。そうすると、抵抗力の弱い子どもたちは、その水が原因で下痢を起こしてしまいます。また、下痢を起こすことでさまざまな病気にかかりやすくなります。しかし、水不足なので、その病気を治すために必要な水が手に入りません。
ところで、地球上にある水のうち、私たちが使用できる水の量はどのくらいか知っていますか。地球は七十パーセントが水で覆われているため、「水の惑星」と呼ばれています。しかし、私たちが飲み水として利用できる水は、〇・〇一パーセントのみです。それはなぜなのでしょうか。地球上にある水のうち、海水は九十七・五パーセント、淡水は残りの二・五パーセントです。淡水とは、塩分濃度が低い水のこと。淡水のうち、ほとんどが南極大陸などの氷や、地下水です。そのため、私たちが利用できる水は淡水のうち河川や湖など、ごくわずかで貴重な資源なのです。では、この限りある水を守るために、どのように使っていけば良いのでしょうか。そのためには、こまめに水を止めるなどの節水を心掛けることが大切です。
このように、「蛇口をひねると安全できれいな水が出て来る。」これは当たり前ではないのです。世界中には、時間をかけないと水を得られない人もいます。今では、コロナウイルスの対策として、石けんによる手洗いが求められていますが、世界人口の四十パーセントにあたる、三十億人の人が家で石けんと水を使った手洗いが出来ずにいるそうです。全員が石けんを使った手洗いをするためには、ひとりひとりが水の現状についてよく考え、水を使っていくことが大切だと思います。
入選: 川崎市立菅中学校 3年 村松 春紀
二パーセントの水
「普段の生活の中で、一体どれくらいの量の水を飲んでいるのだろうか」
以前、些細な好奇心から、実際に一日の間に摂取している水の量を計測したことがあります。飲み物としての水の量だけではなく、料理などに使用する水の量まで、摂取する水をすべて合計してみました。すると、日々約三リットルの水を摂取していることがわかりました。これは、自動販売機などでよく見かける五百ミリリットルサイズのペットボトル約六本分の量で、思っていたよりもかなり多い量だったので、とても驚いた記憶があります。ちなみに、水の量を最も多く使っていたのは料理のときで、特に鍋物やスープなどでは多くの量の水を使っていました。
日々大量に必要となる水、その大部分をまかなってくれているのは「水道水」です。「水道水」は、飲んだり料理で使うだけではなく、手洗いやお風呂など、衛生面でも必要不可欠なものです。
私は、小学校のときに「特別授業」として浄水場を訪れたことがあります。その時に、「どうやって水を綺麗にしているのか」「水をどのくらい綺麗にしているのか」などいろいろなことを教わりました。「特別授業」がもう少しで終わろうとした頃、授業の復習を兼ねて、クイズが始まりました。
「クイズ第一問。毎日、皆さんに提供できるようにお水を綺麗にしていますが、世界中のお水の中で飲み水に出来ているのは何パーセントでしょうか?」、浄水場の職員の方は、「二・二十・五十」と書かれた紙を黒板に貼り、「それじゃあ『二』だと思う人は手を挙げてねー」と言いました。それを聞いてクラスの十人位が手を挙げました。「じゃあ次、『二十』だと思うひとー」、今度は二十人位が手を挙げました。私もここで手を挙げました。「最後に、『五十』だと思うひとー」、七〜八人が手を挙げましたが、一番少ない人数でした。「それでは答え合わせをしましょう!正解は『二パーセント』です。日本では当たり前には飲むことができる水ですが、世界では飲み水に出来ているのはごくわずかな割合なのです」と話してくれました。
そして、「それでは第二問、皆さんは飲める水と飲めない水をどうやって判断しますか?」と言って、職員の方は水が入ったコップを机の上に置くと、「この水はあるものが入ってます。何が入っていると思いますか?近くで見ても大丈夫ですよ」と話を続けました。離れた席に座っていたので、少し近寄ってコップの水を見ました。水は濁っていて底の方は見えず、泥をかき混ぜたような濁り方でした。皆がコップを見終わったあと、職員の方は言いました。「このコップのなかには牛乳が一滴分入っています。一滴だけでも水にとっては汚染の原因になるんです。」
私はびっくりしました。家に帰って、日本の水について調べてみると、国土全体で水道水を安全に飲むことができる国は、世界の中でも十五カ国しかないのだそうです。この「特別授業」で教わったことを家族に話してみると、姉がうなずきました。そして、「私が外国に行ったときには、ガイドさんから水道水や飲食店で出された水は飲まないようにと言われたよ。飲むときは買った水じゃないとお腹を壊しちゃうんだって」と話してくれました。
日本では、公園や学校にある蛇口をひねれば当たり前のように水が出て、その水を飲むことができます。同じように、どの国でも水道水は飲めるくらい綺麗なものと思っていました。しかし、「特別授業」での話を聞き、世界では水道水が飲めることは当たり前ではないことを知りました。そのことを知ったときの驚きは今でも覚えています。
現在の日本では、浄水処理で綺麗な水道水を飲むことが出来ますが、これは昔の人たちがその礎を築いてくれたからです。そして、今も水道水を綺麗にしてくれている人たちがいることを忘れないようにしたいです。また、これからも綺麗な水道水を保っていくためには、私たち一人一人の努力も必要です。今は、生活排水を減らすことを心掛けているぐらいですが、こうしたことも続けていくことが大切なのではないでしょうか。最近はテレビなどで「SDGs(持続可能な開発目標)」についての話をよく耳にします。そうした中で自分が取り組めることを探していきたいと思います。
入選: 川崎市立菅中学校 3年 泰山 愛深
水は幸せの宅配便
水は、生物が生きる上でも新たな世界を切り拓く上でも必要なものだと思います。理由は、大昔の生物は水の中で進化をして陸に進出し、より良い暮らしや世界をつくっていく私達人間は、おいしい水を飲んで生きているからです。
今私が水道の蛇口をひねれば、澄んでいるおいしい水が流れてきます。その水を沸かしてコーヒーを入れたり、朝に顔を洗ったり、食器などの汚れを落とすなど日常生活の中で当たり前のように使っています。そんな水ですが、私達の家に届いて安心して飲めるようになるまでは、多くの人々の苦労と長い歴史があるのです。
今年、川崎市の水道は百周年を迎えます。百年前は今と全く違い、当時の人々はたびたびの水不足に苦しんでいたのでしょう。また、工場を誘致して川崎の発展をめざすためにも水道の整備が必要であったのかもしれません。そんな時代背景から浄水場がつくられ、家庭や工場へと給水していきました。その後は人口の増化に伴い、幾度もの拡張事業が進められて私達の家に届くようになりました。そこには、川や湖から水を引く人や、ダムをつくる工事をする人、浄水場をつくる人、水道管をつくる人、水をきれいにする人などの多くの人々が関わっているのです。そして、私達に水だけではなく、暮らしや笑顔を運んでくれているのです。なので私は、水を、笑顔を届けてくださった人々に「ありがとう」と伝えたいです。
私は水が大好きです。理由は、おいしいからはもちろんですがプールが好きだからです。プールに入ると、ふわふわした不思議な感覚になり、ワクワクした楽しい気持ちになります。そして、みんなが笑顔で遊べるのです。このように、水には人を楽しませる力があると思います。水の音を聞くだけでリラックスできますし、夏になれば海や川に行って水遊びも楽しむでしょう。暑い日にぴったりなスイーツのかき氷の氷だって、元は水です。身近すぎて気付かないのかもしれませんが、私達は豊かな水とともに暮らしているのです。
そこで思いました。もしも、この世界から水がなくなってしまったらどうなるのだろうか。まずは日常生活の中から考えていこうと思います。朝起きて顔を洗うのは、しなくても大ごとになるようなことではないので大丈夫とすると、朝ご飯で考えていきましょう。主食のお米は、炊く時に水が必要です。もっとさかのぼっていくと、育てる時も多くの水が必要なことに気づきます。そう考えると、お米を食べているのは私だけでなく世界の多くの人が食べていますし、朝だけではなく昼や夜も食べると考えれば、必要な水の量はとても多いことが分かります。お米に限らず、野菜や魚でも同じように、水がなくなれば育てることができなくなって食糧戦争が起こるかもしれません。つまり、水は世界の穀物を育てるだけではなく平和を守っているのです。すごいと思いませんか。
そんな水も、限りある資源の1つです。世界では今、環境破壊のために湖から水が消え、干上がってしまっている場所もあります。そこに暮らす人々は水不足に苦しんでいるかもしれません。だから、私達はこの国の、世界の水を大切にするべきだと思います。私が暮らす川崎、いえ日本は、美しい自然に囲まれ、緑豊かで水もキレイでおいしいです。この豊かな水を、みんなで守っていけたら嬉しいです。
ところで、人が使える水はどのくらいか知っていますか。地球の水のほとんどは海水で、人が使える水は、地球上の水全体の約〇・〇一パーセントしかありません。私もこれを知った時は驚きました。雨などで補給はされていますが、とても少ないから大切にすべきというのがわかると思います。
ある時は人と人を結び、またある時は笑顔を運び、平和を守る。そんなすばらしい不思議な力をもつ水が、私は大好きです。水には、まだまだ秘められた可能性や力があると思います。この先もずっと大地を潤し、多くの笑顔を運んでいくために、もっと水を大切にしていきたいです。
入選: 該当者なし
入選: 該当者なし
お問い合わせ先
川崎市上下水道局サービス推進部サービス推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3097
ファクス: 044-200-3996
メールアドレス: 80suisin@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号138247