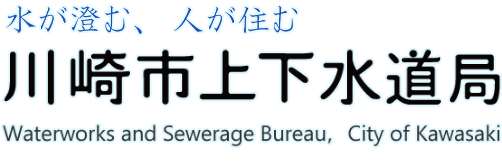第65回水道週間 川崎市小・中学生作品コンクール 入賞作品 作文の部
- 公開日:
- 更新日:
小学校低学年の部
特選: 該当者なし
準特選: 該当者なし
準特選: 該当者なし
入選: 川崎市立子母口小学校 二年 村山 和
「水のおかげで」
わたしは、たまにこうかんがえます。
「わたしたちは、すべて水のおかげで生きているんだ。」
と、思います。たとえば、水がないと、おふろも入ることができないし、トイレもできない、手もあらえない。そしてごはんだってたべれない。本とうになにもできない。
わたしたちだけではない。どうぶつだって、虫だって、そうなの。だからちきゅうの生きものはすべて水のおかげ。これからも、いままでも、水のおかげ。これからも、水にかんしゃしなくっちゃ。日本はいまのところ、せんそうがないからあんぜんにしぜんに、水のおかげで生きてる。いままでは、ふつうにくらしていたけれど、わたしはさいきん、生きることは水のおかげときづいて、水をむだにしないようにきおつけています。おふろだって、あたまをあらっているときはシャワーをあまりださないようにって。トイレも、のぐそするしかない。ごはんも、カップラーメンさえたべれない。あと、手をあらわないと、手が、ばいきんだらけ。みんなみんな、水にかんしゃしてる。いままでもこれからも、ありがとう水。ってかんじ。花火があがったときぐらいのうれしさで水にかんしゃしてる。
わたしたちの水。かんしゃの水。
入選: 該当者なし
入選: 該当者なし
入選: 該当者なし
入選: 該当者なし
小学校中学年の部
特選: 該当者なし
準特選: 川崎市立川崎小学校 四年 酒井あさと
水がきれいなのは当たり前じゃない
わたしは社会で水の学習をしました。その時、きかいの手入れなどを人の手で行なっていることを知り、すごいと思いました。そして、宮がせダムを作るときの村の人の意見も知ることができました。ダムを作るとなると、村の人は家をこわさなければいけません。その時わたしは、「自分たちの思い出の場所を自分たちでこわすなんて。」とむねが苦しくなりました。そして、わたしが村の人だったら、ぜっ対いやで反対すると思いました。それでも、宮がせの人たちはゆずってくれていたので、やさしいと思います。いろんな立場のいろんな気持ちがあるので、ダムを作るのは大変なんだなと思いました。
そうやって水を作るのは大変なのに、学校の水道では水が必要ない時にもジャバジャバとじゃ口から出ていました。わたしは二年生のころから水のむだづかいが気になるようになりました。「もったいない」というふうに感じていました。なぜなら、いっしゅんで水が洗い場についたらその後は、下水道を通って行ってしまうからです。
そして、日本みたいに水がとう明できれいじゃない国もあります。その国ではコロナの中でも手を洗う水がなかったりしています。あったとしても水がとう明じゃなかったり、きれいじゃない水です。その国の人が日本の水の使い方を見たら、きっと、おこると思います。よごれた水がげんいんでなくなるにゅうよう児の数は、一日八百人以上だと本に書いてありました。それを読んで、そんな事ってある?と思いました。でもじっさいに、その様なことがあっておどろきと悲しみがありました。水がきれいなのは当たり前じゃありません。日本では水道の水にかぎりがないように感じますが、本当はあります。水がない国に分けてあげられるくらい大切に使いたいです。
わたしは、手を洗う時など水が必要ない時には出さないように気をつけています。そして、おふろの水や、お米をといだ水などを花にあげたりしています。他にもできることがあったらしたいです。そして大きくなったら水がきたない国がないようにしたいと思いました。
準特選: 川崎市立川崎小学校 四年 島田 弥空
未来につながる浄水場
私は最近学校で水の学習をしました。浄水場やダムの仕組みについて調べました。浄水場は人が水をきれいにしていることですが、自然の力で水をきれいにしていることがあります。
それは川の流れです。川は、上流から下流へと流れていく間に岩や石などを運びながら水をきれいにしていきます。これは家にある活性炭の入った浄水器と同じ仕組みだと聞きました。川の上流では川の流れがはげしいため川の底や山はだをけずります。中流は上流でけずった岩や土を運んでいきます。下流は流れがゆるやかになってきた所で小石や土をつもらせます。こうして粒の大きさのちがうたくさんの岩や石、砂利の間を通ることによって水がろかされていくそうです。私は川の仕組みをじゅくで習った時、川の水の勢いで岩がけずられてどんどん小さくなっていくことだけしか理かいしていませんでした。けれど、そのかていで水をろ過しながら流れていたということに気づいてあらためて自然の力ってすごいなと思いました。
これに対して浄水場では、活性炭などを使ってカビなどのにおいをとりのぞいたり、薬品(ポリ塩化アルミニウム)を加えて、どろや砂などをかためて水の底にしずめることでとりのぞきやすくする仕組みがあります。さらに小さなどろや粒などをろ過池という砂や砂利のそうを通してきれいにしていきます。浄水場ではさらに塩素という薬品を使って消どくし、安全な飲み水にしています。人間の発明した技じゅつもすごいなと思いました。
この二つを比べてどっちの方がいいのかなと思い、いろいろ調べました。人口ぞう加や工場のぞう加によって川がおせんされ、自然の力だけできれいにするのは限界がでてきたれき史を知りました。安全な飲み水を手に入れるために浄水場ができ、人間の技じゅつによってきれいな水をたくさん得ることができるようになりました。だから浄水場の方がいいかなと思いました。けれど、浄水場やダムを作ることは同時に自然をはかいすることになったり、そこに住んでいる人々が家や村を失うことになることを知りました。私はすごく悲しい気持ちになって、考えが少し変わりました。ただ浄水場をふやせばいいということではなく、工夫が必要だと感じました。
川の自然の力だけにまかせた水をきれいにする能力には限界があるので、浄水場はこの先も必要になってくると思います。しかし、浄水場を新しく作ることで家を失う人々のことを考えると私は心からさん成はできません。だからこれから浄水場を作るとしたら私だったら次のような工夫をします。たとえば、浄水場の面積をできるだけ小さくするためにたてに長い浄水場を作るとか、より浄化能力の高い薬品を開発するなどといった技じゅつ開発をしたいです。その前に、水を出しっぱなしにしない、ポイ捨てをしないなど今できることにはしっかり取りくんでいきたいと思います。
入選: 川崎市立小杉小学校 四年 小沢 和奏
安全安心な水
ただ蛇口をひねったり手をかざしたりするだけで出てくるわたしたちにかかせない水はどうやってわたしたちの所へ来るのかを4年生の社会の学習しました。
あたり前のように使っている水には、ダムのために住みなれた村をはなれてくれた人、ボランティアで水源林を守る活動をしてくれている人、安全安心な水をいつでもわたしたちにとどけてくれるために浄水場で24時間交代で働いてくれている人など、たくさんの人のいろいろな思いがあると言うことを知りました。
その事を家で話すと、お父さんが世界にはきれいな水を飲むことさえできない人たちがいると、ユニセフのホームページを見せてくれました。
そこには、安全な水を手に入れられない人は世界で約6億6300万人いると書かれていました。
どろや細菌、動物のふんやにょうなどがまざったよごれた水を、子どもたちは何時間も歩きくんでいるそうです。生きるために飲んでいるそのきたない水が原いんで、なくなってしまうわたしたちよりも小さな子どもは年間30万人、毎日800人以上もいるそうです。
わたしは、毎日あたり前のようにきれいなトイレに行き、おふろに入り、きれいにせんたくされた洋服を着て、きれいな水を飲み、温かいご飯を食べています。そして学校でたくさんのことを学び、友だちと遊んでいます。
夏には家族とプールに行くことを毎年楽しみにしています。このあたり前が本当はあたり前のことではなく、とても幸せなことだと分かりました。幸せな毎日をすごせることをたくさんの人にかんしゃをして、今まで以上に水を大切にしていきたいと思います。そして、世界の全ての人たちに1日でも早く安全安心な水がとどくようにねがっています。
入選: 川崎市立梶ヶ谷小学校 四年 今村 天音
くろうをかけないための節水
わたしは社会の学習でダムやじょう水場のことを学びました。その中で節水を知り、ダムやじょう水場で働いている人たちにくろうをかけないためにいつでもどこでも、どの場合でもトイレに行くときなどかならずトイレを小で流したり、節水をすることを心がけていきます。
わたしがやっている節水はシャワーの水を1回1回止めたり、トイレの水をなるべく小でながしたりしています。
ちなみにシャワーを一回一回止めれば12Lですが、流しっぱなしだと36Lとものすごくさがあります。
なので自分以外の人にもこの方法をやって24Lの節水に協力して節水してほしいです。
もう一つ取り組んでいるのは歯みがきのときにコップを使うことです。
ちなみに歯みがきのときにコップを使うと0.6Lしか水をつかいません。
とりくみたいことは、おふろののこりゆをせんたくにつかったりしたいです。
これからもいろいろな方法の節水をして、じょう水場の人たちにくろうをかけないように生活していきたいです。
入選: 川崎市立西梶ヶ谷小学校 四年 伊東 篤希
かがやく水
みなさんは水のありがたみを感じたことはありますか?
水は身近にありますが、とつぜん水がなくなったらどうでしょうか。もちろん農作物は育ちませんし、のどはからっからになってしまいます。ほかにも、魚だっていなくなってしまいます。なので生き物にとって、水はとても大切なのです。
学校では、プールの時期に二千百三十立方メートル水を使ったと先生から聞きました。一リットルの牛乳パックで計算すると、二百十三万本です。そうぞうもつかないその数にびっくりしました。
今はあたりまえのように水がありますが、昔はどうでしょう。
昔の人は、雨水をため、その水を多くもっている人が売って生きていました。水を手にすること自体むずかしかったのです。今は、使いたいときに使いたいだけ水がつかえます。しかも水道の水もきれいになっているので、昔の人にとってそのことをきいたらかんどうすると思います。
ぼくは、黒部ダムにいったことがあります。そのときは、水のいきおいがすごいなぁと思っただけで、知りませんでした。今、黒部ダムの写真を見たらとても考えてしまいます。黒部ダムは、完成するまで何人もの人を死なせてしまいました。なので写真を見ると、毎回思い出してしまいます。ぼくが水を手にするまで、たくさんの人達の努力や思いがあるのだと考えさせられます。
今ぼくは、社会のべん強をしています。
日本の水のきれいさは、いつかなくなるかもしれません。なのでぼくは、水一てき一てきとても大切に使います。
ぼくはこのあと社会のべん強をより深くべん強して、ずっときれいな水を飲めるように心がけようと思います。
一人一人にできること協力し合いともに助けあって大きなせかいのみんなのかおがにこにこになる未来になるといいなと思います。かがやく水がみんなにとどきますように。
入選: 該当者なし
入選: 該当者なし
小学校高学年の部
特選: 該当者なし
準特選: 該当者なし
準特選: 該当者なし
入選: 川崎市立川崎小学校 六年 出本 紗英
大切な水と私達のくらし
水は生き物にとってとても大切な物だ。料理にも飲む物にも必要だから、水がないと生き物は生きていけない。
アフリカでは、食料が不足している。子ども達もお腹がすいて何かを食べたいのに食べられる物がなく、いつもお腹をすかせている。だから水が必要だ。食料と水は関係ないと考えるかもしれないが、食料をつくるには水がたくさんいる。例えば、お米七十五グラムつくるのに二百七十八リットルもの水を使う。また、よく給食にでるパンも、一枚分の小麦だけで九十六リットルの水が使われている。だから、豊かでキレイな大切な水がないと、水と同様の、生活に欠かせない食料までなくなってしまう。
しかし、キレイだった水を汚しているのは私達自身だ。料理に使った油や汚れている水をそのまま流していたり、川や海にゴミを放りなげたりする人が多くいる。今はボランティア活動として川や海にあるゴミを拾ってくれている人もいるが、その活動をしてくれている人だって家庭をもっている人や仕事をしている人もいて、大変になる。だから、そもそも汚れた水を流さない工夫を一人一人が少しでも取り組んでくれたら、よりよいくらしができるのではないだろうか。料理に使った水を捨てたい時は、その油を吸収しゴミとして出したり、川や海の側にゴミ箱をたくさんおいたりしたら、水を汚すゴミが少しだけ減少すると思う。一人一人が少しでもこのような工夫をおこなったら、ゴミが減少し、海や川もより豊かな水になるだろう。
私は、食器を洗うときに油がついたお皿をそのまま水で流してしまったことがある。
だからこれからは、豊かな水にするためにどう工夫をしていくか、どうしたら水が豊かになるかを考えていきたい。また、豊かな水の大切さをたくさんの人に知ってもらい、みんなで協力し、豊かな水、そして豊かなくらしをつくるためにたくさんの工夫をしていきたい。
入選: 川崎市立西御幸小学校 六年 西井 歩
きれいな水は、豊かなくらしへ
私たちは毎日「水」を使って生活をしています。特に私たちが住んでいる日本は、水道水などの水がとてもきれいで清潔で私たちは、当たり前のようにやっている水道水を飲むということも水がきれいだからできることです。
ですが私たちがいつも使っている水道水などの水がきれいにではなくきたない水だったらどうなるでしょう。食器を洗う時、手や体を洗う時などの時に、きたない水だときれいにできなくなり次にご飯を食べる時に食中毒や病気になってしまう危険もあります。このようなきたない水を毎日使っていると、今まで私たちが送っていた豊かなくらしが出来なくなってしまいます。それだけではなく食器も体も他の物などもきたない水で洗うことになるので不衛生な環境が続いてしまいどうしても病気になる人が大量にでてしまい豊かなくらしとは程遠い状態になってしまいます。
ですがきれいなだけだといけません。水は日本だけでも約1億人が毎日使い続けています。そして一家庭あたりの1日に使う水の量は平均で214リットルも使っています。その多くは、お風呂やトイレなどで何と約60%も使っています。このように一家庭だけでもたくさんの水が必要です。そして私たちは、毎日豊かな水を使って豊かなくらしをしているのです。
つまり私達が豊かな生活をするためには、きれいで豊かな水がたくさん必要です。食器を洗う時、お風呂の時、手を洗う時、そうじをする時そして飲む時にもきれい豊かな水が必要です。これらのように私達は、きれいで豊かな水があるおかげで今のような快適でよりよい、健康な毎日を送ることができています。
日本はこのように快適に過ごせています。私は、このことはとてもすごいことだと思います。しかし他の国には、日本のように水道水が十分に使えない国がたくさんあります。日本では、シャワーなどは、ふつうにできますが他の国だと気持ちよく洗えないとお父さんから聞いたことがあります。
私は、日本は特別水がきれいで豊かだからよかったけれど他の国では、安心して飲んだりすることが出来ないのでこれからは、どこの国でもきれいな水で安心してのむことができる未来を作っていけたらなと思いました。
最後に私は、水の大切さを改めて考え、きれいな水があるだけでも今のように豊かなくらしが出来ていることが本当にすごいことだと思いました。そしてこれからもこのようなくらしが続き、他の国でも同じようにしていくのが大切だと思いました。
入選: 川崎市立梶ヶ谷小学校 六年 小宮 桜子
生きるために
私の家は、道から家に着くまで階段が四十五段あります。学校の帰りや塾の帰り、習い事の帰りなど、家にたどり着くまでに、この階段を上がらなければなりません。
一番大変なのは、忘れ物をした時です。やっと階段を下りきったと思った時に忘れ物に気付くと、もう一度上って取りに行かなければなりません。そんな時にはすぐに水を飲める環境があるとうれしいです。
SDGsに基づいて、水道の蛇口から安全できれいな水を飲める国はとても少なく、命がけで私の家の何倍もの距離を歩いて水を取りに行く人々がいます。それも、取りに行った水が安全か分からないのです。
もしかしたら、その取りに行った水が水たまりの水かもしれません。ゾウが入った水かもしれません。
日本。私たちの日常では、蛇口から安全な水が出ます。そして、近くのコンビニエンスストアや、スーパーマーケットで、安全な水を買うことができます。
しかし、水を命がけで取っていっている人はどうでしょう。
水がなければ、生き物は生きることが出きません。
人間には約六十五パーセント。ホウレンソウには約九十二パーセント。ニワトリには約七十四パーセント。ウシには約五十五パーセント。ニンジンには約六十七パーセントの水が含まれています。
私たち人間は水道やペットボトルの水を飲みますが、海の水には塩分が含まれています。水を飲むために海の一部の生き物たちは、体の中にあるろ過装置のようなもので塩分をこしとって飲んでいるそうです。体の中にろ過装置を作るほど水は必要だということです。
私は今の生活をふり返って水はどれだけ必要な物かということが分かりました。水を飲むため、生きるために進化したり、命がけで水をとりに行く人々がいることを改めて感じました。これからも、このことを意識して生活していきたいです。
私たちにとって水は命そのものです。
入選: 川崎市立宮崎台小学校 五年 清徳 柚利加
大切なしげん、水
わたしたちは、毎日あたり前のように手や物を洗うため、料理に使うため、飲むためなどに、水を使っています。日本はめぐまれていて、家のじゃ口さえひねれば水がでてきて、コンビニやスーパーに行けば安い値段で水を買うことができます。しかし、そうではない国だってあります。例えばアフリカです。アフリカでは、じゃ口をひねっても水は出ませんし、安く水が手に入るところなどありません。ただただよごれている水を、飲んだら、命を落とすかもしれない水を飲まなければ、いけないのです。そのような、安全な水が手に入らない国は、世界で六億六千三百万人もいるのです。それにくらべて日本は、水や食料にこまっている人は、ごく小数です。それに、日本の子どもはプールに入ったり、水でっぽうや水風船などで遊んだりしますが、アフリカの人は、そんなこと思いつきません。なぜなら、水がとてもきちょうだと感じていて、水不足だということを理解しているからだと思います。そんなところからでてきたのは、ユニセフぼきんです。ユニセフぼきんは、生活するだけでも大変な人などの人のためにつくられたものです。よく、学校や習い事先でぼきん活動をしているのを見たことがあります。きっとお金や食料、水などにこまっている、助けを求めている人たちを、助けてあげたい、という気持ちがあるからこそできる活動なんだと分かりました。人が少しでも多くぼきんを行うことによって1人でも多く助かるのだということを感じました。そのことを通して、わたしは、少しでも多くぼきんをして、少しでも多く水をむだ使いしないようにして、少しでも多くそのことをまわりの人に伝えていきたいし、水をむだにしないという活動の中でも、節水が特に良い活動だと思ったので、これから、せっ極的に活動をして、それをやり続けていきたいと思っています。
わたしたちは、毎日あたり前のように手や物を洗うため、料理に使うため、飲むためなどに、水を使っています。しかし、その中でも水をむだ使いしている場面はあります。手や物を洗うときなんかは、石けんや洗ざいなどで洗っている最中に「またすぐに使うからいいや。」などと思って水を出しっぱなしにしていたり、料理をするときにも水を流しっぱなしにしているときがあります。でも、水というものは、大切なしげんの中の一つです。「水なんていくらでもでてくるからいいや」というわけではないのです。1度使った水を工場の人たちが何時間も何時間も努力をしてきれいにしてもう1度使えるようにしてくれているのです。なので、どれだけ水にめぐまれていようと、水をむだ使いするということは、食品ロスと同じように絶対に良いことではないので、絶対にやらないでほしいと、わたしは思っています。
入選:川崎市立稲田小学校 六年 桐谷 日絆
水とSDGs
私がこの作文について書こうと思ったきっかけは、私はSDGsの事を調べるのが好きで、その中に水の事についてのSDGsがあるので、この作文を書こうと思いました。
まず、私は節水について調べました。日本は他の国より、多く水を利用しています。なぜなら、生活で使う水以外に、「輸入」を他国に頼っているからです。このまま日本人が多くの水を使うと、他国の生活を破壊してしまいます。これらの問題を少なくするために私達ができる事が節水です。例として、水の出しっぱなしをしない、必要最低限以外は水を使わない。などがあります。
次に日本のように安全な水がどのくらいの国で使えるのかを調べました。実は世界で数えられるほどしかありません。世界の約四分の一の人は、安全な水を使えないそうです。私はこれらの事を調べて、今の環境に感謝すると同時に、節水をして水を大切にしたいと思いました。
みなさんも今、改めて安全な水が使える環境を大切にし、自分の国だけでなく、他の国や今後の未来のために節水など自分で簡単にできるSDGsをやってみませんか。
中学校の部
特選: 川崎市立橘中学校 二年 金居 凛
無意識な水
水ほど環境によって変化する不思議な物質があるだろうか。
水には大きく分けて三つの状態がある。それは、固体、気体、液体だ。私たちが日常的に触れ合っているのは液体のときだろう。学校であれ、家であれ、場所を問わず蛇口をひねれば一瞬にして流れてくる。また、固体も気体も触れ合う機会が少ないというわけではなく、液体より気づきにくいというだけで、意識的に周りを見れば一定の確率で見つけることができる。例として気体は水蒸気、固体は氷などだ。そう、水には他の物質にはあまりない柔軟性という特性がある。だからこそ水というのは私たちの日常生活で多用される。
だが、水の柔軟性というのは時として恐ろしい凶器になるのだと歴史の授業で学んだ。熊本県で昔起こった四大公害病にも数えられる水俣病事件である。化学工場から排出された有害物質が海に放出され、そこの海産物を長期的に食べた住人が集団で神経系を患い、重症になった事件だ。水はさまざまな環境に適応する。だから有害物質と混ざりあい被害が拡大した。
しかし私たちは刺し身を食べるとき、コップに入っている水を飲むとき、「これは毒かもしれない」と思うだろうか。いや、思わない。水俣病事件以外にも水に関する公害は起こっているのになぜ、私たちは水に対して意識を向けないのだろうか。
一つ目は機関がしっかり検査しているのが分かっているからだと考える。身近な例でいうと学校の保健委員が水道の水質検査をしてくれている。通っていたプール教室では授業が始まる前に毎回検査をしてくれていた。だからそれらの水が安全だと分かる。しかしそれほど水質検査にいちいち注目している人が多いとはあまり考えられない。その理由として私たちの根底に「自分たちの水は絶対安全だ」という思いがあるからだろう。
そこで二つ目の考えだ。それは日本の環境だ。例えば発展途上国のアフリカでは水源が飲用には適していないために、動物の糞尿や細菌が混ざって人体に多大な被害がでている。一方、日本は国土の三分の二が森林である世界有数の森林大国だ。豊かな緑からできた湧き水が川に流れ、海に運ばれる。だから魚が美味しく、安心な状態で出荷できる。きれいな水源はあるし、インフラも整備されているから水を飲んでもお腹を壊すことはないし、死んでしまうこともない。そのことを裏付けるように湖やダムから給水している水道水の安全できれいな国ランキングでは三位にランクインしている。水道水を安全に飲める国が九ヶ国しかないことからも、日本の水の安全性がよく分かる。また、水がきれいということは同時に環境もきれいということだ。外の景色は透明で空気も安全。私たちは日本の安全性が無意識のうちでも分かるから水に意識を向けないのだと考える。
では、意識を向けないことが悪いのかというと私はそうは思わない。むしろ逆に意識を向けなくてもいい恵まれた環境だからこそ私たちは日々の生活に目を向け、学業や仕事に意識を向けることができる。
世界に誇る緑の豊かさの基に成り立つ「きれいな水」が今の日本人が豊かな生活を送れている理由の大半を担っているのではないだろうか。
準特選: 川崎市立橘中学校 二年 根本 紗衣
二つの水で豊かな暮らしを
私たちは普段、清潔な水を使い生活している。日本の水は世界有数の安全性を誇っているため、ほとんどの人は日々の生活・飲料用水すべてに水道水を使っているのではなかろうか。確かに、水道水は安価かつ安全だ。だが、日本のミネラルウォーターもまた、世界有数の安全性をもつことを忘れてはならない。この二つを使い分けることでよりよい暮らしを送ることができるのではないだろうか。
では、どのように水道水とミネラルウォーターを使い分けるのか。それぞれの長所と短所を整理しよう。
まず、ミネラルウォーターの特徴についてだが、ミネラルウォーターとは何なのだろうか。ここでは、食品衛生法により「水のみを原料とした清涼飲料水」と定義されたミネラルウォーター類の一種とさせていただく。ミネラルウォーターの大きな特徴は、必然的に自分の地域の水を使う水道水と異なり、自分で水の種類を選べることだ。産地に限らず、水の硬度を選択できる。硬度が高いと飲みごたえのある硬水、低いと口当たりが軽い軟水ということになる。日本の水道水のほとんどは軟水なので、あえて硬水を選ぶ場合はミネラルウォーターが適しているといえる。例えば、健康に気を遣う人やスポーツをしている人には、ミネラルを多く含んでいる硬水をおすすめする。ただし、大量に一度に摂取すると胃腸に負担をかけるかもしれないので、注意してほしい。また、不足しているカルシウムや亜鉛と同時に過剰摂取に気をつけなければならないナトリウムやリンを摂取してしまう可能性がある。その点も配慮しなくてはならない。料理で水を使う場合、塩素臭がなく、料理の味を引き立てるミネラルウォーターがよいだろう。さらに、日本料理には軟水、西洋や肉料理には硬水といった具合で使い分けができるのも、料理にミネラルウォーターを使う大きな利点だろう。
続いては水道水の特徴だ。まず一つめだが、これはもう皆さんお分かりだろう。コストパフォーマンスの圧倒的なよさだ。ミネラルウォーターが一リットルあたり二百円前後なのに対し、水道水は一リットルあたり約〇・一円という恐るべき安さである。なんと、水道水の価格はミネラルウォーターの価格の約二千分の一なのだ。なので、やはり大量に水を消費する掃除などでは、依然として水道水のほうが適しているだろう。二つめに挙げられるのは、水道水には腐る心配がほとんどないということだ。水道水には水を消毒するための塩素が含まれているため、氷にして長期保存することに適している。さらに、製氷機に水道水を入れると、塩素により製氷機のカビが発生しにくくなるという利点がある。水道水の塩素によるメリットはもう一つあり、うがいの際の消毒作用が期待されている。一昨年から続くコロナ禍で、うがいや手洗いに対する意識は高まってきているだろう。衛生の面ではミネラルウォーターよりも水道水の方に分があると言えるだろう。
さて、このようにミネラルウォーターと水道水の使い分けの例を紹介してきた。二つの水をそれぞれの特性を活用することにより、さらに豊かな暮らしを送れるのではないだろうか。ここで覚えておいていただきたいのが、この二つの水の使い分けができるのは水道水の安全性が非常に高い日本だからこそできることだということ。清潔な水は大事に使っていきたい。
準特選: 該当者なし
入選: 川崎市立川崎中学校 一年 黒澤 希美
世界中に清潔な水を
「安全な水とトイレを世界中に“だれもが安全な水とトイレを利用できるようにし、自分たちでずっと管理していけるようにしよう。”」これは、SDGsの目標。今、世界では水道の設備がない暮らしをしている人は二十億人。トイレがなく、道ばたや草むらなど屋外で用を足す人は四億九千四百万人とたくさんの人が悩んでいる。例えば、片道一.五キロメートル以上、子供にとっては往復一時間かかる道のりを歩く。それでも、一回の水くみでは十分な水を運べず、得られる水はひどく汚れている。そして、不衛生な水で体調を崩してしまう。そうすると、最悪な場合、命を落としてしまうケースも。
そこで、SDGsでは「二千三十年までに、だれもが安全な水を、安い値段で利用できるようにする。」ことや、「二千三十年までに、だれもがトイレを利用できるようにして、屋外で用を足す人がいなくなるようにする。女性や女の子、弱い立場にある人がどんなことを必要としているのかについて、特に注意する。」、「二千三十年までに、汚染を減らす、ゴミが捨てられないようにする、有害な化学物質が流れ込むことを最低限にする、処理しないまま流す排水を半分に減らす、世界中で水の安全な再利用を大きく増やすなどの取り組みによって、水質を改善する。」、「二千三十年までに、今よりもはるかに効率よく水を使えるようにし、淡水を持続可能な形で利用し、水不足で苦しむ人の数を大きく減らす。」、「二千三十年までに、必要な時は国境を越えて協力して、あらゆるレベルで水源を管理できるようにする。」を目標にし、「二千三十年までに、集水、海水から真水を作る技術や、水の効率的な利用、排水の処理、リサイクル・再利用技術など、水やトイレに関する活動への国際協力を増やし、開発途上国がそれらに対応できる力を高める。」ことや、「水やトイレをよりよく管理できるように、コミュニティの参加をすすめ、強化する。」ことを実現のための方法としている。
私たちもできることはないだろうか。日本は水を大量に使っているそう。私たちが節水をすることで、他の国の人に割り当てられる水が増えるかもしれない。私たちの身の回りに何か協力できることがあるかもしれない。他人ごとのように思わないで、顔を洗うときや歯磨きをするときなど、水を出しっぱなしにしないこと、食器・フライパンは、油汚れなどを新聞紙や布で落としてから水洗いをするなど自分にできる節水の仕方を考えて実践してみてほしい。
私たちが当たり前のように使っている水。世界では、水がなかったり、、汚かったりして苦しんでいる人々がいるため、「水があるのが当たり前」と感じてはいけないと思った。清潔な水であり、安心して飲めるだけでも幸せなのだから、私も節水をすることを普段から心がけて自分も苦しんでいる人を助けたいと思った。早く世界のすべての人々に清潔で安心して飲める水を平等に行き渡ってほしい。
入選: 川崎市立西高津中学校 一年 中野 真緒
使える水
みなさんは、水の循環について知っていますか。そう、雨が降り川に流れ、というものです。水の循環というと、水が常に循環していて、水は無くならない、というイメージがあるのではないでしょうか。でも私たちが使える水に注目してみるとどうでしょうか。水の循環の中に使える水は入っています。しかし、使える水は、本当に無くならないのでしょうか。
私たちが使っている水は、浄水場できれいにされています。きれいでおいしい水が飲めるのも、このおかげです。つまり、使える水はきれいにするという手間がかかって出来ているのです。ここで循環の話に戻ります。循環した水は、浄水場にいき、きれいにされます。さて、循環した水がすぐにきれいになると思いますか。循環した水が、すぐに使えますか。答えはいいえです。きれいになるのも、使えるようになるのも、どちらも時間がかかります。新たにできる使える水が届くよりも、先に使える水を全国の人がたくさん使ったら、使える水はどんどん減っていきます。そうやって使い続けたら、使える水はどうなるでしょうか。使える水は、有限です。使い続けたら、使える水はいつか無くなってしまうのです。今、毎日のようにきれいな水を使えているのは、浄水場できれいな水が作られ、それが届けられているからです。水の循環は無くならないといえど、使える水の循環はと中でとぎれる可能性があります。その可能性があるかぎり、水は貴重なのです。
水は、どんなときでも、私たち人が、動物が、植物が生きるために必要な物です。そんな水を毎日使えているのは、とても豊かな証こです。世界には、私たちと同じようにきれいな水を使えない人たちがいます。私たちは、とても豊かな国に産まれてきたのです。使える水は、世界にある水と比べると、とてつもなく少ないのです。災害などで断水が起きると、水の重用さがさらに分かります。水は、身近にあるものですが、いつ無くなるか分からない、そんなものでもあります。私たちは、水に支えられながら生きているのです。
豊かな水には、日本の水にめぐまれている環境と、浄水場などの水の設備、そして私たち人が関わっています。豊かな水は、自分たちで作ることができるのです。水に囲まれて生活している私たちは、水があるのがあたり前になっています。そんな中でも、水の大切さを忘れないことは大事な事になっています。
水は無限で、有限なものです。たくさんあるからたくさん使えて、無くなってしまうから新たに作るということが、私たちの生活に大きな影響を与えています。水道から水が飲めるのも、その影響の一つです。この豊かな生活を、これからも続けていくために、私たちは、水に向きあって、人と水、たがいのために行動をするのです。水は、どんなときも、いつだってそばにいる、人類の成長の証でもあります。水は、守らなければいけない、守り続けなければいけない、人類の豊かの宝物なのです。私は、そんな水に感謝を伝えます。「命を支えてくれてありがとうございます。」
入選: 川崎市立菅中学校 一年 池田 大真
水の大切さ
人間は古くから水を使用しています。飲料水としての使用はもちろん、まき水などにも使用してきました。そんな人間の生活に必要な水ですが、最近となって値上げされているのは知っていますか。その理由は単純で、水が貴重になってきたというのが主な要因だと考えられています。
水が貴重になってきたというのは、水不足が発生していることをしめしています。世界全体で見たとき、二〇二〇年時点で五人に一人が水不足になっていると考えられています。日本ではまだ水不足が発生していませんが、二〇五〇年には日本でも水不足が発生していると考えられています。そう考えると、水不足について知り、解決に導きたいと考えますよね。
そもそも、昔はあまり水不足が発生していませんでした。なぜ最近で水不足が発生しているのでしょうか。要因として主なものの一つに「人口の増加・産業の発達による水の無駄使いの加速」というものが挙げられています。この水の無駄使いというのは本当にささいなことで例を挙げると歯みがきや手洗いの最中の水の出しっぱなしなどの日常生活に関係することから、スプリンクラーを停止するのを忘れるなど、注意不足が要因の無駄使いから、料理の食材を何度も何度も必要以上に洗ってしまうなどの単純な無駄使いまで多くあります。
日本では世界的に見ても国民が水に対してあまり考えていない国です。その心構えが水の無駄使いを生み出し、そのせいで日本人は一日で二百リットルから三百リットルもの量になる水を一人で使用しています。この二百リットルから三百リットルという数字は、世界平均のおよそ二倍というとてつもないものになってしまっています。日本人がしてしまっている水の無駄使いが、世界の水不足に拍車をかけてしまっているのかもしれません。
それでは、「日本のせいで世界の水不足に拍車がかかる」ということをそ止するためには自分たちが何を行えばいいのか考えてみましょう。まず、行うことを一言で表すと「節水」です。その中でも有効な具体例を出すと「炊事」、「歯みがき」、「洗濯」、「洗車」の四つがあります。炊事に関する節水方法は、前述した食材の洗いすぎで一人当たり一日で三十リットルから四十リットルも無駄にしていると考えられているので、洗いすぎをやめれば節水していると言えます。歯みがきに関する節水方法はとても簡単で、「歯みがきをしている最中に水を止める」というものです。水道では三十秒でおよそ六リットルの水が出るので、歯みがきを五分間しているなら、六十リットルも水を無駄に使用していることになります。そしてこの節水方法は、歯みがき以外でも、顔や手を洗うときにも活用することができます。洗濯に関する節水方法は、「洗濯で使用する水をお風呂の残り湯にする」というものです。お風呂の残り湯を使用するということなので、水温が高く汚れ落ちも良くなります。また、浴槽は小さなものでも二百リットルはあるので、洗濯以外にも植木への水やりやまき水などにも使用することができます。洗車に関する節水方法は、「ホースではなくバケツを使用する」というものです。一般的な洗車をバケツで行うと、およそ三十リットルで足ります。しかし、同じ大きさ、同じ方法の洗車をホースを使用して行うと二百四十リットル程の水を使用しています。この二百四十リットルという数字は、バケツを使用する洗車を八回行って使用する水の量と同じです。そして、バケツを使用することで使用しないで済むこの二百十リットルがあれば日本では一日程度、外国では二日程度の生活ができます。今、紹介した四つの節水方法を行うと、一人が一日でおよそ百六十リットルの量の水を節約することができます。この節水方法を日本にいる全員で行うと一日でおよそ百九十億リットルの節水を行っていることになります。
二〇二〇年時点では、四人に一人が水不足に苦しんでいるといわれています。さらに、二〇二二年では五人に二人が二〇五〇年には二人に一人が水不足になるという予測がたてられています。二〇五〇年の二人に一人が水不足というものの中には、日本やアメリカ合衆国などの人々もいると考えられます。今、行ってしまっている日本人の水の無駄使いのせいで約三十年後の人々を死のふちまで追いつめています。約三十年後の人々を死のふちから救うためには節水することが大切です。未来の命を水不足から救い出すことができるのは、今、生きている我々だけです。
入選: 川崎市立菅中学校 一年 鷲山 雄哉
水は限られた資源
蛇口をひねると簡単に出てくる水。そのことを、当たり前のことのように考えてはいませんか。
まず、僕たちの体の中には、たくさんの水分が含まれています。身体の中の六十パーセントは水分でできており、これは体液とよばれる水分でできています。まさに、人間は水でできているといっても、過言ではないのです。そして、体液というのは、飲料水でとった水分が腸から吸収され、血液などになったものをいいます。また、体液は人間の体にさまざまな役割を果たしています。例えば、酸素や栄養分を身体中に運び、老廃物を体外へ出したり、皮膚への血液の循環を増やし、汗を出して体温を一定に保ったりなどの働きがあります。これらの働きのおかげで、良い環境を維持することができるのです。
次に水の使用用途についてです。まず、日本が最大限に利用することのできる水の量は、理論上で約四千二百億リッポウメートルあります。その中でも、実際に使用される水は、生活用水として約百五十億リッポウメートル、工業用水として約百六億リッポウメートル、農業用水として約五百三十五億リッポウメートルあります。その合計量は、約七百九十一億リッポウメートルになります。その他にも、水は発電所や建物を作る際などに使われています。また、使用されなかった水は、地下水として貯えられたり、海へ流したりしています。
ところで、こんなにも水があるのなら、日本が水に困ることはないといえるかもしれません。確かに、他のアフリカやアジア地域の水不足と比べると、まだまだ大丈夫な気もします。しかし、日本も水不足になる可能性があると言われています。主な理由としてあげられるのが、地形、水の使用量、降雨量の三つです。
地形による水不足というのは、どんなに沢山の雨が降っても、海に流されて、水が確保できないことをいいます。なぜなら、日本は山が多く、大陸の国々と比べて土地が狭いことから、河川が急になり、距離も短いといった特徴があるからです。実際に、一九九四年にこのような地形を理由から、渇水が起きました。
次に、水の使用量による水不足です。日本の年間の降水量は千七百十八ミリメートルであり、これは世界平均の約二倍です。しかし、国の面積に対して人口が多いことから、一人当たりで見ると、世界平均の四分の一程度なので、意外と水が足りていません。それに対し、日本の一人当たりの水の使用量は、二百リットルです。これは、世界平均の倍になっています。無駄な消費があるのが分かります。
最後に、降雨量による水不足です。なぜなら、温暖化のせいで、降雨量のバランスがとれなくなっているからです。実際に、今年は大雨やゲリラ豪雨などがありました。これらの大雨は、短い期間で雨がたくさん降ります。なので、短い期間の大雨が増え、雨が降らない日数も増えているのが現状です。このように、たくさんの雨が降る時期は災害レベルの洪水や土砂災害などが起こり、雨が降らない時期は渇水が起こり、水不足になってしまいます。実際に、今年の梅雨は明けるのが例年よりも、異常に早かったです。なので、渇水が起こり、植物や野菜が上手く育たず、焼けてしまったり、枯れてしまったりする被害がありました。
このように、水不足は地形、水の使用量、降雨量の三つからできています。これらの水不足を、少しでも対策するために、必要なことは節水です。例えば、水を出しっ放しにしないことです。実際に、蛇口から出る水は一分間に約十一リットルほどです。なので、歯みがき中やお風呂に入る時も、水をこまめに止めることが重要です。また、この他にも節電が大切なことの一つです。なぜなら、水不足の原因に温暖化現象があるからです。例えば、電気をこまめに消すことです。これだけでも節電になり、温暖化対策、水問題につなげていくことができます。
このように水不足はとても重要な問題です。なので、身近にできる節水や節電などの対策をしていくことが大事です。今はまだ、水に困っていなくても、いつか水が減ってしまうかもしれません。だからこそ、水が出てくることを当たり前のように思わず、少しずつ対策していくことが大切なことだと思います。
入選: 該当者なし
お問い合わせ先
川崎市上下水道局サービス推進部サービス推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3097
ファクス: 044-200-3996
メールアドレス: 80suisin@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号147835