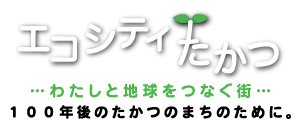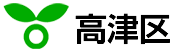「たかつ水と緑の探検隊」第1回の記録
- 日時:平成26年2月22日(土) 13:00~15:30
- 場所:川崎市立緑ヶ丘霊園内の森
- 講師:岸 由二先生(「エコシティたかつ」推進会議委員長、慶應義塾大学名誉教授)
- 参加人数:約13名
1 森の観察
歩道からの観察

森の観察の様子
一方、落葉樹が多く林床が明るい森では、アズマネザサ(シノダケ)などの下層植物が繁茂しています。このような場所は、下草や堆積した落ち葉などが一旦雨を受け止めるため、保水力が高く、あまり土の流出がありません。また、このような場所にはたくさんの生きものが棲んでいます。
谷戸の観察

谷戸の森の様子
スギやシラカシなどの常緑樹を間伐し、シュロやアオキなどを取り除くことで林床を明るくし、下層植物の回復を図ることが重要です。林床が明るくなれば、谷戸の上部にわずかに残っているアズマネザサが回復し、森の保水力を向上させることができます。
ただ、間伐後の下層植物が回復するまでは、一時的に保水力が低下するため、土の流出を防ぐための、間伐した樹木を活用したカントリーヘッジを設置します。
2 外来植物(トキワツユクサ)の駆除

雪によるトキワツユクサの駆除作業
谷戸の入り口付近にもこのトキワツユクサが繁茂しており、駆除作業を実施しました。
通常は、根ごと抜き取り駆除しますが、トキワツユクサは低温に弱いことから、先週の大雪で付近に残っていた雪で覆うことによる駆除を試みました。次回3月15日の探検隊で雪による駆除の効果について確認することとしました。
3 湧水地の観察とメダカの放流
湧水池では、事前に事務局側で採取した生きものを観察しました。
【見つけた生きもの】
- アメリカザリガニ(約20匹)
- ヨコエビ(1匹)
- マツモムシ(1匹)
アメリカザリガニ以外の生きものがほとんど見られませんでした。
生きものが少ないため、参加者でメダカを放流しました。メダカを放流することで、メダカを食べるギンヤンマのヤゴが棲むなど、生きものが賑わう池になることが期待されます。

湧水地の様子

参加者によるメダカの放流