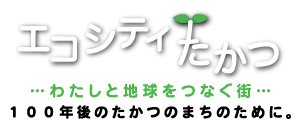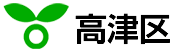学校流域プロジェクト

環境学習・地域交流・防災拠点の整備 学校は、子どもの学習の場であるとともに、子どもの学習活動や創造的な遊びにさまざまに接することを通して保護者、教員、地域市民が交流し、学校と地域文化が相互に影響を与えあう場でもあります。また、緊急時には、地域の防災の拠点として活用されます。
このような相互の交流の深まりにも期待しつつ、学校を、将来を担う子どもたちが、身近な場所で自然や水循環の仕組み、さらには自然再生の過程を実感する場として位置づける。また同時に、健全な水環境のもとに生きものの賑わいを再生し支える地域のモデル基地としても位置づける。そして、各種のビオトープや雨水利用施設などを計画的に整備し、学習活動、課外活動、地域との交流活動等に活用します。
適切な年度計画のもと、小学校で取り組みを開始し、高津区全ての学校への展開を目指します。また、プロジェクトを進める上で、地域の町内会や、市民グループ、NPO、行政等の連携等は欠かせません。財源の確保や人材の育成なども同時進行または検討します。
ビオトープとは?
高津区内の小学校ビオトープマップ
具体的な内容

ビオトープの創出とモニタリング、管理、活用
学校がある土地や自然、既存の施設などを活かし、ビオトープを創出します。
- 水のビオトープ…雨水利用を工夫した池等
- 草地のビオトープ…蝶やバッタが暮らせる在来植物の草地
- 森のビオトープ…蝶や鳥が採餌や巣作りの頼りにできる落葉樹主体の木立、落葉樹の落葉落枝は堆肥や保水土壌づくり等に活用
学校の敷地内に降った雨水の保水の推進
雨を貯留する施設を工夫し、校庭の保水を進めます。
貯留雨水の活用
貯留した雨水を、ビオトープや花壇への水まきに利用します。
学校教材としての活用
ビオトープや雨水の利用などを通して、生物や健全な水の循環、学校を含む足元の小流域、それを含むさらに大きな流域・水系について学び、学年をこえた学習教材として活用します。
人材の育成
推進体制など
区内の学校を地域の拠点として、学校、地域の町内会や市民グループ、NPO、行政が連携して進めていくこととします。2008年度に先行的に再生整備した久地小学校、西梶ヶ谷小学校のケースを参考としながら、その地域の状況に応じた柔軟な推進体制を構築していきます。
「学校流域プロジェクト」ロゴマーク
ロゴマーク1

ロゴマーク2