第2章 川崎市政の現況と課題
- 公開日:
- 更新日:
「第1章 危機にある川崎市財政」は,<1>市税収入と歳出総額とのギャップがさらに拡大傾向にあること,<2>このために,川崎市がかつてない財政逼迫に直面していること,<3>さらに,市税収入を含む歳入総額は,今後も伸び悩む情勢にあることを,説明しました。これを受けてこの「第2章 川崎市政の現況と課題」においては,歳出構造を分析し,その硬直化が進んでいることから,これまでの部分的改良では,このままのサービス水準すら維持できない危機的状況にあることを説明します。
1 硬直化の進む歳出構造
市税収入をはじめとする歳入総額に増収を期待できないとすれば,それに見合った水準にまで歳出総額を削減することによって,はじめて収支は均衡水準を回復することとなります。しかし,残念ながら,これまでの豊かな歳入構造に支えられてきた川崎市の歳出構造は,相当程度,硬直化が進んでおり,にわかに歳出削減できない状況に陥ってしまっているのです。以下,この点を人件費・扶助費・投資的経費の3つに分けて説明します。
グラフ2-1-1 一般会計歳出決算額の推移
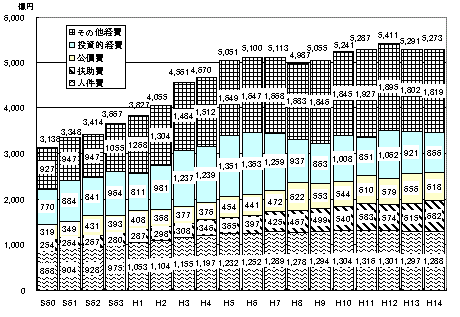
(1)人件費
他の指定都市と比較した場合の川崎市の特色は,普通会計総額に占める人件費の割合の高さにあります。そして,この高い人件費が歳出構造の硬直化をもたらしている要因の一つなのです。一部の民間企業のような人員削減や大幅な給与体系の見直しは現行の公務員制度の下では困難なことですが,率先して改革しなければならない課題は,職員配置と人事・給与制度に係る内部改革なのです。この点については,「第4章 行政体制の再整備」で詳しく述べますが,その課題について簡単に言及するとすれば,次の2点となります。
ア 職員の高年齢化と人件費単価の高騰
川崎市の平成12年度の普通会計総額に占める人件費の割合は,23.1%で,指定都市のなかでもっとも高く,指定都市平均(17.2%)と比べて5.9 ポイント高い水準にあります。昭和40年代から人件費比率が高かった川崎市は,その後も,高度成長に伴う労働力の流入や北部地域の宅地開発に伴う急激な人口の増加を受けて,指定都市への移行(昭和47年度)前後に大量の職員を採用しました。このときの団塊の世代を中心とする職員の高齢化が進み,年功序列型賃金体系のなかで,必然的に人件費単価が高くなっています。
イ 直営方式と手厚い職員配置
川崎市は,市民一人当たりの職員数が,他の指定都市に比べて多くなっています。これは,<1>保育所運営,ごみ収集・処理,道路維持補修業務,その他施設管理業務等について,その多くを直営方式で事業実施してきたこと,<2>市民サービスを提供するために,国基準等よりも手厚い職員配置が行われてきたこと,などが主な要因としてあげられます。
(2)扶助費
歳出構造硬直化の大きな要因の一つは,大幅な扶助費の増加にあります。平成12年度の扶助費575億円は,平成2年度の298億円の約2倍に相当します。歳出全体に占める扶助費の割合も高くなってきており,普通会計総額に占める割合は,平成2年度の7.5%から,介護保険制度が導入される前年の平成11年度には11.2%と,3.7ポイントも上昇しています。こうした扶助費の大幅な増加傾向については,次のような要因が考えられます。
ア 高齢者人口の急速な増加の影響
川崎市における全人口に占める高齢者人口比率は,昭和45年の3.4%から,平成12年には,4倍近い12.4%となりました。全国的にもかなり高齢者比率が低かった時代に設計された施策は,寝たきりや痴呆性などの高齢者介護に要する費用の増加を招くだけではなく,一般高齢者に対する給付やサービス費用の増加にもつながっています。
イ 一般財源の負担増に直結する単独事業費の著しい伸び
扶助費のなかで,補助事業費は平成2年度の232億円から平成12年度には192億円増加して424億円となっていますが,単独事業費は,平成2年度の 66億円から,平成12年度には2倍以上の151億円となっています。これは,老人医療費助成費(67歳から69歳までの高齢者に対する市の単独事業)の増加や,対象年齢の相次ぐ引き上げによる小児医療費助成費の増加などによるものです。
また,事業費に占める一般財源の額をみますと,補助事業費が総額424億円のうち123億円であるのに対して,単独事業費は,151億円のうち137億円と補助事業費を実額で上回っています。
ウ 生活保護費の大幅な増加
扶助費に占める生活保護費の割合は高く,平成12年度で55.2%となっています。特に近年,長引く不況や高齢化の進行などにより,受給者が急速に増加しており,平成2年度146億円であった生活保護費は,平成12年度には171億円増加し,2倍以上の317億円となっています。このように生活保護費の増加が,扶助費全体の増加の大きな要因となっています。
エ 国・県の補助制度等の見直しの影響
国は,平成元年度に国庫補助負担率の引き下げを恒久化し,児童保護措置費負担金をそれまでの10分の8から2分の1に,生活保護負担金を10分の8から4分の3にするなどの改定を行いました。こうした制度変更は,交付税の不交付団体であった川崎市にとっては,大きな負担増となりました。
また,最近改正された新たな医療保険制度により,本人負担の増加とともに,老人保健法に基づく老人医療の対象者年齢が70歳から75歳に引き上げられました。70歳から74歳までの高齢者に対する給付内容は,当面75歳以上の対象者と同様の内容となっていますが,67歳から69歳までの高齢者に対する医療費助成を単独事業費として実施している川崎市が,この制度をこのまま維持すると,今後相当程度の財政負担が生じる懸念があります。
グラフ2-1-2 扶助費の推移(普通会計)
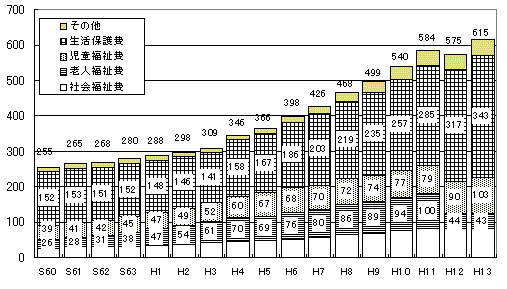
グラフ2-1-3 扶助費の推移(普通会計/補助単独事業別)
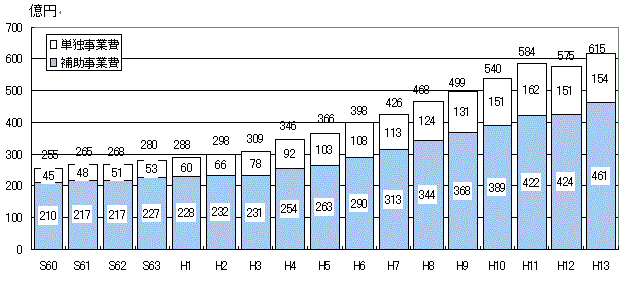
(3)投資的経費
ア 近年における大幅な事業費の増加と極端な落ち込み
財政硬直化の要因の一つとして,「ムダな公共事業」「過度な普通建設事業」がよく指摘されるところですが,川崎市の状況はさほど単純ではありません。
指定都市に移行した昭和47年度以降の決算総額(普通会計ベース)に占める投資的経費の割合の推移を見ますと,昭和47年度から平成6年度までは,他の指定都市に比べて特段低いものではありませんでした。むしろ,昭和50年代前半や昭和60年代当初,さらには平成3年度から平成6年度の間には,指定都市平均を上回っている年度も見られます。他都市と比較して投資的経費が大幅に落ち込んでくるのは,国の景気対策に連動した投資が一段落した平成7年度以降となっています。
ここで,単独事業費と補助事業費に分けて見てみますと,補助事業費については,指定都市移行後昭和54年度までの約8年間は,移行に伴う学校,廃棄物処理場,保育所等の整備を中心に,他都市に優るとも劣らない水準となっています。しかし,昭和55年度以降は,その比率は他都市平均を下回るようになり,この傾向は,現在に至るまで一貫して続いています。
一方,単独事業費の占める割合は,昭和58年度までは,他都市と同じかそれを下回る水準となっていました。しかし,昭和59年度から平成6年度までは一貫して他都市を上回って,投資的事業を推進してきたことが示されています。つまり,バブル経済期から崩壊後の平成6年度まで,他の指定都市と同等以上の割合で投資的事業を行ってきた川崎市は,平成7年度以降,事業費の圧縮を急激に余儀なくされているのです。
グラフ2-1-4 補助・単独別投資的経費(構成比)の推移―川崎市及び指定都市平均
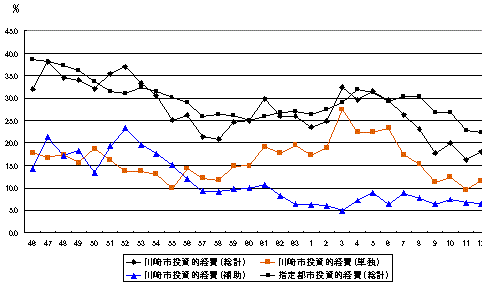
イ 土地取得をめぐる状況と課題
こうした投資的経費の状況と密接な関係にあるのが,土地の取得状況です。土地開発公社による土地取得の推移を見ますと,川崎市の土地取得は,先にみた投資的経費の急速な伸び(平成3年度)に4年程先行して,いわゆるバブル経済の絶頂期(昭和62年~平成2年)から急速に増加しています。
また,それまでは,取得金額と処分金額(市による買い戻し)がおおむね均衡していたのに対して,昭和62年度から平成6年度までの間は,平成3年度を例外として,毎年度,取得金額が処分(買い戻し)金額を大幅に上回り,その結果,土地開発公社の年度末土地保有残高は,昭和61年度の423億円から平成6 年度には,1,437億円と1,000億円以上も増加しています。
注目すべきは,バブル経済がすでに崩壊していた平成3年度以降も年間300億円以上の規模で土地取得が続けられ,他方,買い戻しは遅々として進まなかったことです。また,土地開発公社の土地取得は,その全額を金融機関からの借り入れによって行っているため,土地保有残高の増加は,そのまま借入金の増加となり,平成9年度にはその金額は,1,439億円にまで膨れあがっています。
平成12年度に「土地開発公社経営健全化計画」を策定し,供用済み用地を中心に買い戻しを集中的に行っているため,その額は次第に減少しつつありますが,逆に,投資的経費の財源の多くが買い戻し財源に充当され,他の事業財源を圧迫する事態となっています。
グラフ2-1-5 土地開発公社の取得・処分金額・残高
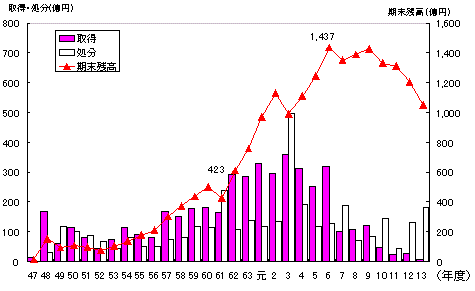
ウ 投資的経費と財源内訳の推移
昭和60年以降の投資的経費とその財源内訳の推移を見ると,平成4年度までは,投資的経費の半分程度を一般財源で賄っていることがわかります。ところが,平成5年度以降,その比率は極端に低下し,経費の4割弱しか一般財源で調達することができず,平成10年度及び12年度に至っては,事業費の3割にも一般財源が達せず,この傾向は現在もなお続いています。
一方,この間の市債発行額をみると,平成5年度の発行額は前年の435億円から55%増加して674億円となり,翌年の平成6年度も減税補てん債の発行もあって,867億円という多額の発行となっています。その後も毎年500億円から800億円程度の市債発行が続いており,平成5年度以降の投資的事業は,借金である市債の発行に頼りながら続けられてきたのです。
この結果,市債残高は急速に増加しており,平成14年度末には,集中的投資が始まる前の平成2年度(2,917億円)の2.7倍強の8,020億円となっています。このような市債残高の増加は,土地開発公社の借入残高や下水道事業会計の起債残高とも重なって,今後公債費として市財政の大きな圧迫要因となることが懸念されています。
グラフ2-1-6 投資的経費と財源内訳の推移
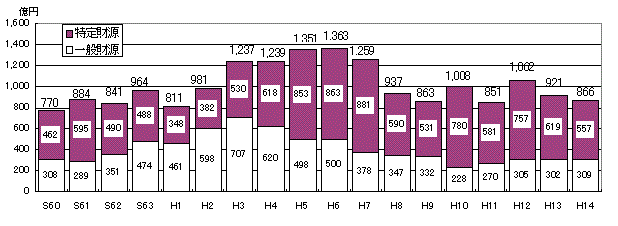
グラフ2-1-7 市債発行額、市債残高の推移
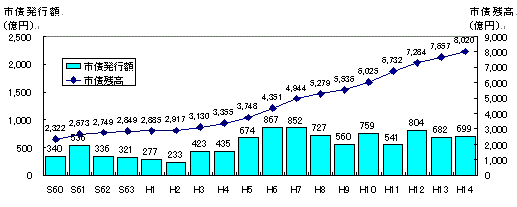
2 今後の財政見通しと従来対策の限界
以上,伸び悩む市税収入と硬直化の進む歳出構造に関して説明してきました。これを踏まえて,改めて今後の財政見通しを行い,これまでのペースの改革では,到底財政再建をなしえないことを明らかにします。
(1)今後の財政見通し
中期的な財政収支見通しを一定の条件のもとで試算してみます。歳入の根幹である市税収入は,平成15年度については固定資産の評価替え等を見込んだ積み上げ額とし,平成16年度以後は内閣府試算にならって1.5%の税収増を見込んでいます。現在の経済状況を想定しますと,これでも過大な税収見積もりとなる可能性もありますが,この市税増収見積もりを前提としても,歳出構造の硬直化の影響で,いままで以上に巨額な収支不足が生じる見込みとなりました。
すなわち,このままのペースで,これまでの財政運営を続けていけば,平成15年度から平成19年度までの今後5年間において,総額で約3,100億円,年平均で約600億円を超える収支不足が発生することが見込まれます。
なお,仮に,急速な経済回復などがあって市税収入が想定の1.5%を超えて大きく伸びたとしても,現在,地方交付税の交付団体となっている川崎市においては,地方交付税の減額が予想され,直ちに実質的な収支改善につながらないことに注意することが必要です。
中間財政収支見通し
| 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入合計 A | 5,273 | 5,376 | 5,504 | 5,953 | 6,175 | 6,118 |
| 市税 | 2,610 | 2,544 | 2,583 | 2,621 | 2,661 | 2,701 |
| 市債 | 699 | 863 | 876 | 1,309 | 1,449 | 1,378 |
| その他 | 1,964 | 1,969 | 2,045 | 2,023 | 2,065 | 2,039 |
| 歳出合計 B | 5,273 | 5,924 | 6,017 | 6,553 | 6,887 | 6,893 |
| 義務的経費 | 2,588 | 2,908 | 3,062 | 3,423 | 3,638 | 3,486 |
| 義務的経費(人件費) | 1,288 | 1,284 | 1,249 | 1,217 | 1,245 | 1,292 |
| 義務的経費(扶助費) | 682 | 747 | 796 | 851 | 909 | 969 |
| 義務的経費(公債費) | 618 | 877 | 1,017 | 1,355 | 1,484 | 1,225 |
| 投資的経費 | 866 | 1,014 | 869 | 867 | 868 | 869 |
| その他経費 | 1,819 | 2,002 | 2,086 | 2,263 | 2,381 | 2,538 |
| 収支不足額 C=A-B | 0 | △548 | △513 | △600 | △712 | △775 |
※平成14年度は当初予算
| 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入合計 A | 3,425 | 3,353 | 3,268 | 3,264 | 3,317 | 3,304 |
| 市税 | 2,610 | 2,544 | 2,583 | 2,621 | 2,661 | 2,701 |
| 市債 | 205 | 205 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| その他 | 610 | 604 | 649 | 607 | 620 | 566 |
| 歳出合計 B | 3,425 | 3,901 | 3,781 | 3,864 | 4,029 | 4,079 |
| 義務的経費 | 1,902 | 2,137 | 2,049 | 2,049 | 2,191 | 2,237 |
| 義務的経費(人件費) | 1,149 | 1,147 | 1,109 | 1,079 | 1,106 | 1,152 |
| 義務的経費(扶助費) | 294 | 315 | 334 | 356 | 377 | 398 |
| 義務的経費(公債費) | 459 | 675 | 606 | 614 | 708 | 687 |
| 投資的経費 | 309 | 367 | 368 | 367 | 368 | 369 |
| その他経費 | 1,214 | 1,397 | 1,364 | 1,448 | 1,470 | 1,473 |
| 収支不足額 C=A-B | 0 | △548 | △513 | △600 | △712 | △775 |
※平成14年度は当初予算
5カ年収支不足額合計 約3,100億円
主な前提条件
- 財政健全化債,土地売払収入などの財源対策は未計上
- 市税は,平成15年度の固定資産税評価替えの影響を勘案し,平成16年度以降は経済財政諮問会議「構造改革と経済財政の中期展望」による内閣府試算実質経済成長率1.5%増
- 人件費は,給与費では給与改定を見込まず,退職手当では退職予定者数を勘案
- 投資的経費は,原則として,平成14年度と同額計上(ただし西口文化ホール取得費は上乗せ計上)
- その他の経費の繰出金等は,特別会計・企業会計の収支見通しを勘案(高速鉄道を含む)
(2)収支不足への対応とその限界(財政再建団体への転落)
ア これまでの財源対策の実施
こうした収支不足に対し,仮にこれまでと同様の財源対策を講じたとしても,財政調整基金が底をつくことの影響や減債基金の積立繰延を実施しても市債償還の負担が翌年度から発生してしまうことなどから,収支不足を解消できない状況が見込まれます。
例えば,平成15年度では,これまでの歳入・歳出対策を行い,331億円の財源対策を実施しても,次の表のE欄にあるように217億円の収支不足となります。
| 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入対策 財政調整基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳入対策 土地売払収入 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 歳入対策 財政健全化債 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 歳出対策 国保繰出一部未計上 | △68 | △68 | △68 | △68 | △68 |
| 歳出対策 減債基金積立繰延 | △111 | △100 | △89 | △78 | △80 |
| 歳出対策 下水道会計繰出金抑制 | △55 | △55 | △55 | △55 | △55 |
| 繰延による後年度負担 | - | 28 | 68 | 103 | 88 |
| 合計D | 331 | 292 | 241 | 195 | 212 |
| 対策後の収支E=C+D | △217 | △221 | △359 | △517 | △563 |
イ さらに減債基金からの借入実施
さらに,この収支不足額を埋めるため,現在考えられる最後の手立てとしては減債基金からの借入(繰替運用)が想定されます。しかし,仮にこの手法を実施したとしても,平成15年度及び平成16年度は,次の表のG欄にありますように,収支不足は解消できますが,平成17年度には190億円の赤字が生じ,平成 18年度以降には,巨額の財政赤字が累積し(平成18年度で707億円,19年度では1,270億円),国の指導・監督下におかれる「財政再建団体」に転落する危険性があり,川崎市財政はまさに危機的な状況にあります。
| 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対策後の収支 E | △217 | △221 | △359 | △517 | △563 |
| 減債基金借入 F | 217 | 221 | 169 | - | - |
| 借入後の収支 G=E+F | 0 | 0 | △190 | △517 | △563 |
| 財政赤字(累計) | 0 | 0 | △190 | △707 | △ 1,270 |
| 減債基金借入可能額 | 607 |
ウ 財政再建団体への転落とその影響
赤字自治体の財政再建を図るため地方財政再建促進特別措置法(以下「再建法」という。)がありますが,この法律は昭和29年度の赤字団体の再建を目的に制定されたもので,現在ではこの法律を準用して再建を行うことになります(準用財政再建といいます)。
再建法に基づく財政再建は,自治体自らの申し出によってその手続きが始まるものですが,市町村にあっては,その赤字額が標準財政規模の20%を超えると(*注),再建法に基づいて財政再建を行わなければ,通常の地方債を発行できないこととされており,このため一般的には,自治体は再建の申し出をせざるを得ない仕組みとなっています。
再建団体は,「財政再建計画」を策定することになりますが,総務大臣の承認が必要とされておりますので,国の強力な指導・管理下のもとで,一定の行政水準を維持しながら,赤字額の計画的な解消を進めることになります。
当然のこととして,川崎市が独自に展開してきた単独事業や国のサービス水準を上回って提供してきた上乗せ事業は原則として見直しされることになりますし,同様に国の想定している負担水準を市の判断で軽減しているものも通常の負担に戻さざるを得ません。
このことは,川崎市の自主的・自立的な行財政運営に大きな支障を来すこととなり,市民生活に多大な影響を与えることが危惧されます。財政再建団体に転落することは,行政の無責任と言わざるをえません。
(*注):標準財政規模の推移
平成12年度 3,003億円(20%相当 601億円)
平成13年度 2,940億円(20%相当 588億円)
平成14年度 2,844億円(20%相当 569億円)
お問い合わせ先
川崎市総務企画局行政改革マネジメント推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3569
ファクス: 044-200-0622
メールアドレス: 17manage@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号9029

 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全