4-1-(2) ごみをつくらない社会の実現に向けた取組の推進
- 公開日:
- 更新日:
現状と課題
- 本市においてはこの10数年、市民1人1日あたりのごみ排出量が減少するなど、減量・リサイクルの取組は市民の間に一定程度浸透しているといえます。しかしながら、資源物を含めた総排出量は、1990年のごみ非常事態宣言時からほぼ横ばいに推移しているなど、依然として高い水準であり、また、資源集団回収や分別収集によるリサイクル量はここ数年伸び悩んでいます。
- このため、循環型社会の構築に向け、市民・事業者・行政の協働のもと、3R(リデュース(発生・排出抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用))の推進を基本とし、さらなる発生・排出抑制に取り組むとともに、従来からの資源集団回収、分別収集の拡充など、より一層のリサイクルを推進することが必要です。
- こうしたことから、廃棄物対策については、従来の適正処理を中心とした取組から、ごみ減量やリサイクルの拡充など、環境への配慮に重点を置いた取組が求められています。
- 持続可能な社会の実現に向けて、拡大生産者責任の考え方のもと、生産者には製造した製品が廃棄物となった場合にも、その後の再使用・再生利用・処分が容易に行えるなど十分な環境配慮を行うことが求められています。
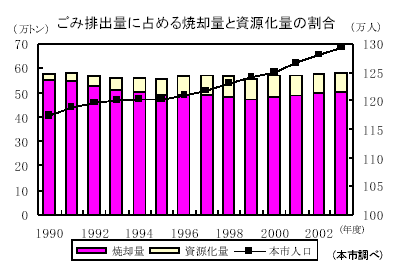
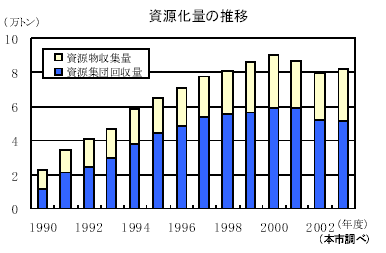
施策課題
現状と課題を踏まえ、以下の施策課題に取り組みます。
(1)市民・事業者の排出抑制とリサイクル活動の支援
- 資源集団回収や生ごみコンポストの利用促進など、リサイクルに向けた市民の自主的な取組を支援するとともに、環境学習や市民間交流、実践活動の場の提供などの支援を通じ、ごみ減量に対する意識啓発を推進します。
- 家庭系ごみの約4割を占める生ごみを減らすために、モデル事業などを踏まえて本市に適した減量化・リサイクルの中長期計画として「かわさき生ごみリサイクルプラン」の策定に取り組みます。
- 本市の実施する分別収集に加え、スーパーマーケットなどの店舗が自ら販売したもののうち、リサイクル可能なものを店頭回収する取組を事業者との協働により推進します。
- 事業活動に伴い発生する産業廃棄物及び一般廃棄物の発生・排出抑制とリサイクルの促進に向けた指導を実施します。
- ごみ減量に向けたさまざまな取組を推進することにより、今後10年間で市民1人が1日あたりに出すごみを180グラム減量することをめざします。
具体的な事業と事業目標
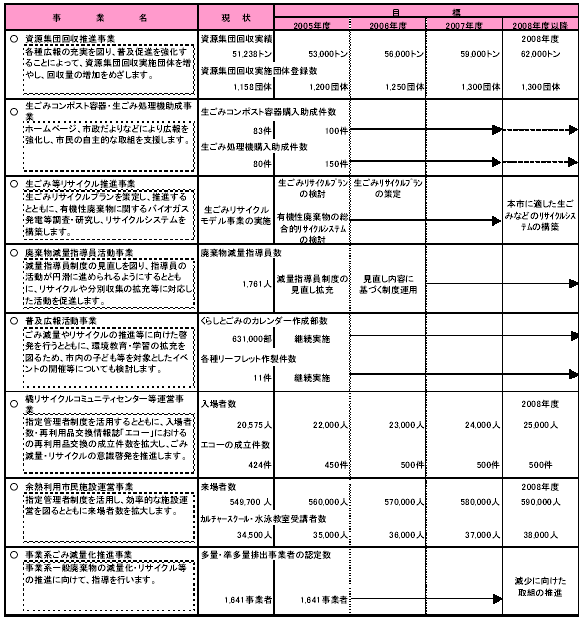
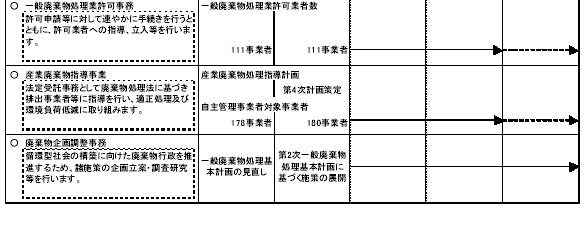
(2)資源物の分別収集の推進
- 従来の空き缶・空きびん・ペットボトルなどの分別収集に加え、2006年度からミックスペーパーの分別収集のモデル実施を進めます。
- 今後10年間には、ミックスペーパーの分別収集を全市展開するとともに、容器包装リサイクル法に基づくその他プラスチック製容器包装の分別収集や生ごみの資源化などに取り組みます。
- これらの取組を推進することにより、今後10年間をめどに市全体の1年間の資源化量を20万トン(資源化率35%)に拡大します。
- 分別収集の拡充には、経費の増加が伴うため、資源物の日など現行の資源物収集体制の検証を行い、効率的かつ効果的な分別収集体制の構築に取り組みます。
具体的な事業と事業目標
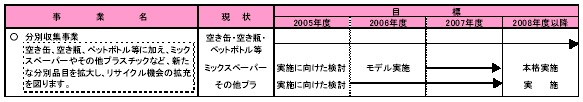
(3)資源物の適正処理
- 資源の有効利用の観点から、分別収集した資源物については、資源化処理施設において選別等を行い、容器包装リサイクル法によるルートや民間ルートを活用しリサイクルを推進します。
- その他プラスチック製容器包装の分別収集の実施に向けて、効率的な収集運搬のための資源物ストックヤード(一時保管場所)と中間処理施設の整備に向けた検討を行います。
具体的な事業と事業目標
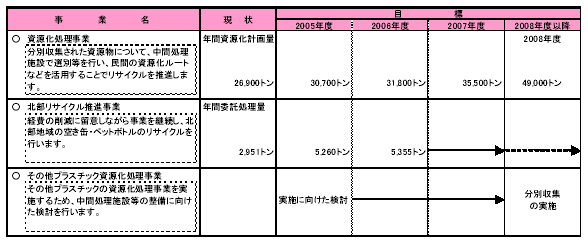
(4)公共工事におけるリサイクルの推進
- 循環型社会の構築に向け、循環型社会形成推進基本法や建設リサイクル法等に基づき、工事過程における建設副産物の発生・排出抑制に努めるとともに、やむを得ず出た建設副産物については再使用及び再資源化(再生利用及び熱回収)を推進するなど、民間事業者に率先して環境配慮の取組を進めます。
- 建設副産物の再資源化については、建設汚泥や建設発生木材などリサイクル率が低い品目もあるため、リサイクル率の向上に向けて国・県と共に調査研究を進めます。
- 公共工事に伴う建設発生土については、できる限り発生場所での再使用を図るとともに、現場外へ搬出する場合は、浮島2期埋立処分場に埋め立てるほか、他自治体との連携により地方港湾の埋立用材として活用を図ります。
- 上下水道の工事においては、埋戻しが必要となることから、資源の有効活用の観点から発生土を土質改良し、埋戻材として利用を図ります。
具体的な事業と事業目標
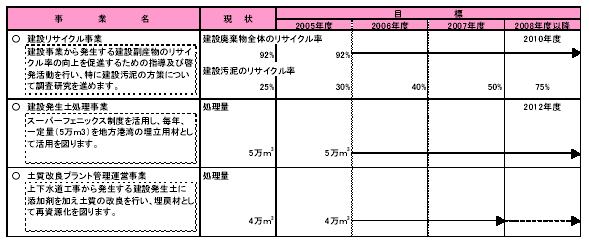
(5)経済活動におけるリサイクルの推進
- 循環型社会の構築に向け整備が進む各種リサイクル関連法令に基づき、事業者に対して適切な手続を行うほか、法の趣旨が徹底されるよう指導や普及啓発を行います。
- 家電リサイクル法の対象品目(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン等)については、小売店による引取りが事実上困難なケースもあるため、本市独自の家電リサイクル協定店制度により、事業者との協働のもと家電リサイクルを推進します。
- 事業者が実施する工事について、建設リサイクル法に基づく届出に対する審査業務・現場調査を実施し、本市が実施する工事と同様に建設副産物の再使用・再資源化を促進します。
具体的な事業と事業目標
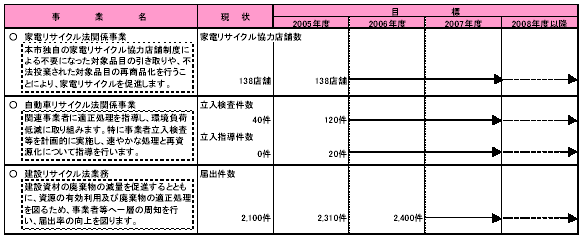
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部企画調整課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2550
ファクス: 044-200-0401
メールアドレス: 17kityo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号34416

 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全