2.1 子どもの権利と権利条例
- 公開日:
- 更新日:
2-1-(1)権利条例の認知度
「川崎市子どもの権利条例」について知っていますか。」という質問に対し、
- 子どもにおける認知度は全体で45.2%、小学生年代は高く56.6%だが、中学生年代(43.5%)、高校生年代(31.6%)と認知度が低下する。
- おとなの認知度は全体で31.0%となり、子どもよりも低い。子どもがいるおとなは49.3%と比較的高くなるが、いないおとなは20.1%と特に低い値を示す。
子どもの有無による関心の差異が、条例の認知度を大きく左右している。
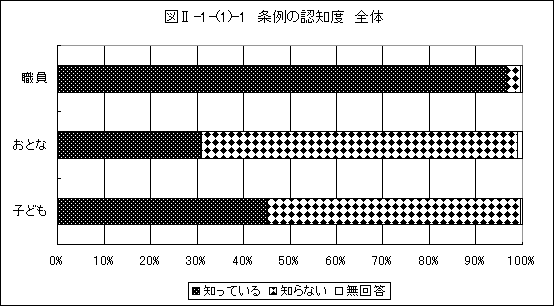
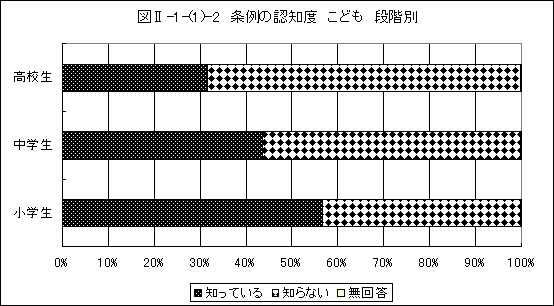
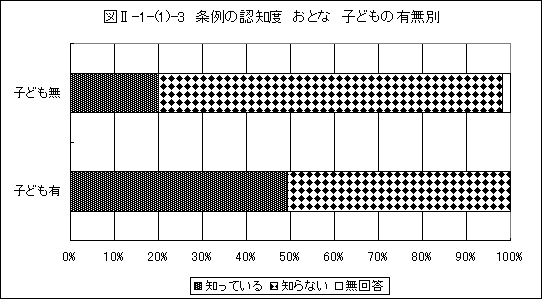
2-1-(2)権利条例を知った場所
前の質問で「知っている」と答えた者に「どこで知ったか」と尋ねた。
- 条例を知った手段としては、子どもは授業・先生の話が特に高く(70.8%)、特に小学生年代は80.5%ときわめて高い数値を示している。子どもの場合、それ以外ではパンフレット・ポスターなどで認識した率が45.1%を示すが、それ以外の方法ではいずれも6%未満でしかない。このことは、学校における条例に関する学習が一定の成果を示していることを示唆している。
- おとなが条例を知った手段は、パンフレット・ポスターなどが最も高い(65.7%)。次に新聞(28.9%)が続き、それ以外の手段は20%を割っている。これは、一般市民に対するパンフレット・ポスターという宣伝手段の有効性を示唆している。
- 職員が条例を知った手段は、おとなと同様、パンフレット・ポスターなどが最も高く(71.1%)、「授業・先生の話」(52.3)、「研修・講演会」(43.0%)、新聞(24.6%)と続く。
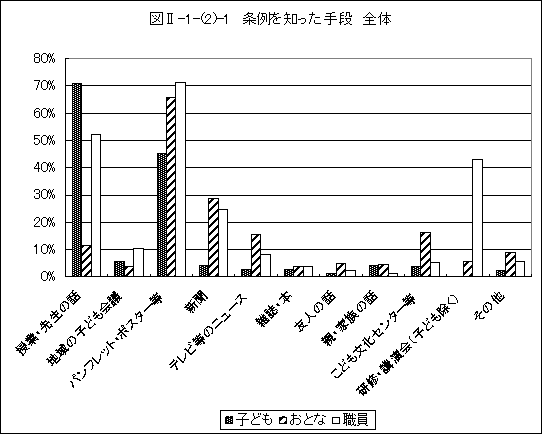
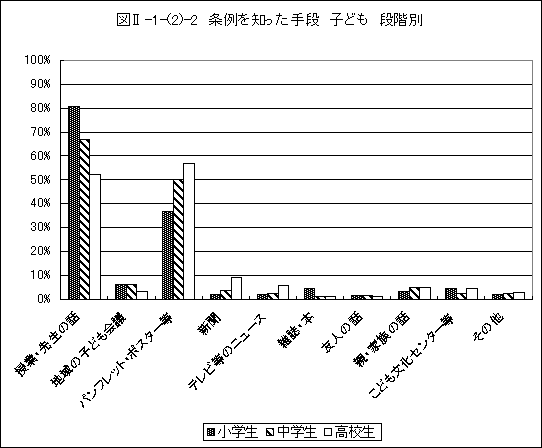
2-1-(3)権利条例に基づいた各制度の認知度
権利条例をもとにしてつくられた仕組みで、きいたことのあるものについて尋ねた。
- 子どもの各制度に関する認知度を見ると、全体では「川崎市子ども会議」の認知度のみが高く(43.9%)、それ以外の制度はいずれも16%を下回っている。
- おとなの認知度を見ると、子ども以上に各制度の認知度が低く、最も高い「川崎市子ども会議」でも22.4%しかない。ただし、子どものあるおとなは「川崎市子ども会議」の認知度のみ41.3%と高くなっている。
- 子どもの場合もおとなの場合も、条例の認知度と各制度の認知度が強く関係している。子どもの場合、条例を知っている子どもは63.8%が「川崎市子ども会議」を認知している。おとなの場合、条例を知っている場合にはいずれの制度も20%以上の認知度を示し、条例を知らない場合にはいずれの制度も8%以下の認知度となる。
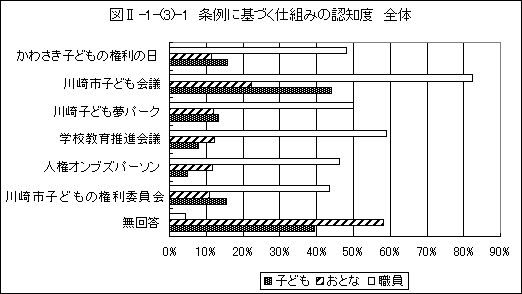
2-1-(4)権利条例に記載されている権利に対する認識
- 子ども、おとな、職員いずれも、条例に記載されている各種の権利について大切だと思うものを2つ選んでもらったところ、「安心して生きる権利」のみが過半数の回答を得た(子ども60.0%、おとな74.1%、職員73.4%)。その他の権利はいずれも40%未満の回答しか得られず、特に「参加する権利」は子ども、おとな、職員いずれも最も低い数値を示した(子ども10.6%、おとな11.0%、職員8.5%)。多くの市民にとって「安心して生きる権利」は共通して重視すべき権利と認識されているが、逆に「参加する権利」については、優先順位が低く受けとめられていることを示す。
| 大切だと思う権利 | % |
|---|---|
| 安心して生きる権利 | 60.0% |
| ありのままの自分でいる権利 | 34.3% |
| 自分を豊かにし力づけられる権利 | 23.0% |
| 自分で決める権利 | 19.0% |
| 必要に応じて支援を受ける権利 | 19.0% |
| 自分を守り・守られる権利 | 16.3% |
| 参加する権利 | 10.6% |
| 大切だと思う権利 | % |
|---|---|
| 安心して生きる権利 | 74.1% |
| 自分を豊かにし力づけられる権利 | 30.1% |
| 自分を守り・守られる権利 | 25.2% |
| ありのままの自分でいる権利 | 18.4% |
| 必要に応じて支援を受ける権利 | 14.4% |
| 自分で決める権利 | 11.9% |
| 参加する権利 | 11.0% |
| 大切だと思う権利 | % |
|---|---|
| 安心して生きる権利 | 73.4% |
| ありのままの自分でいる権利 | 29.8% |
| 自分を守り・守られる権利 | 29.8% |
| 自分を豊かにし力づけられる権利 | 22.1% |
| 必要に応じて支援を受ける権利 | 21.6% |
| 自分で決める権利 | 12.6% |
| 参加する権利 | 8.5% |
2-1-(5)自己決定したい項目
- 子どもが自分で決めていいことについて、おとなと職員はほぼ同様の回答傾向を示し、5割以上が「可能」と回答する項目と3割以下の人しか「可能」と回答しない項目とに大きく二分される。これに対して、子どもの中では5割を超えた項目は三つ(つき合う友達65.2%、クラブ活動・部活動59.0%、服・ファッション57.5%)に留まる一方で、それ以外のほとんどの項目は2割から5割の間の回答に集中している。おとなと職員との回答傾向と子どもの回答傾向で大きく異なる項目は子どもの回答が高くなっている項目として「テレビやゲーム」、「学校での髪型」、「家に帰る時間」、「アルバイト」、「学校に持っていっていい物」が、逆に子どもの回答が低くなっている項目として「習いごと」、「趣味活動」、「進学したい学校」、「塾」が上げられる。
- 子どもの回答の中でも小学生年代は比較的自己決定したいと考える回答が少なくなっているのに対して、中学生・高校生年代へとあがるにつれて、自己決定したいという回答が増加する〔表2-1-(5)-2参照〕
| % | 子ども | おとな | 職員 |
|---|---|---|---|
| 80.0-84.9 | 部活・クラブ活動80.4 | ||
| 75.0-79.9 | |||
| 70.0-74.9 | 部活・クラブ活動71.6 | 進学したい学校71.2 | |
| 65.0-69.9 | つきあう友達65.2 | 進学したい学校65.3 | 習いごと66.1 つきあう友達65.2 |
| 60.0-64.9 | 習いごと60.8 | ||
| 55.0-59.9 | 部活・クラブ活動59.0 服・ファッション57.5 | つきあう友達56.2 | 趣味活動58.1 服・ファッション56.9 |
| 50.0-54.9 | 服・ファッション54.5 趣味活動54.0 就職53.5 | 就職53.2 | |
| 45.0-49.9 | 進学したい学校49.7 | ||
| 40.0-44.9 | 就職43.1 テレビやゲーム42.6 | 塾43.4 | |
| 35.0-39.9 | 習いごと38.8 学校での髪型38.7 趣味活動38.6 家に帰る時間37.3 アルバイト36.1 | 塾36.3 | |
| 30.0-34.9 | 学校に持っていっていい物34.9 | ||
| 25.0-29.9 | 学校に着ていく服25.5 | 学校に着ていく服27.0 | 学校に着ていく服28.0 |
| 20.0-24.9 | 塾23.7 | アルバイト22.4 | 学校での髪型21.5 |
| 15.0-19.9 | テレビやゲーム19.6 学校での髪型17.9 学校に持っていっていい物15.4 | テレビやゲーム19.6 アルバイト15.8 | |
| 10.0-14.9 | 家の食事のメニュー12.3 | 家の食事のメニュー11.3 学校に持っていっていい物10.1 | |
| 5.0- 9.9 | 家の食事のメニュー7.0 | ||
| 0.0- 4.9 | とくにない4.9 | 家に帰る時間4.9 とくにない2.0 | 家に帰る時間1.8 とくにない1.5 |
| % | 小学生年代 | 中学生年代 | 高校生年代 |
|---|---|---|---|
| 80.0-84.9 | つき合う友達80.4 | ||
| 75.0-79.9 | |||
| 70.0-74.9 | 服・ファッション74.1 | ||
| 65.0-69.9 | つき合う友達67.7 | 進学したい学校65.4 | |
| 60.0-64.9 | 部活・クラブ活動61.3 服・ファッション60.6 | 就職61.6 | |
| 55.0-59.9 | 部活・クラブ活動56.8 | 部活・クラブ活動59.4 アルバイト56.9 | |
| 50.0-54.9 | つき合う友達51.7 | 進学したい学校53.3 | 趣味活動54.2 |
| 45.0-49.9 | 就職45.9 | 家に帰る時間48.7 学校での髪型47.2 | |
| 40.0-44.9 | テレビやゲーム43.5 服・ファッション42.9 習いごと42.2 | テレビやゲーム44.2 趣味活動40.5 | |
| 35.0-39.9 | 学校での髪型39.8 アルバイト39.1 家に帰る時間38.4 学校に持っていっていい物36.7 習いごと35.1 | テレビやゲーム39.1 習いごと39.1 学校に持っていっていいもの38.2 | |
| 30.0-34.9 | 進学したい学校34.9 学校に着ていく服32.2 学校での髪型31.3 学校に持っていっていいもの30.9 | ||
| 25.0-29.9 | 家に帰る時間27.9 就職 27.3 趣味活動25.3 | 塾29.4 | |
| 20.0-24.9 | 塾24.1 学校に着ていく服22.7 | ||
| 15.0-19.9 | 塾19.2 アルバイト18.3 | 学校に着ていく服19.7 | |
| 10.0-14.9 | |||
| 5.0- 9.9 | 家の食事のメニュー9.4 とくにない8.1 | 家の食事のメニュー6.2 | |
| 0.0- 4.9 | とくにない3.5 | 家の食事のメニュー4.8 とくにない2.3 |
2-1-(6)権利と責任との関係
- いずれのグループも、「権利も責任も両方同じように大切」と回答する割合が最も高くなっており、特に職員・おとなの回答では6割を超えている。一方で、「権利優先(権利が認められてはじめて責任がはたせる)」「責任重視(今の子どもはわがままだから、そう言われてもしかたがない)」という回答もいずれの集団でも1割前後存在している。
- 年代別に子どもの回答をみてみると、「決めつけないでほしい」という回答は小学生年代で特に高くなっている(29.7%)のに対して、高校生年代では18.3%に留まっている。「責任重視」という回答は小学生年代で低く(8.2%)、中学生年代(13.7%)、高校生年代(19.0%)と増加している。
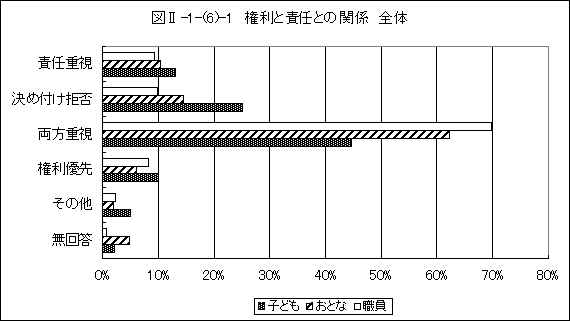
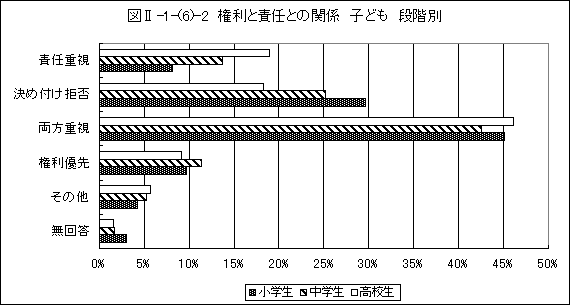
2-1-(7)自分がされていやなことを他人にすること
「いじめなど、自分がされていやなことを他の人にすることをどう思うか」という質問に対して、
- 「すべきではない」と回答した子どもが52.5%、「しないほうがいい」が40.0%で、9割以上が否定的見解を回答しており、「されたのだから、してもかまわない」(2.1%)、「自分がやりたいことなら、してもいい」(1.0%)といった回答は少数に留まる。なお、条例の認知度との有意な相関はみられない。
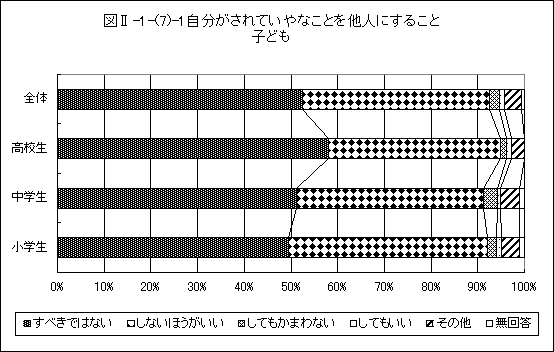
2-1-(8)子どもを支える活動に関する川崎市の支援
- 子どもを支える市民活動やNPO・NGO活動に対する川崎市の支援については、おとな全体の回答でも職員の回答でも、「もっと活動しやすくなる情報を提供すべき」という声が最も高く(43.7%、39.9%)、次に「わからない」(32.1%、21.1%)「もっと財政的支援をすべき」(8.0%、20.6%)の順となっている。また権利条例を知っているおとなの回答では特に「もっと活動しやすくなる情報を提供すべき」との意見が多い(54.2%)。
- 市が充実させるべき子育て支援は、いずれの項目も満遍なく2割から4割の回答が集まっている。
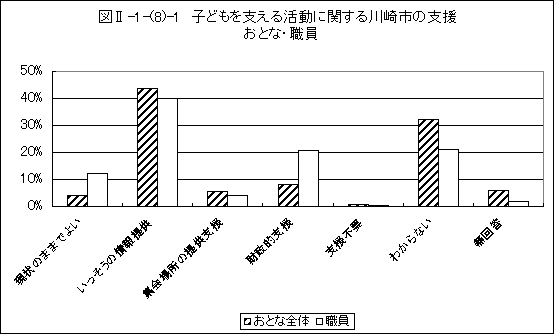
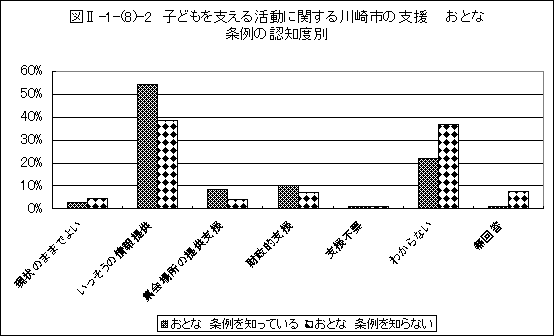
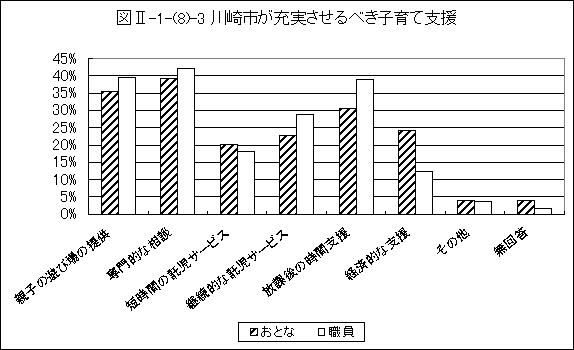
2-1-(9)子どもが自分の権利を学ぶ機会と方法(職員のみ)
- 職員の中では、子どもが自分の権利を学ぶ機会があると「思う」(18.8%)、「やや思う」(42.3%)をあわせると6割以上が権利学習の機会が存在すると認識していることが読み取れる。
- 学習する機会があると「あまり思わない」「思わない」と回答した職員にその理由を尋ねたところ、最も多くなったのが「教え方が分からない」(39.4%)、「よい教材がない」(26.9%)の順となっており、他の項目も回答が広く分散している。
- 権利に関するパンフレットの活用方法として、「配布だけしている」職員は33.6%、「説明して配布している」職員は37.9%となっており、「権利学習に活用している」職員は18.5%に留まっている。
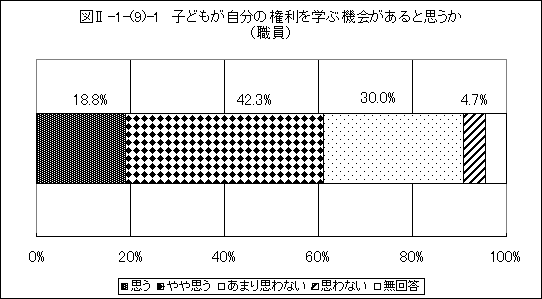
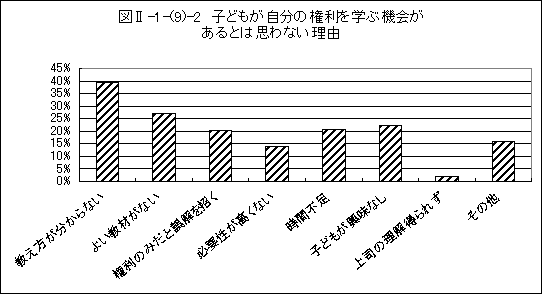
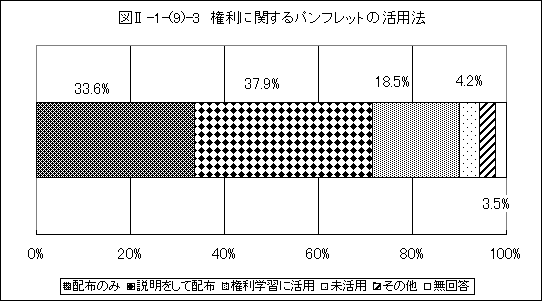
お問い合わせ先
川崎市こども未来局青少年支援室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2688
ファクス: 044-200-3931
メールアドレス: 45sien@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号3298

 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全