子どもと学校
- 公開日:
- 更新日:
2-2-(1)学校で学びたいことを学んでいるか
- 子ども全体では学校で学びたいことを学んだと感じている割合は17.7%、やや感じている割合が38.4%となっており、過半数が学びたいことを学んだと回答している。ただし、小学生年代は二つの数字とも高く(24.7%、44.5%)、学校年代が上昇するにつれ割合が低下しており(高校生年代11.7%、31.6%)、高校生年代は過半数が「感じていない」(14.2%)、「あまり感じていない」(36.1%)と回答している。なお、条例の認知度による有意な差はみられない。
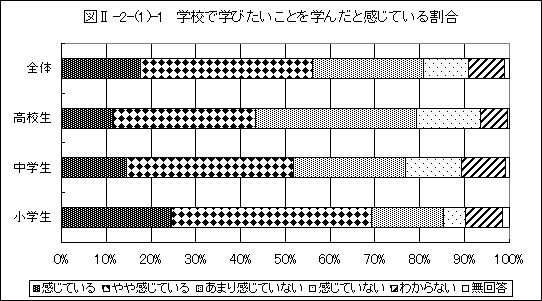
2-2-(2)教師による児童・生徒に関する情報の開示
- 子どもが、教師が書いた自分の情報について知ることができるか否かについては、「できる」という回答は小学生年代から高校生年代まで大きな変化はなく全体で21.2%となっているが、「できない」という回答は小学生年代で14.4%なのに対し、中学生年代で29.7%、高校生年代で40.6%に達している。これは「分からない」という回答が小学生年代で64.2%に達しているためであると思われる(中学生年代44.5%、高校生年代37.9%)。条例の認知度による有意な差はみられない。
- 子どもに関する情報の保護者に対する開示が十分であるかについては、おとなでも31.3%が「わからない」と回答しており、十分だと「思う」(1.7%)は、「やや思う」(6.8%)と足しても1割に達しない。この数値は子どもの有無とは無関係である。これに対して職員は「思う」(15.8%)、「やや思う」(28.0%)と合計で4割を超えており、おとなと職員の意識の差が見られる。
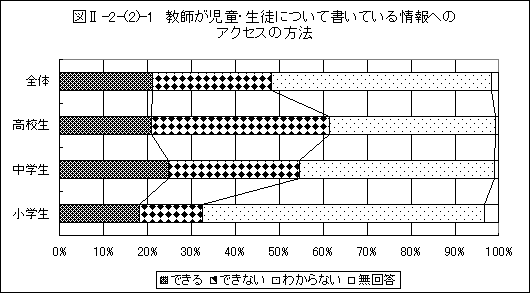
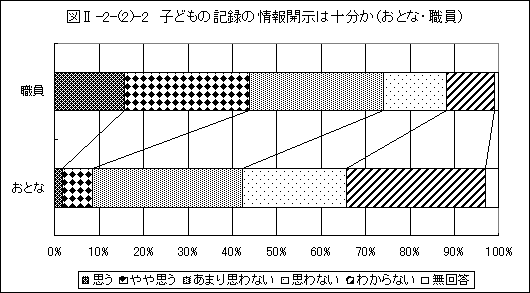
2-2-(3)学校・施設内での体罰
- 学校や施設内での体罰(先生からたたかれること)について子どもは「よくある」(1.5%)、「ときどきある」(7.2%)と回答しており、1割近くが体罰を体験していることが示された。
- 学校や施設内での体罰に対する評価について、体罰否定(体罰はあってはならない)は子ども48.1%、おとな41.5%に対して、体罰肯定(子どもが悪い場合は体罰できたえるべき)は子ども5.5%、おとな3.5%となっている。また少しの体罰を容認する(子どもが悪いのだから体罰を受けてもしかたがない)回答については子ども23.4%、おとな37.7%となっており、子どもの3割、おとなの4割は程度はともかく体罰そのものを否定はしないことが示されている。
- それに対して職員は体罰否定が73.5%に達し、体罰肯定は0.5%に過ぎない。
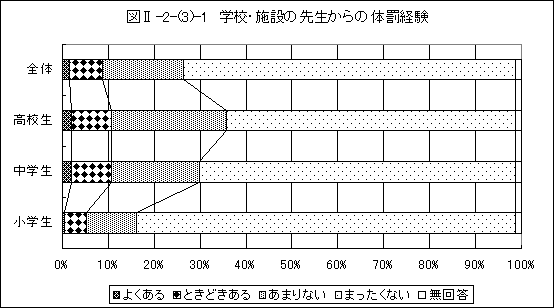
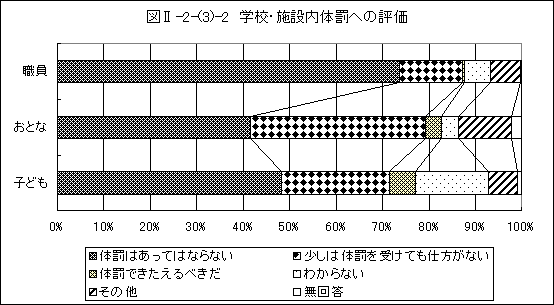
2-2-(4)学校忌避の感情と理由
- 子どもの中で「学校に行きたくないと思ったことがある」のは67.1%となっており、特に高校生年代では83.1%となっている。
- 「行きたくない」と思った理由としては、子どもが「疲れていた」(61.5%)、「学校がつまらない」(33.4%)、「なんとなく」(32.5%)、「友達がいやなことを言ったり、したりする」(20.0%)といった順で理由をあげているのに対して、おとなは「友達がいやなことを言ったり、したりする」(50.6%)、「疲れていた」(33.8%)、「学校がつまらない」(29.4%)、「先生がいやなことを言ったり、したりする」(22.1%)といった順になっており、職員も「友達がいやなことを言ったり、したりする」(60.3%)、「疲れていた」(51.8%)、「学校がつまらない」(41.1%)、「なんとなく」(28.6%)といった順になっている。なお、子どもの無いおとなで「疲れていた」を理由にあげたのは24.2%であるのに対し、子どものあるおとなでは47.4%に達している。このことは、子どもたちが疲労していることを職員はかなり把握しているが、一般のおとなは理解していないことを示唆する。
- 年代別でみると、「疲れていた」と「学校がつまらない」を理由に挙げている割合は小学生年代から高校生年代にかけて増加している(疲れていた:53.9%⇒68.0%、学校がつまらない:21.4%⇒42.0%)一方、「友達がいやなことを言ったり、したりする」という回答は27.1%から15.6%へと減少を示している。
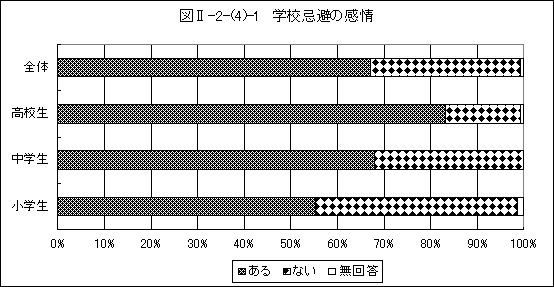
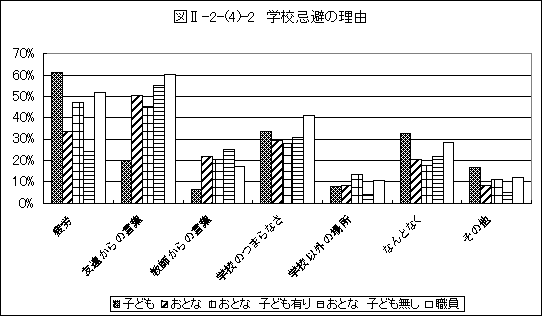
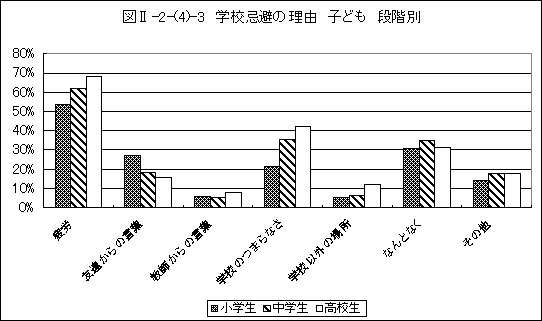
2-2-(5)学校生活の楽しさ
- 学校生活が楽しいと「感じている」のは50.2%、「やや感じている」(35.7%)とあわせると8割以上の子どもは学校生活を楽しんでいる一方、「あまり感じていない」(9.8%)と「感じていない」(3.9%)を合計すると1割以上の子どもが学校生活を楽しんでいないことが示されている。また年齢が上昇するにつれて、楽しいと感じる割合は低下する傾向にある。
(「発表会・文化祭」と「友達との交流」は年代が上がるにつれて上昇する。) - 楽しいと感じている場としては、「友達との交流」(87.0%)、「休み時間」(73.9%)、「遠足・修学旅行」(62.2%)、「クラブ活動・部活動」(59.7%)が高い数値を示している。
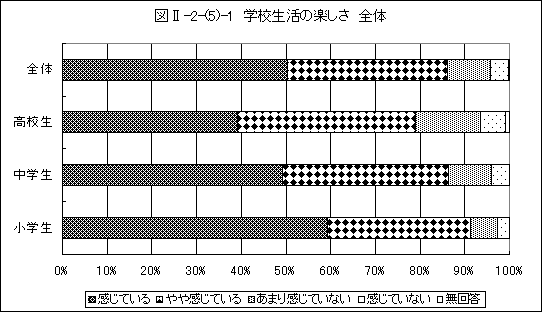
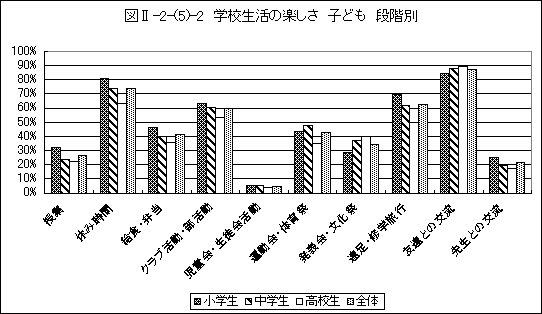
2-2-(6)出席停止・停学手続きの適切性
- 出席停止・停学・退学・退所などの手続きの適切性について、おとなは「わからない」と回答したのが59.0%に達しており、特に子どものあるおとなは69.5%が「わからない」と回答している。適切だと「思う」(3.5%)、「やや思う」(10.2%)を合計してようやく1割を超えた程度である。一方職員は7割近くが適切だと「思う」(41.3%)、「やや思う」(13.5%)と回答している。
- 手続きの不適切さを指摘する意見では、おとなは「子どもからの意見聴取が十分に保障されていない」(60.3%)を指摘する声が大きいのに対して、職員側は「保護者」(63.2%)、「子ども自身」(60.5%)への説明不足を回答している。
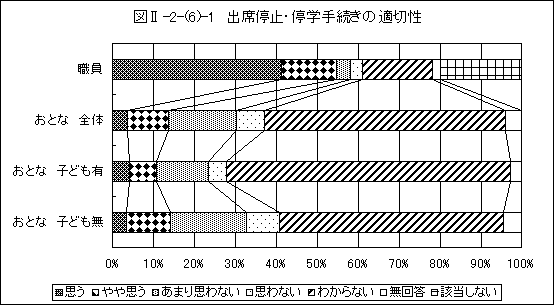
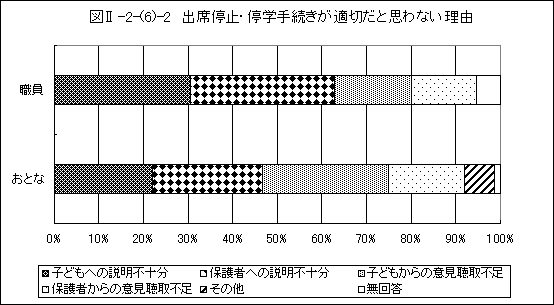
お問い合わせ先
川崎市こども未来局青少年支援室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2344
ファクス: 044-200-3931
メールアドレス: 45sien@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号3346

 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全