建築協定制度について
- 公開日:
- 更新日:
【重要なお知らせ】新たな窓口対応について
令和4年2月からの景観・地区まちづくり支援担当の窓口応接時間帯についてお知らせいたします。詳しくはこちらのページをご覧ください。
建築協定制度について
私たちが、建築物を建てる場合、建築計画の基本となるいろいろな基準を定めた「建築基準法」を守らなければなりません。建築基準法は、全国的に守られるべき必要最低限の基準を定めています。地区の持っている特色を活かしたきめ細やかな規制を行う場合には、建築協定制度を活用することができます。
例えば、住宅地としての良好な環境を守るために、他の用途を規制したり、商店街としての利便をより高度に維持、増進することを目的に、店舗を建てやすくするなど、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を、地域住民の合意により定めることができます。これが建築協定制度です。
建築協定の法的な性質
建築協定の法的性質は、当事者全員の合意によってのみ締結・変更が行えること、協定違反があった場合の措置はあらかじめ協定の内容として定めておかなければならないこと等から一種の契約による自主的規制であるといえます。したがって、協定に定める建築物に関する基準は、建築主事による確認の対象となる「建築物に関する法令等の規定」には該当せず、建築協定について違反があっても特定行政庁による違反の是正措置は行われません。
建築協定の内容
協定区域を決めます
まとまった単位から区域を考えます。
決め方としては、地形的条件では、道路・公園等の都市施設での境界などが望ましく、地理的条件では、町会、自治会等の境界が望ましいでしょう。
建築物の基準を考えます
協定の区域において、「建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備」に関する基準を定めることによりその区域内の良好な環境を法律的立場から保護するのが目的です。
たとえば、次のようなことが定められます。
1.低層の1戸建住宅中心の環境を守りたい。
3階以上の高さの住宅を規制する。
軒高が7メートルを越える高さの住宅を規制する。
共同住宅を規制する。
2.整然とした街並みを保全したい。
道路からの外壁後退距離を定める。
道路沿いの柵は生け垣又はフェンスとする。
3.ゆったりとした住宅地にしたい。
敷地面積の最低限度を定める。
敷地に対する建築物の面積を規制する。
有効期間について
期間の長さに定めはありませんが、10年に1度程度、定めた基準が現況に即しているかを確認することが望ましいです。
※建築基準法との関係について
建築基準法で定めた基準を緩和するような内容の協定は、たとえ住民全員の合意があっても、定めることができません。
建築協定の手続き
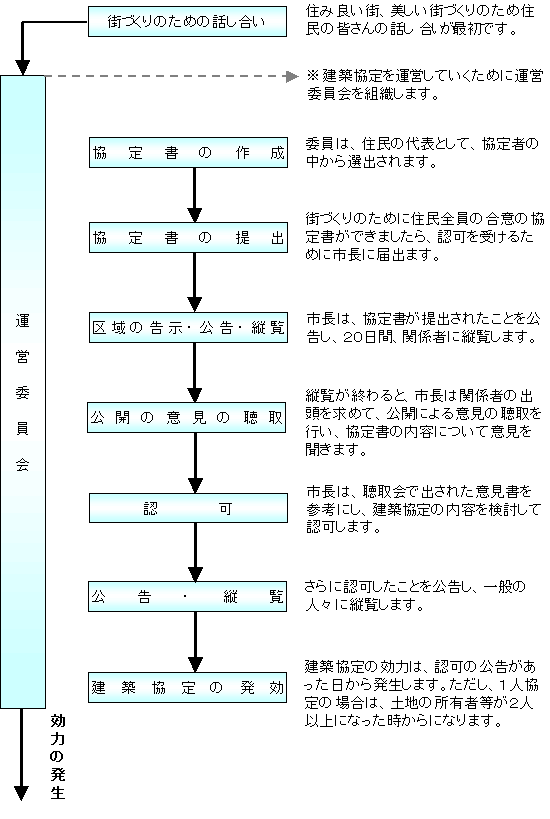
建築協定 Q&A
Q1 建築協定区域は、どのくらいの広さがあればよいですか?
A
建築協定区域については、建築基準法上「いくら以上の面積にしなければならない」という規定はなく、「土地について一定の区域を定め」とあるだけですので、建築協定の趣旨に合うように、良好な居住環境を維持促進し、将来にわたり良好な地域環境を確保することができるような区域であれば結構です。
Q2 建築協定には、誰でも参加できるのですか?
A
建築協定に参加できるのは、協定区域内の土地の所有者及び借地権者(法律では「土地の所有者等」と総称しています。)です。
Q3 建築協定に後から加入しようとする場合、どのような手続きが必要ですか?
A
建築協定区域外の土地の所有者又は借地権者が新たに参加を希望するときは、建築協定の締結の場合と全く同様の手続きにより、特定行政庁(川崎市)の認可を受けることとなります。ただし、協定区域内に隣接した土地であって、協定隣接区域と定めている場合の土地の所有者又は建築協定区域内の借地権の目的となっている土地の所有者が、後から加入しようとする場合には、特定行政庁(川崎市)に対し、書面で意思表示をすれば参加することができます。
建築協定内の土地を後から購入したり、借地したりする人は自動的に協定の効力が及びますが、念のために運営委員会などに連絡しておくことがよいでしょう。
Q4 建築協定が、認可されないのはどのような場合ですか?
A1 形式的・手続き的な理由により、認可できない場合。
- 建築協定区域内の土地の所有者及び借地権者の合意によって、作成されたものではない場合。
- 建築協定区域内、建築物に関する基準、協定の有効期間又は協定違反があった場合の措置を定めていない場合。
A2 実質的理由により認可できない場合。
- 建築協定がその目的となっている土地又は建築物の利用を不当に制限するものである場合。
- 建築協定が、建築物の利用を促進し、かつ、土地の環境を改善するために必要なものであるとはいえない場合。
Q5 建築協定で、建築基準法が定めている基準を緩和することができますか?
A
法に定める基準は公法上の最低の基準であり誰もが守らなければならないものですから、例えお互いに合意の上であっても、協定で法が定めている基準を緩和することはできません。
Q6 建築協定で、青空駐車の禁止や、空地管理などについて規制することはできますか?
A
建築協定は、建築物に関する基準について定めることとなっておりますので、建築物が存在しない空地の利用方法や管理について規制することはできません。
Q7 敷地分割を禁止した場合、相続などをするための分筆はできますか?
A
相続などによる所有権移転のための分筆は可能ですが、分筆し所有権移転したそれぞれの土地に建物を建てることはできません。
したがって、分筆前の土地を一つの敷地として建物を立てることとなります。
Q8 建築協定に違反した場合には、どのように取り扱いますか?
A
建築協定は、私人が自主的に規制を行うことを目的として締結するものですから、建築協定の違反行為があった場合の措置について、建築協定書に定めておかなければなりません。
一般的に、建築協定書に委員長が運営委員会の決定に基づいて、違反者に対して違反にかかる工事の施工停止又は是正のための措置をとることを求め、それに応じない場合は、裁判所へ提訴することができることなどを定めている例が多いです。
川崎市内の建築協定区域
※建築協定区域内で建築計画等がある場合には、各地区の運営委員会に御連絡いただきますようお願いいたします。
運営委員会の連絡先は、計画部景観・地区まちづくり支援担当(電話:044-200-3025)までお問い合わせください。
- 上布田地区の詳細については、計画部景観・地区まちづくり支援担当まで御連絡ください。
位置図
 久保台地区(PDF形式, 588.71KB)別ウィンドウで開く
久保台地区(PDF形式, 588.71KB)別ウィンドウで開く 有馬五丁目地区(PDF形式, 2.75MB)別ウィンドウで開く
有馬五丁目地区(PDF形式, 2.75MB)別ウィンドウで開く グランフォーラム宮崎台桜の邱地区(PDF形式, 1.99MB)別ウィンドウで開く
グランフォーラム宮崎台桜の邱地区(PDF形式, 1.99MB)別ウィンドウで開く 宮崎・土橋・神木地区(PDF形式, 1.49MB)別ウィンドウで開く
宮崎・土橋・神木地区(PDF形式, 1.49MB)別ウィンドウで開く 虹ヶ丘第1・第2地区(PDF形式, 1.93MB)別ウィンドウで開く
虹ヶ丘第1・第2地区(PDF形式, 1.93MB)別ウィンドウで開く 虹ヶ丘第三地区(PDF形式, 1.06MB)別ウィンドウで開く
虹ヶ丘第三地区(PDF形式, 1.06MB)別ウィンドウで開く 虹ヶ丘第四地区(PDF形式, 445.12KB)別ウィンドウで開く
虹ヶ丘第四地区(PDF形式, 445.12KB)別ウィンドウで開く 虹ヶ丘第5地区(PDF形式, 393.20KB)別ウィンドウで開く
虹ヶ丘第5地区(PDF形式, 393.20KB)別ウィンドウで開く 新丸子東3丁目地区(PDF形式, 484.03KB)別ウィンドウで開く
新丸子東3丁目地区(PDF形式, 484.03KB)別ウィンドウで開く 川崎駅日進町地区(PDF形式, 649.50KB)別ウィンドウで開く
川崎駅日進町地区(PDF形式, 649.50KB)別ウィンドウで開く 北加瀬2丁目地区(PDF形式, 931.89KB)別ウィンドウで開く
北加瀬2丁目地区(PDF形式, 931.89KB)別ウィンドウで開く
協定書
 久保台地区(PDF形式, 102.26KB)別ウィンドウで開く
久保台地区(PDF形式, 102.26KB)別ウィンドウで開く 有馬五丁目地区(PDF形式, 7.16MB)別ウィンドウで開く
有馬五丁目地区(PDF形式, 7.16MB)別ウィンドウで開く グランフォーラム宮崎台桜の邱地区(PDF形式, 648.57KB)別ウィンドウで開く
グランフォーラム宮崎台桜の邱地区(PDF形式, 648.57KB)別ウィンドウで開く 宮崎・土橋・神木地区(PDF形式, 120.65KB)別ウィンドウで開く
宮崎・土橋・神木地区(PDF形式, 120.65KB)別ウィンドウで開く※別途、川崎市地区まちづくり育成条例第14条第1項の規定に基づく事前協議が必要となります。
 虹ヶ丘第1・第2地区(PDF形式, 90.61KB)別ウィンドウで開く
虹ヶ丘第1・第2地区(PDF形式, 90.61KB)別ウィンドウで開く 虹ヶ丘第三地区(PDF形式, 107.15KB)別ウィンドウで開く
虹ヶ丘第三地区(PDF形式, 107.15KB)別ウィンドウで開く 虹ヶ丘第四地区(PDF形式, 74.64KB)別ウィンドウで開く
虹ヶ丘第四地区(PDF形式, 74.64KB)別ウィンドウで開く 虹ヶ丘第5地区(PDF形式, 82.97KB)別ウィンドウで開く
虹ヶ丘第5地区(PDF形式, 82.97KB)別ウィンドウで開く 新丸子東3丁目地区(PDF形式, 105.53KB)別ウィンドウで開く
新丸子東3丁目地区(PDF形式, 105.53KB)別ウィンドウで開く 川崎駅日進町地区(PDF形式, 632.48KB)別ウィンドウで開く
川崎駅日進町地区(PDF形式, 632.48KB)別ウィンドウで開く 北加瀬2丁目地区(PDF形式, 1.26MB)別ウィンドウで開く
北加瀬2丁目地区(PDF形式, 1.26MB)別ウィンドウで開く
※ファイルは、すべてPDF形式での提供となります。
お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局計画部
景観・地区まちづくり支援担当
地区まちづくり支援班
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3025
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号17938

 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全