基本施策 4-1-(2) ごみをつくらない社会の実現に向けた取組の推進
- 公開日:
- 更新日:
(1)市民・事業者の排出抑制とリサイクル活動の支援
現状と課題
- 地球温暖化の防止及び循環型社会の構築等の観点からごみの減量を進め、また、やむを得ず発生したごみについては再使用・再生利用し、焼却対象量を極力削減する必要があります。
- 市民のおよそ1割が毎年転出入する中で資源化率の一層の向上を図るため、市民全体のリサイクル意識の向上を図る必要があります。
- ごみの排出量に応じた負担の公平性を確保し、減量に向けた動機付けを図ることが必要です。
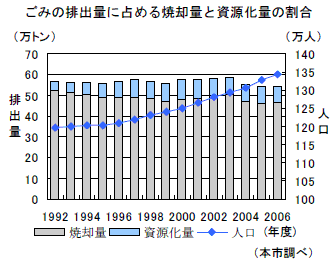
計画期間(2008~2010年度)の取組
- 「川崎市一般廃棄物処理基本計画」に基づき、2015年度までに、市民一人一日あたり180グラムのごみ排出量の減量や、資源化率35%をめざし、各種取組を行います。
- 市民への資源集団回収事業の周知を進め、実施団体及び回収業者と連携を図りながら、回収量の拡大を図ります。
- 2015年までに市民一人一日あたり100グラムの生ごみ排出量の減量をめざし、生ごみ処理機等の購入助成及び生ごみリサイクル講習会を開催するほか、地域特性を活かした生ごみリサイクルシステムの構築に向けた取組を進めます。
- 民間主体による事業系生ごみリサイクルの事業化について調査・検討を進めます。
- ミックスペーパー(菓子箱や包装紙、封筒などの雑かみ)及びその他プラスチック製容器包装の適正な排出に向けた普及広報を行います。
- ごみの一層の減量化に向け、排出量に応じた負担の公平性を確保するため、経済的手法の導入に向けた検討を行います。
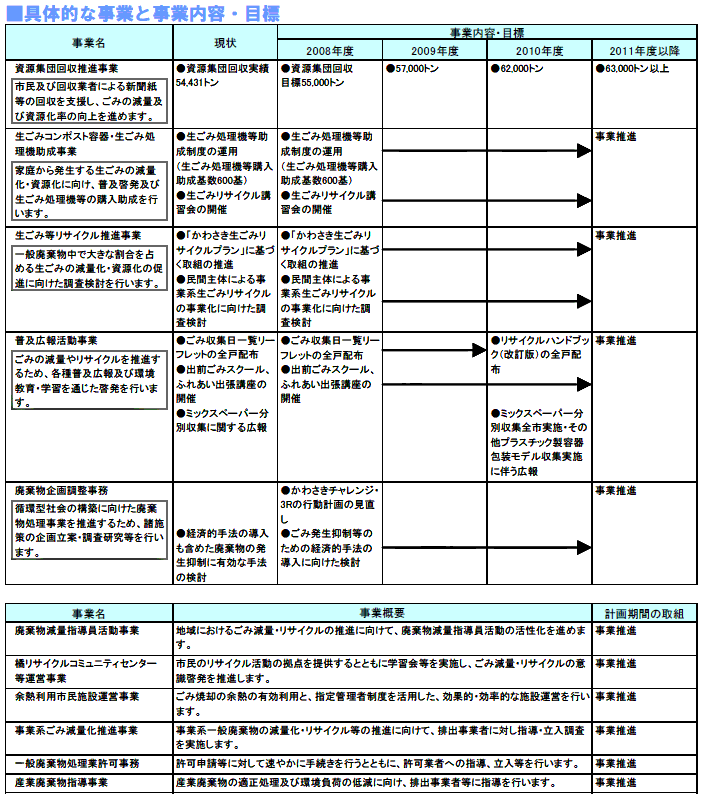
(2)資源物の分別収集の推進
現状と課題
- 本市の資源物を含めたごみ排出量は、人口増加が続く中にあってもほぼ横ばいに推移するなど、事業者処理責任の強化等のこれまでの取組による一定の効果が認められますが、依然として高い水準にあります。また、分別収集による資源化量も伸び悩んでいます。
- 循環型社会の構築に向け、市民・事業者・行政の協働のもと、3R(リデュース(発生・排出抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用))を推進するとともに、分別収集を拡充し、一層のリサイクルを進めることが必要です。
- 特に、家庭系廃棄物の7.6%(2003年度本市調査)を占めるその他プラスチック製容器包装は、焼却処理によるサーマルリサイクル(熱回収)以外にも、マテリアルリサイクル(製品の原材料に戻す)やケミカルリサイクル(化学的に処理して化学原料等に戻す)への利用が可能であることから、資源の有効利用と二酸化炭素削減の観点から、資源化を積極的に進めることが必要です。
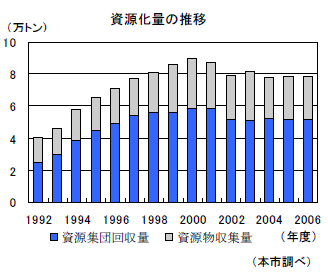
計画期間(2008~2010年度)の取組
- 空き缶・空き瓶・ペットボトル・使用済み乾電池等の分別収集を引き続き実施するとともに、資源物収集の委託化を進め、効率的な収集体制を構築します。
- 2010年度にミックスペーパー(菓子箱や包装紙、封筒などの雑かみ)の分別収集を全市展開します。
- 2010年度にその他プラスチック製容器包装のモデル収集を開始します。
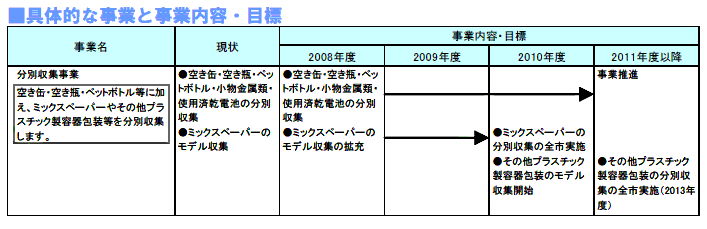
(3)資源物の適正処理
現状と課題
- 分別収集により処理施設に搬入された資源物は、資源化処理施設等において適正かつ安定的に処理を行い、民間の資源化ルート等も活用しながら確実に資源化する必要があります。
計画期間(2008~2010年度)の取組
- 分別収集した空き缶・空き瓶・ペットボトル等を適正に資源化するとともに、2010年度に分別収集を全市展開するミックスペーパーや、同年度にモデル収集を開始するその他プラスチック製容器包装等を適正に処理できるような体制を整えます。
- 2008年度から廃蛍光管の拠点回収を実施します。
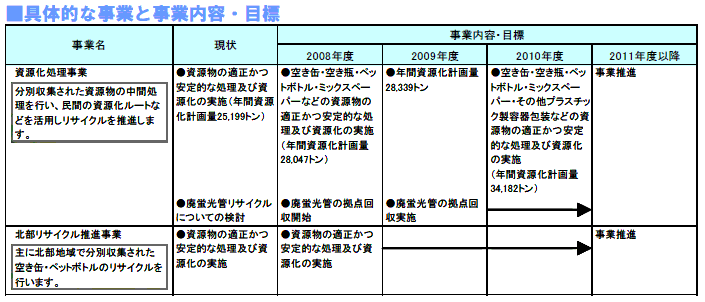
(4)公共工事におけるリサイクルの推進
現状と課題
- 建設副産物(建設工事に伴い副次的に得られた物品)は、我が国の資源利用量の約4割を建設資源として消費する一方で産業廃棄物全体の最終処分量の約2割を建設廃棄物として処分しています。
- さらに、今後、住宅・社会資本の更新に伴い、建設副産物の排出量が増大し、資源循環に占める建設産業の比率がより高くなることが予測されます。
- 建設汚泥については、建設発生土(改良土)になっても建設資材としての需要が少なく、海洋投入という安価な処理方法に依存していることからリサイクル率が低迷しています。
- 本市の公共工事から発生する建設発生土について、現場内利用、工事間利用等を図り、再生資源の有効利用を促進しています。
- 公共工事からの建設発生土の不法投棄などを防止するため、全量搬出先を指定しています。
計画期間(2008~2010年度)の取組
- 循環型社会形成推進基本法や建設リサイクル法等に基づき、工事過程における建設副産物の発生・排出抑制に努めるとともに、やむを得ず出た建設副産物は、再使用及び再資源化(再生利用及び熱回収)を推進するなど、環境配慮の取組を進めます。
- 建設副産物の再資源化については、建設汚泥など、リサイクル率が低い品目もあるため、リサイクル率の向上に向けて国・県・他都市とともに調査研究を進めます。
- 公共工事に伴う建設発生土については、できる限り発生場所での再使用を図るとともに、上下水道の埋戻材に改良する場合は「土質改良プラント」に搬出します。また、現場外へ搬出する場合は、浮島2期埋立処分場に埋め立てるほか、他自治体との連携により地方港湾の埋立用材として活用を図ります。
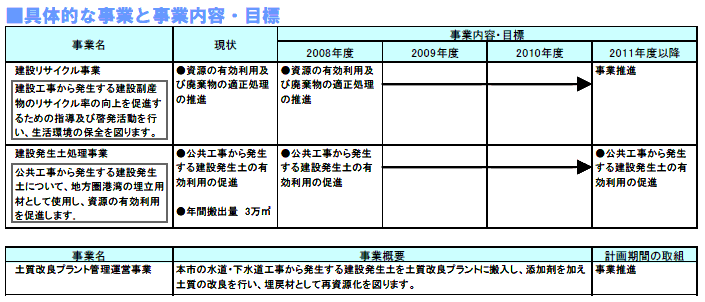
(5)経済活動におけるリサイクルの推進
現状と課題
- 家電リサイクル法の対象4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機)は、リサイクル料金が廃棄段階で徴収される法制度であるため不法投棄が多く、そのような中、2011年に予定されるテレビ放送の地上デジタル化に伴い、一層のテレビの不法投棄が懸念されます。
- 使用済自動車が不法投棄されることなく適正にリサイクルされるよう、自動車リサイクル法の適正な運用が求められます。
計画期間(2008~2010年度)の取組
- 循環型社会の構築に向け整備された各種リサイクル関連法令に基づき、事業者に対して適切な指導・普及啓発を行います。
- 家電リサイクル法の趣旨が徹底されるように市民、事業者の指導及び普及啓発を行うとともに、市内の電気店と協働して家電の適正なリサイクルに取り組みます。
- 自動車リサイクル法に基づき許認可等を行うほか、登録及び許可業者の中で特に立入検査等を行う必要性が高い事業者に対する指導を行います。
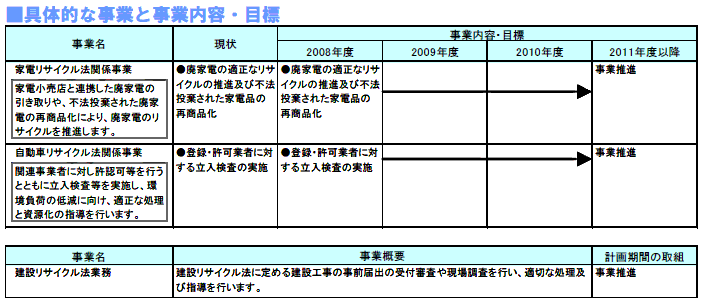
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部企画調整課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2550
ファクス: 044-200-0401
メールアドレス: 17kityo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号24038

 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全