日本の選挙権拡大の歴史
- 公開日:
- 更新日:
最初はわずか1%の有権者だった
明治23年(1890年)-制限選挙

日本で初めての選挙として「衆議院議員総選挙」が実施されました。選挙権を得ることができたのは、満25歳以上の男性で直接国税を15円以上納めている人だけでした。
当時は、15円でお米が約300kgも買うことができました!
(当時の有権者数は、約45万人、人口の約1%でした。)
大正14年(1925年)-男性だけの普通選挙
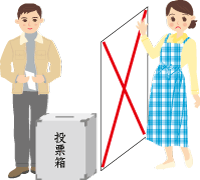
衆議院議員選挙法の改正により、納税要件がなくなり、満25歳以上の男性全てに選挙権が認められました。
納税要件は、「10円以上」(1900年)、「3円以上」(1919年)と徐々に引き下げられました。
(当時の有権者は、約1,200万人、人口の約20%でした。)
昭和20年(1945年)-男女平等の普通選挙
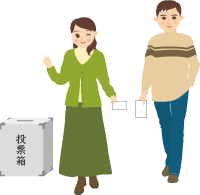
戦後、衆議院議員選挙法が改正され男女平等の完全普通選挙制度が確立しました。同時に、年齢要件も満20歳以上に引き下げられました。
(当時の有権者約3,700万人、人口の約50%でした。)
平成27年(2015年)-70年ぶりの選挙権年齢の引き下げ

選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられました。選挙権年齢の引き下げは、実に70年ぶりのことです。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号18982

 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全