基本施策 3-2-(1) 子どものすこやかな成長の保障
- 公開日:
- 更新日:
(1)確かな学力の育成
現状と課題
- 国際化、情報化、少子高齢化など、さまざまな面で大きく変化している21世紀の社会を主体的に生きていく中で、生涯にわたり子どもたち一人ひとりが個性を発揮し活躍することができるように、「確かな学力」を成長や発達段階に応じて身につける必要があります。
計画期間(2008~2010年度)の取組
- 児童生徒の学習環境を整備するとともに、指導方法や指導形態等の改善を図ることにより、本市の児童生徒に基礎・基本等の「確かな学力」の育成をめざします。
- 学習状況調査を実施して児童生徒の学習状況を的確に把握し、教育課程・指導方法の改善・充実を図ります。
- 基礎・基本の確実な定着等をめざし、課題別学習や習熟度別学習などの少人数指導を推進し、子どもたち一人ひとりの状況に応じたきめ細やかな学習指導の充実を図ります。
- 小学校1年生については、学校生活への適応、基本的な生活習慣の定着、望ましい集団づくりなど、学習指導・児童指導を充実するために、1クラスあたり35人以下の学級編成を引き続き実施するなど、一人ひとりにきめ細やかな指導ができる体制づくりを推進します。
- 二学期制を活かして、子どもたちが連続して学習に取り組むことができる環境整備を進めます。
- 教育活動サポーター事業を拡充し、児童生徒への学習支援を充実します。
- 国際化の進展に対応し、英語による日常的な会話や情報交換ができるような基礎的・実践的なコミュニケーション能力の育成をめざし、小・中・高等学校に外国語指導助手(ALT)等を派遣し、小学校の英語活動及び中・高等学校の英語教育の充実を図ります。

授業風景
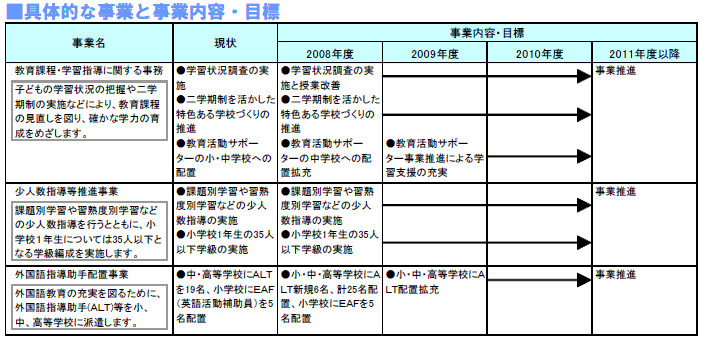
(2)豊かな心とすこやかな身体を育む教育
現状と課題
- 子どもたちが感性を磨き、豊かな心を育んでいくうえで読書や音楽の役割は重要なものであり、これらを子どもたちが実際に経験できる環境づくりが必要です。
- 子どもたちが一人ひとりの違いを認め合い、互いの人権を尊重し合える取組の推進が求められています。
- 子どもたちがすこやかな生活を送るための基礎となる「健康な身体づくり」、「体力の向上」を学校教育活動の中で図っていくことが必要となっています。
- 児童・生徒の安全に対する取組については、従来の校内安全・通学路の交通安全対策を推進するのみならず、学校・保護者・地域が一体となって子どもたちの安全を守り、下校後に安心して公園などで遊べるような防犯面を含めた地域ぐるみの安全対策が求められています。
計画期間(2008~2010年度)の取組
- 家庭・学校・地域の人々とのつながりの中で、子どもたち一人ひとりが個性を発揮し活躍することができるよう、さまざまな事業を推進します。
- 読書活動や音楽活動などを通じて豊かな人間性や社会性を育成するとともに、善悪の判断、基本的なしつけなどについて家庭や地域と連携し、社会の一員としての自覚を育て自立を図ります。
- さまざまな教育活動の中で子どもたち自身が子どもの権利について理解し、自分らしく生き、社会に参加しながら成長できるよう子どもの権利学習を推進します。また、子どもを一人の人間として尊重し、権利侵害から守り自分らしく生きていくことを支えていくために学校・家庭・地域の連携により子どもの権利保障を推進します。
- 子どもは地域全体の財産であると認識し、地域におけるさまざまな危険から子どもたちを守る取組を、スクールガード・リーダーや地域の各種団体、関係機関などと連携をとりながら推進します。
- 学校における救命救急対応としてAEDを計画的に配置し、安全対策を推進します。
- 子どもが運動の楽しさを味わうことのできる授業づくりとして地域の人材活用や、運動をする動機付け等を行うことで、子どもたちの主体的な健康づくりや基礎体力づくりを推進します。
- 健康に過ごすための自己管理能力や望ましい食習慣を身に付けられるよう、学校給食などを通じて食育を推進するとともに、安全で安心な学校給食を提供します。
- また、学校給食調理業務の委託化を推進し、効率的な業務運営体制を構築します。

スクールガード・リーダーの活動の様子
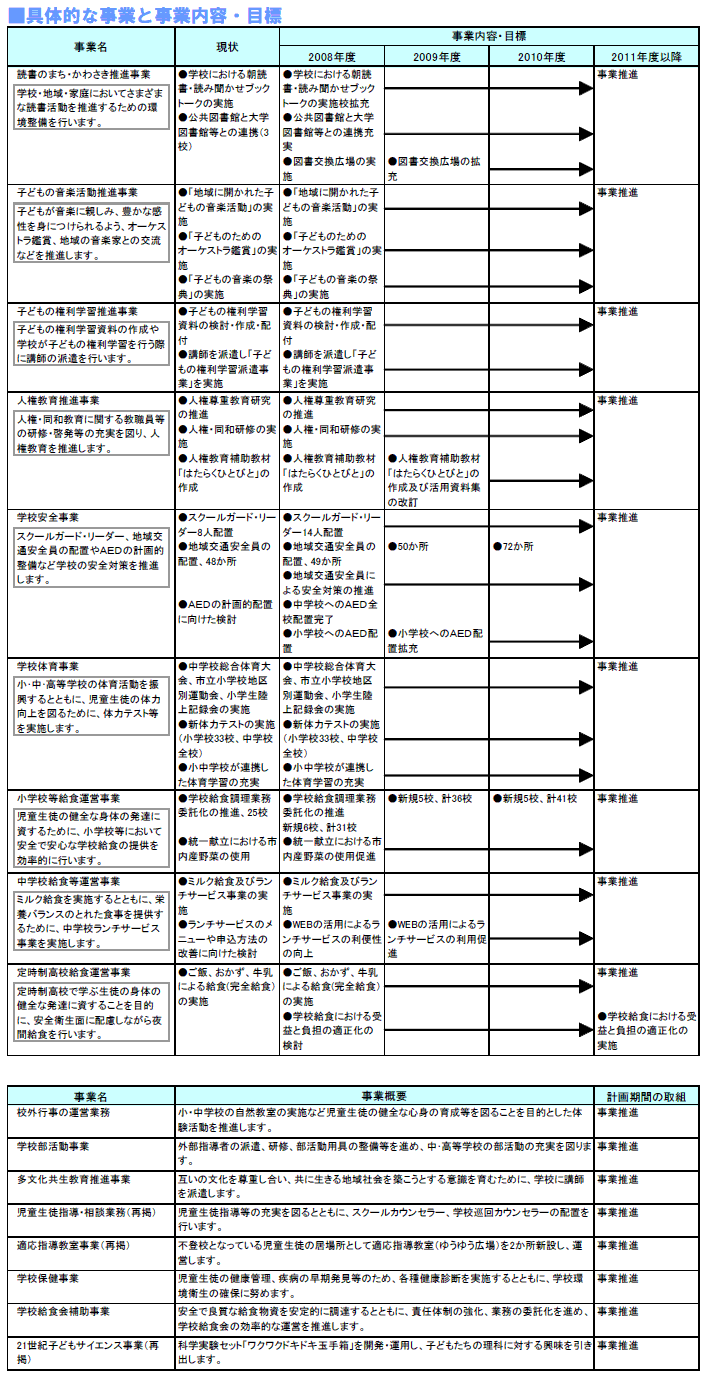
(3)学校の教育力の向上
現状と課題
- 社会の状況が大きく変わり、学校・家庭・地域社会の連携を一層推進することや、学校の教育力の向上が課題となる中で、子どもたちのよき理解者となり、すこやかな成長を支え、保護者や地域住民から信頼されるために、教職員の資質や指導力を一層向上させていくことが求められています。
計画期間(2008~2010年度)の取組
- 教職員が創意工夫を発揮し、自らの能力を十分に発揮することができるよう、教職員の採用方法の改善、教職員の人事評価制度や管理職登用制度を見直し、教職員の人事管理制度の再構築を行います。
- 教職員に対して採用時から経験年数等に応じた体系的な研修を実施し、教職員の資質や指導力を向上させていきます。
- 団塊の世代の退職に伴う大量採用に対応し、初任者研修等指導員を配置するなど、新任教員の指導力向上をめざした研修体制の整備を推進します。
- 学習指導要領の改訂に伴う教育課程の見直しや学習指導・評価の改善などを充実させるため、各教科、教育課題、学校間連携等に係る研究活動や各学校に対する指導・助言を行います。
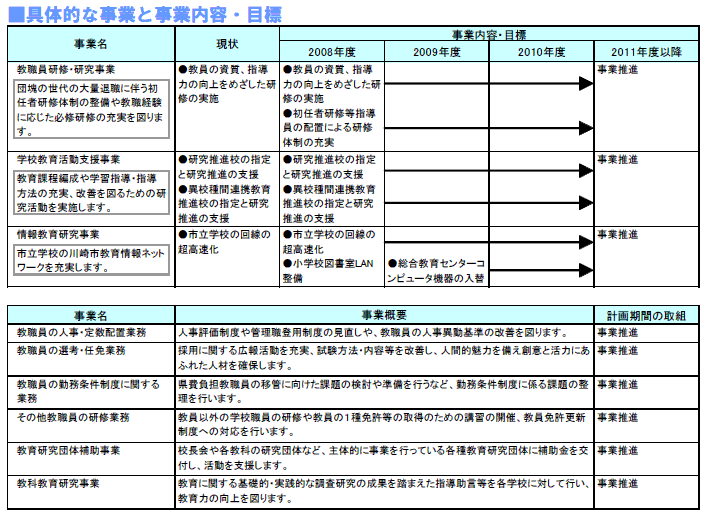
(4)特別支援教育の推進と児童生徒等の就学支援
現状と課題
- 2006年度に各小・中学校で実施した調査では、通常の学級に在籍する児童生徒のうち、校内委員会において支援が必要と判断された児童生徒の割合は全体の約2.3%となっています。
- 近年、特別支援学校や特別支援学級に在籍する障害のある児童生徒や通級指導教室を利用する児童は増加傾向にあり、こうした障害のある児童生徒に対して、一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切に教育的支援を行っていく特別支援教育体制を構築していくことが課題となっています。
- 公立小・中学校に在籍する外国籍児童生徒数は増加傾向にあることから、海外帰国・外国人児童生徒に対する教育相談、就学支援の充実が課題となっています。
計画期間(2008~2010年度)の取組
- 特別な教育的ニーズのある児童生徒、海外帰国・外国人児童生徒等に対して必要な教育的支援を行っていきます。
- 聾・養護学校が特別支援教育のセンター的役割を担っていけるよう、地域におけるネットワークづくりを進めていきます。
- また、聾学校については複数の障害種に対応する特別支援学校への転換に向けた検討を行います。
- 田島養護学校の狭あい等の課題解決に向けた取組を進めます。
- 経済的な理由により修学困難な高校生・大学生に対し奨学金制度により支援を行い、教育の機会拡充を図ります。
- 外国人児童生徒の編入手続を身近な区役所で行うことができるようにしていくとともに、就学支援を充実していきます。
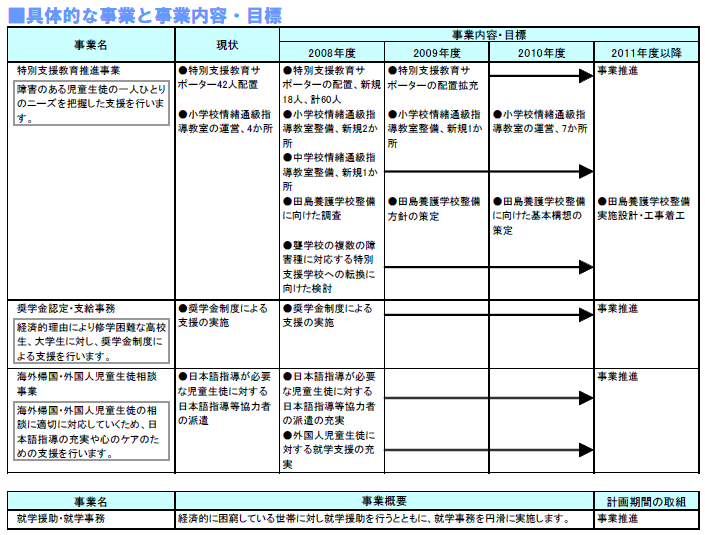
(5)不登校等の児童・生徒への対応
現状と課題
- 子どもたちの家庭や学校生活の悩みや不安、保護者の教育や育児に対する悩みや不安の解消にむけた相談体制を充実していくことが必要となっています。
- 思春期を迎え精神状態が不安定な状況にある子どもたちの中には、中学校進学による環境変化に対応できず不登校になってしまう、いわゆる「中1ギャップ」という状況があり、その対応が必要となっています。
- 不登校の状態が続いている子どもたちの居場所づくりや、再び学校に戻れるような支援も求められています。
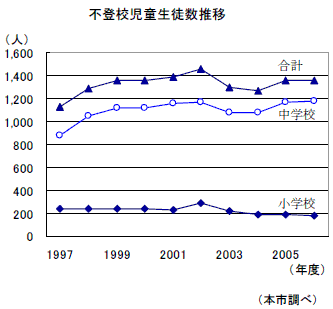
計画期間(2008~2010年度)の取組
- スクールカウンセラーを全中学校に配置、学校巡回カウンセラーを小・高等学校に派遣し教育相談体制を充実するとともに、小・中学校の連携強化などを推進し、心の育ちに配慮した支援を行います。
- 総合教育センター内に教育相談室を増設するとともに、心理臨床相談員を増員して、子どもたちと保護者の教育相談体制の拡充を図ります。
- 子どもたちが抱く中学校進学に伴う不安を、小・中学校が連携し軽減していく取組を進めるため、フレンドシップかわさき事業(心のかけはし相談員)を充実し、不登校の未然防止を図ります。
- 不登校の状態が続いている子どもたちの学校復帰に向けて、適応指導教室(ゆうゆう広場)を増設します。
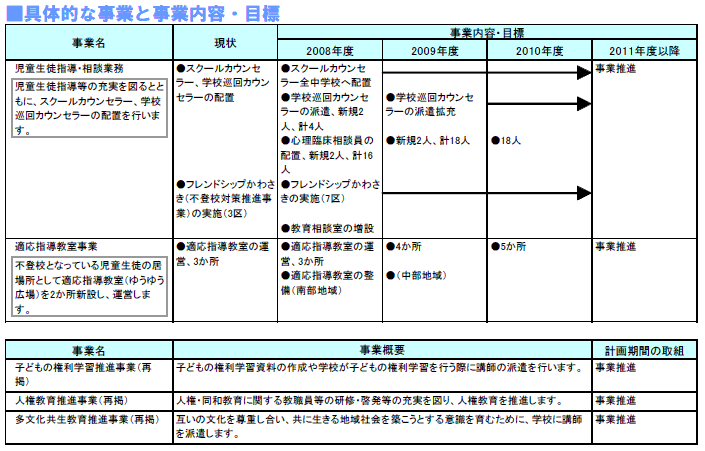
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部企画調整課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2550
ファクス: 044-200-0401
メールアドレス: 17kityo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号24075

 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全