細菌による食中毒 ~黄色ブドウ球菌~
- 公開日:
- 更新日:
黄色ブドウ球菌は決して珍しい菌ではありません。化膿した傷口をはじめ皮膚、鼻腔、手指など、健康な人でも約30%が保菌しているといわれています。また、人だけではなく、他のほ乳類や鳥類にも広く分布している、とても身近な菌です。
この菌による食中毒の多くは、調理する人の手から食品が汚染されて起こります。特徴や予防法を知って、食中毒の発生を防ぎましょう。
黄色ブドウ球菌による食中毒とは?
原因菌
黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)
菌のいる場所
健康な人でも約30%の人は、手指や鼻腔、消化管などにこの菌をもっているといわれています。特に化膿した傷に多くいるので、調理する人の手や指に化膿しているような傷口がある場合には、食品を汚染する確率が高くなります。
菌の特徴

顕微鏡で観察すると、ブドウの房のように集団を形成しているのでこの名前がつけられました。。汚染された食品中で増殖するとき、熱や乾燥に強いエンテロトキシンという毒素を作ります。
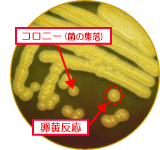
卵黄加マンニット寒天培地という培地に発育させると、コロニー(菌の集落)の周りに卵黄反応と呼ばれる不透明な環を形成することもこの菌の特徴の一つです。
毒素
エンテロトキシン
毒素の特徴
100℃30分の加熱でも無毒化されない、熱に強い毒素です。
原因食品
弁当、おにぎり、サンドイッチなど、調理加工時に素手で扱って作る食品が原因になることが多いです。
潜伏期間
30分~6時間程度
主な症状
激しい吐き気、嘔吐が特徴です。その他、下痢や腹痛などを起こし、まれに発熱などの症状がみられますが1~2日程度で自然回復します。
予防方法
丁寧な手洗い、調理器具の洗浄殺菌が大事です。手に化膿した傷などのある人は、食品に直接触れないように注意しましょう。
食中毒を防ぐため、国や川崎市で微生物の基準が設定されている食品等があります。その中で、黄色ブドウ球菌の基準が定められているものは以下の通りです。
食品衛生検査所では、この基準が守られているか確認するための検査を行っています。
川崎市の定めた黄色ブドウ球菌の衛生指導基準
食品の種類
魚肉ねり製品
食肉製品
豆腐
魚介類加工品
弁当類、惣菜類
生菓子
ゆでめん、むしめん
調理器具
調理従事者手指
衛生指導基準
陰性であること
国の定めた黄色ブドウ球菌の規格基準
食品の種類
非加熱食肉製品
特定加熱食肉製品
加熱食肉製品(加熱殺菌後包装容器に入れたもの)
規格基準
1gあたり1000個以下
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部中央卸売市場食品衛生検査所
住所: 〒216-0012 川崎市宮前区水沢1-1-1
電話: 044-975-2245
ファクス: 044-975-2116
メールアドレス: 40kensa@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号17003

 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全