細菌による食中毒 ~サルモネラ属菌~
- 公開日:
- 更新日:
サルモネラ属菌は食物や水を介して、またヒトからヒトに感染する古くから知られている病原細菌です。この菌は自然界に広く存在しており、牛や豚などの家畜、鶏などの家禽、犬や猫などのペットも多く保菌しています。
サルモネラ属菌は生肉、特に鶏肉や鶏卵からの感染がよく知られていますが、その他の動物も多く保菌しており、汚染された手で食材を触ることによって二次的に広がっていきます。特徴や予防法を知って、食中毒の発生を防ぎましょう。
サルモネラ属菌による食中毒とは?
原因菌
サルモネラ属菌(Salmonella Enteritidis など)
菌のいる場所
自然界に広く分布しており、さまざまな動物の腸管や糞便、川や下水などに存在します。
爬虫類と両生類は自分は症状を起こさずにサルモネラ属菌を保菌している場合があります。ペットにカメなどを飼っている人は、ペットに触った後は十分に手洗いをするよう気をつけてください。
菌の特徴

サルモネラ属菌による食中毒は、増殖した細菌が胃腸に直接作用する、いわゆる感染型といわれる形式でおこります。
サルモネラ属菌が腸管に入ると、小腸表面にある上皮細胞の中に入り込み、基底膜という部分までたどり着くと増殖を始めます。サルモネラ属菌は体の中に内毒素を持っており、菌体が壊れると、これが外に出て腸炎などの中毒症状を引き起こします。
食中毒が起きるのはサルモネラ属菌を1,000万個以上摂取した場合とされていますが、健康状態によってはもっと少量でも症状を引き起こすことがあります。
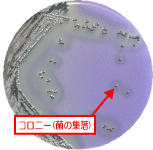
→MLCB寒天培地(サルモネラ属菌の分離培地)に発育したサルモネラ属菌のコロニー(菌の集落)です。
原因食品
鶏卵、鶏卵を使用した生菓子、生肉、生レバー、加熱が不十分な食肉など。
汚染された調理器具や手指を介して二次的に汚染された食品も原因となります。
潜伏期間
4~48時間
主な症状
悪心及び嘔吐ではじまり、その後38℃前後まで発熱し、数時間後に激しい腹痛及び下痢がおこります。軽い症状の場合は特別な治療なしに回復することがありますが、激しい下痢等になった場合は脱水症状などを引き起こし重症となることがあります。老人や乳幼児、免疫が弱まった人などは要注意です。
予防方法
肉や卵は十分に加熱(75℃以上、1分以上)することが有効です。卵の生食は新鮮なものだけにしましょう。この菌は5℃以下ではほとんど増殖しないので、食肉や卵は冷蔵庫に入れてきちんと低温で保存しましょう。生肉を扱ったあとは、手を洗ってから他の食品を扱うようにしましょう。肉と他の食品は調理器具や容器を分けて処理や保存をしましょう。まな板は肉用、野菜用、魚用など、用途にわけて使用するのが望ましいです。
また、ペットなどの動物も多くが保菌しています。動物に触った後にはきちんと手を洗いましょう!
食中毒を防ぐため、国や川崎市で微生物の基準が設定されている食品等があります。その中で、サルモネラ属菌の基準が定められているものは以下の通りです。
食品衛生検査所では、この基準が守られているか確認するための検査を行っています。
川崎市の定めたサルモネラ属菌の衛生指導基準
食品の種類
食肉製品
豆腐
弁当類、惣菜類
生菓子
衛生指導基準
陰性であること
国の定めたサルモネラ属菌の規格基準
食品の種類
殺菌液卵
非加熱食肉製品
特定加熱食肉製品
加熱食肉製品(加熱殺菌後包装容器に入れたもの)
規格基準
陰性であること
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部中央卸売市場食品衛生検査所
住所: 〒216-0012 川崎市宮前区水沢1-1-1
電話: 044-975-2245
ファクス: 044-975-2116
メールアドレス: 40kensa@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号17113

 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全