細菌による食中毒 ~カンピロバクター~
- 公開日:
- 更新日:
カンピロバクターは、近年本国で発生している食中毒の中で発生件数が最も多い食中毒です。家畜の流産の原因菌として獣医領域で注目されていた菌で、鶏、豚、牛などの家畜動物をはじめ、ペット、野鳥、野生動物などあらゆる動物の腸管等に存在しています。
この菌は、ごく少量を体内に取り込んだだけで食中毒を引き起こします。特徴や予防法を知って、食中毒の発生を防ぎましょう。
カンピロバクターによる食中毒とは?
原因菌
カンピロバクター(Campylobacter jejuni/coli)
菌のいる場所
家畜やペット、野生動物などさまざまな動物の体内に存在します。動物の体内や腸管内の限られた環境でしか発育・生存できず、通常食品内では増殖できません。
菌の特徴

この菌はコルク栓抜きのように全体がらせん状にねじれた形をしています。
通常の空気中では酸素が多くて発育することが出来ませんが、逆に酸素が無くても増殖できないという特徴があります(こうした性質を微好気性といいます)。他の菌と違って発育が可能な温度域が高い部分に限られ、31℃~46℃で発育します。
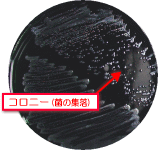
CCDA寒天培地上に発育したカンピロバクターのコロニー(菌の集落)です。
原因食品
生レバーやささみなどの刺身、鶏のタタキなどの半生製品、加熱不足の調理品、鶏肉等を扱ったあとの二次汚染。
潜伏期間
一般に2~5日程度
主な症状
下痢、腹痛、発熱、悪心、嘔気、嘔吐、頭痛、悪寒、倦怠感など、他の細菌性食中毒とよく似ています。また、カンピロバクターに感染した数週間後に、手足の麻痺などの障害を起こす「ギラン・バレー症候群」を発症する場合があることが指摘されています。
予防方法
カンピロバクターは熱に弱いため、十分に加熱調理することで防ぐことができます。食中毒を起こさないよう以下のことをしっかり守りましょう。
- 食肉は中心部までよく加熱しましょう(75℃、1分以上)。
- 食肉を保存するときは他の食品と容器を分けて保存しましょう。
- 料理をするときは手を綺麗に洗いましょう。特に、食肉に触った後は他の食材や器具を触る前に丁寧に洗いましょう。
- 生肉を扱った調理器具は使用後すぐに丁寧に洗い、熱湯等で消毒しましょう。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部中央卸売市場食品衛生検査所
住所: 〒216-0012 川崎市宮前区水沢1-1-1
電話: 044-975-2245
ファクス: 044-975-2116
メールアドレス: 40kensa@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号17015

 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全