産業連関表の仕組みと見方
- 公開日:
- 更新日:
生産活動を営んでいる産業は、他の産業から原材料(中間生産物)等を購入し、労働力や資本等の生産要素を調達して、生産工程に投入することにより財・サービスを産出しています。産出された財・サービスは、最終生産物として最終的な利用者に供給されるか、中間生産物として再び他の産業部門に供給されています。
各産業は複雑な相互依存関係を形成していますが、こうした産業相互間の経済取引の状況を一覧にしたものが産業連関表です。産業連関表の基本的な枠組みは図1のとおりです。
図1 産業連関表のひな型
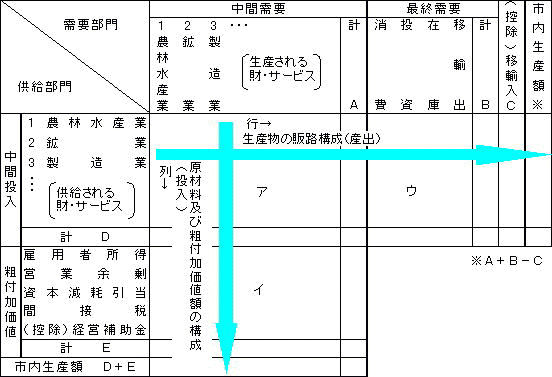
縦(列)方向
表頭(列部門)には、「商品」の買い手としての産業部門が表示され、表側(行部門)には、「商品」の売り手としての産業部門が表示されています。
したがって、この図1の表を縦(列)方向にみれば、各産業部門がその商品を生産するのに要した費用の構成(投入の内訳)がわかります。つまり、生産のために必要な原材料等をどこからいくら買ったか、また、その生産活動によって新たに生み出された価値はいくらかを示しています。このような、生産に必要な原材料等の購入費用を「中間投入」、生産によって生み出された価値を「粗付加価値」といい、粗付加価値には生産活動に伴って支払われた賃金(雇用者所得)や企業の利潤(営業余剰)などがあります。
横(行)方向
また、この表を横(行)方向にみれば、各産業部門が生産した商品の販売先構成(産出の内訳)がわかります。つまり、生産物をどこにいくら売ったかを示しています。このうち、各産業部門へ中間財として販売されるものを「中間需要」といい、中間財とならずに最終財として、消費、投資として使われるもの、及び県外への移輸出となるものを「最終需要」といいます。
表全体
表は大きく分けて3つの部分から成っています。
- 中間投入(=中間需要)部門(表のアの部分)
商品を生産するために産業間で行われる財・サービスの取引関係を示しています。 - 粗付加価値部門(表のイの部分)
生産活動に必要な労働、資本などの投入コストが記録されています。 - 最終需要部門(表のウの部分)
各部門で生産された商品が、消費、投資、移輸出としてどれだけ販売されたかが記録されています。アの部分は「内生部門」、イとウの部分は「外生部門」といいます。
投入と産出のバランス
産業連関表では、縦(列)方向からみた投入額の計と横(行)方向からみた産出額の計は、すべての産業部門において一致しており、各部門の関係は次のとおりとなっています。
- 総供給額=市内生産額+移輸入額=中間需要額+最終需要額=総需要額
- 市内生産額=中間投入額+粗付加価値額=中間需要額+最終需要額―移輸入額
- 中間投入額=中間需要額
- 粗付加価値額=最終需要額―移輸入額
このモデルを川崎市の数値で表すと図2のとおりとなります。
図2 平成12年川崎市産業連関表(3部門統合表)
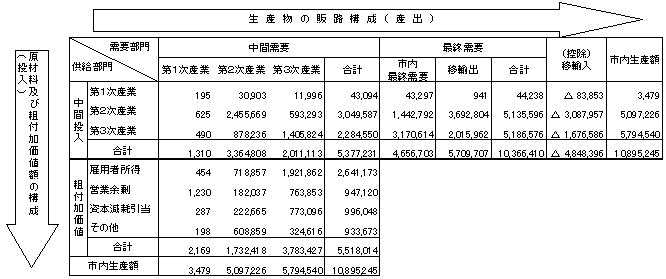
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号11171

 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全