5 第2期実行計画の要件(2)
- 公開日:
- 更新日:
1 新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」の趣旨
2 総合計画の構成
3 川崎市基本構想(1)
3 川崎市基本構想(2)
4 第1期実行計画の推進と成果
5 第2期実行計画の要件(1)
5 第2期実行計画の要件(2)
5 第2期実行計画の要件(3)
6 第2期実行計画の基本的な考え方
7 都市構造と交通体系の考え方(1)
7 都市構造と交通体系の考え方(2)
(2)産業・経済
ア 市内経済の概況
我が国の経済は、バブル経済の崩壊による低迷から2001(平成13)年度を底として回復に向かい、緩やかな成長を続けています。
市内経済についても市内総生産が対前年度比で2004(平成16)年度に1.4%の減少となったものの、2005(平成17)年度には再び0.9%の増加に転じているほか、製造品出荷額等が対前年比で2003(平成15)年から4年連続で増加しています。
一方で、サブプライム住宅ローン問題を背景とする金融資本市場の変動や米国経済の動向、原油価格の高騰等の影響により、金融機関に損失が発生するとともに、株価が下落し食料品を中心とした物価が上昇するなど、国内経済の先行きは不透明感を増しています。
本市の場合、原油価格高騰の影響を受けやすい企業・産業が数多く立地しており、また、市内産業を支えている中小企業にとって、金融環境の変動は経営の不安定要因となることから、今後の経済動向を注視していく必要があります。
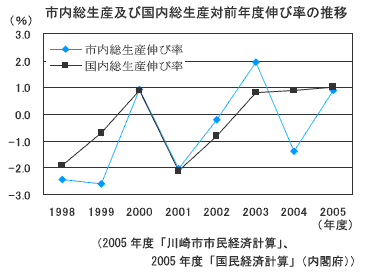
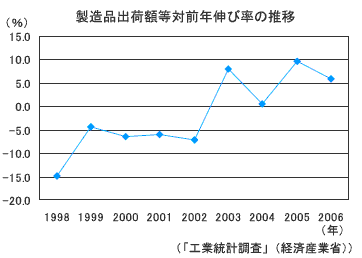
イ 市内産業構造の変化
本市は、我が国を代表する工業都市として、日本経済の発展を支えてきましたが、バブル経済の崩壊以降、生産拠点の海外移転やサービス経済化の進展などにより、その産業構造は大きく変貌しています。
まず、市内総生産の産業分野別構成比を見ると、1980(昭和55)年度には製造業などの第2次産業で61.4%、サービス業などの第3次産業で38.6%となっていましたが、第2次産業の総生産額が減少し第3次産業の総生産額が増加する中で、本市の産業構造は第2次産業から第3次産業へと大きくシフトしており、2005(平成17)年度には第2次産業で31.6%、第3次産業で68.3%となっています。
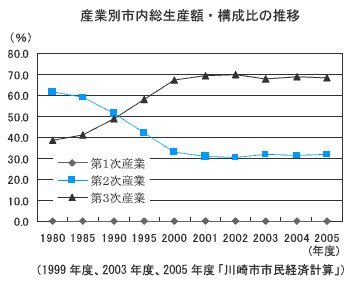
一方で、本市の基幹産業である製造業の製造品出荷額等の推移を見ると、1997(平成9)年から6年連続で減少が続いていましたが、2003(平成15)年に増加に転じ2006(平成18)年まで4年連続で増加となりました。
こうした動きは、本市の強みである素材型産業や加工型産業などのものづくり産業がバブル経済の崩壊や生産拠点の海外移転による産業の空洞化という厳しい経済環境を乗り越え、再生に向けて歩み出したことを示すものと見ることができます。
また、従業員1人当たりの製造品出荷額等の推移を見ると、1998(平成10)年以降、一貫して増加を続けており、この間に約1.8倍の伸びとなりました。これは、本市製造業のものづくり技術と生産性の高さを示すものと言えます。
さらに、こうした産業構造の変化の過程で、本市では研究開発都市としての機能強化が進んでいます。
本市の全産業に占める「学術・開発研究機関の従業者数」の割合は3.68%となっており、大都市平均0.43%の8倍の水準となっています。
また、市内の企業内研究開発が市内生産額に占める割合は4.6%で、国内の6倍となっており、研究開発型企業の集積が本市の特徴となっています。
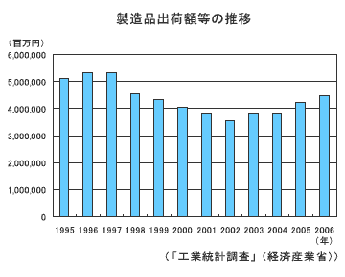
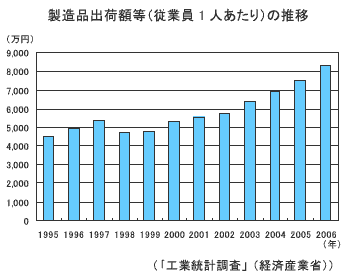
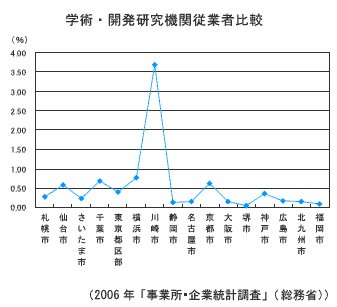
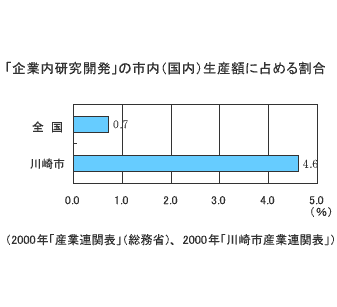
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部企画調整課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2550
ファクス: 044-200-0401
メールアドレス: 17kityo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号23255

 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全