川崎臨海部ニュースレター「KAWASAKI Coastal Area News」vol.37 世界を変え、未来を変える拠点、キングスカイフロント ~川崎臨海部で進む最先端の研究開発~
- 公開日:
- 更新日:
ページ内目次

〜在宅ケアの課題解決のために〜 “看工連携”により、新たなケアの仕組みをデザインする 研究開発プロジェクト「CHANGE」
ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)
“看工連携”____ 聞き馴染みがない言葉かもしれませんが、「看護」の分野に「工学」のイノベーションを持ち込むことで、看護ケアをより負担の少ない形に変えていこうとする新しい取り組みです。そんな看工連携による研究開発プロジェクト「CHANGE」を令和4年より推進している中核拠点が、ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)。プロジェクトリーダーを務めるiCONM研究統括で、東京大学大学院工学系研究科教授の一木隆範先生にお話を伺いました。

一木 隆範 先生
iCONM研究統括 東京大学大学院工学系研究科教授
――プロジェクトCHANGEはどのような目的・背景で誕生したのでしょうか?
CHANGEは文部科学省/JSTに採択された国家プロジェクトCOI-NEXT川崎拠点の呼称で、健康長寿社会の実現や医療現場の課題解決に取り組むため立ち上げました。国内では、高齢者が増える一方でケアする側の人材は少子化で減少し、在宅医療・在宅ケアの比重が高まっています。そこで私たちは、“看工連携”により、誰でも手軽に家で使えるケア製品やサービスをつくることで、この課題の解決を図ろうとしています。例えば、血液検査に代えて呼気を使った健康診断や、ケア業務の中で多くの時間を取られる服薬管理の自動化など「ケアを提供する側」に立った研究開発。そして、老化細胞の除去により老化を遅らせるなど「ケアを受ける側」にも立った研究開発を両輪としています。
―― プロジェクトにかける先生ご自身の思いをお聞かせください。
私はこれまで工学研究者として“医工連携”に取り組み、高度な工学技術による医療への貢献を実践してきました。ところが看護は、属人的な部分が多いがゆえに工学を持ち込むハードルが高い領域です。しかし、だからこそ“看工連携”に本気で取り組めば、現場を大きく変える余地は大きく、イノベーションが起こせるはずだと考えています。
実は遠方で暮らす身内が訪問看護サービスを受けており、個人的にも在宅ケアの質の向上や均てん化の必要性を強く感じていました。似た境遇の人と話すと必ず共感を得られることもあり、在宅ケアにおけるイノベーションは社会的なニーズだと確信し、社会実装への思いを強くしています。
――10年後のゴールを見据えたプロジェクトで、発足から2年がたちました。この間の進捗を教えてください。
私たち工学の研究者が、看護の現場を熟知すること。まずはそこから始めました。具体的には川崎市看護協会の協力下、現場の看護師へのヒアリングを行うだけでなく、看護業務を臨床現場でつぶさに観察し、工学が役立つことがないかを見極めていきます。その結果、非常に多くの潜在的な研究テーマが浮かび上がっています。
一方で、最終的に製品化・産業化・社会実装を目指す上では、ケア従事者と工学研究者だけの連携では足りず、企業や医療界全体、そして行政、市民を巻き込んだ大きなうねりにすることが必要です。そこで令和6年11月に、さまざまなステークホルダーによる共創を促す仕組みとして、「かわさきケアデザインコンソーシアム」を発足させました。また市民のケア力向上を図る意図で、将来の当事者となる高校生の啓発活動なども行っています。
―― 本プロジェクトでは、川崎市との連携もカギになっていると聞きます。
「川崎拠点」ということで、本プロジェクトでも川崎市の強みを最大限活用させていただいています。中でも全国で唯一、市単位の看護協会がプロジェクトに参画しています。看護師の方々が機動的に考えてくださり大きな推進力を生みだしています。また、川崎市は行政もそこに立地する企業も、「先陣を切って変革していこう」という、イノベーションに対する貪欲な姿勢があり、それが非常に心強い。川崎は、本プロジェクトを進める格好の場所だと言えます。
―― 最後に、今後の展望についてお聞かせください。
今後も現場との連携により試作と試用・評価を繰り返し、真に解決手段となるものを目指します。ただし革新的な技術・サービスが生まれたとしても、その価格が高ければ「誰もが使える」とは言えません。ですから、産業化の先のコモディティ化まで進めるのが、私たちのゴールです。
さらに、将来的には海外展開も視野に入れています。日本が世界の中でも最も高齢化が進んでいることをアドバンテージとし、プロジェクトCHANGEから生まれたイノベーションを世界に通用する新たな産業に育てたいと考えています。

ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)
iCONMは、公益財団法人川崎市産業振興財団が平成27年4月よりキングスカイフロントにて運営を開始した、ライフサイエンス分野の拠点形成の核となる先導的な施設。有機合成・微細加工から前臨床試験までの研究開発を一気通貫で行うことが可能な最先端の設備と実験機器を備え、産学官・医工連携によるオープンイノベーションを推進することを目的に設計された、世界でも類を見ないユニークな研究施設です。
【キングスカイフロント立地機関×川崎市】の取組
【慶應義塾大学×川崎市(1)】
再生医療や創薬分野における 新たなライフサイエンス拠点が誕生
令和6年9月、キングスカイフロントに「慶應義塾大学再生医療リサーチセンター」が開所しました。同センターは、再生医療や疾患治療・予防の研究と人材育成を目的として設立されたもの。脊髄損傷をはじめ、細胞再生治療、筋萎縮性側索硬化症やアルツハイマー病等に対するiPS細胞創薬、次世代小型霊長類モデルであるコモンマーモセットを対象とした研究などが主要な研究テーマです。
再生医療の実用化には、基礎研究を実際の臨床の現場につなぐシステムの構築が不可欠であり、アカデミア・研究機関・医療機関・企業、行政など、さまざまな機関の連携が重要になります。この点、キングスカイフロントには非臨床研究を行う「公益財団法人 実中研」がすでに立地しており、令和5年には対岸の大田区・羽田地区に先端医療の臨床を担う「藤田医科大学東京 先端医療研究センター」が開所しました。そこに、基礎研究を担う同センターが加わり、再生医療や創薬分野における〈基礎→非臨床→臨床〉の一連の研究を川崎市殿町・大田区羽田地区で行える体制が整いました。
同センターの開所により、世界最高水準の研究開発から新産業を創出するオープンイノベーション拠点の実現に向け、また一歩前進したといえます。

慶應義塾大学再生医療リサーチセンター
【慶應義塾大学×川崎市(2)】
健康長寿の秘訣を探る 「高齢者の暮らし方と健康に関する学術調査」
慶應義塾大学医学部と川崎市は、平成29年度から市内にお住まいの85歳~89歳の方約1,000名を対象に健康調査を実施しています。
調査結果からは、協力者の約7割にフレイルの一歩手前の状態であるプレフレイルが認められ、食習慣の調査では、たんぱく質摂取量が多いほど健康に過ごせる可能性が高いこと、身体活動の調査では、活動量が多い人ほどフレイルになりにくいこと、医療・介護レセプトデータとの突合結果からは、抑うつ傾向が高いほど医療費負担の増になることが明らかになっています。
さらに、令和6年からは100歳以上のお元気な市民の方を対象に、健康長寿の秘訣を探る調査を開始しました。
1,000人規模の調査は学術的に大きな意義があり、得られた知見は公共データベースでの公開や健康サービスの開発への利用等で、社会還元を図っています。

健康調査の様子(令和5年追跡調査)
【保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科×川崎市】
中学生のアイデア創造力向上を目指し 「アントレプレナーワークショップ」を開催
イノベーションの創出を牽引する人材育成に力を入れている神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科(SHI)と川崎市は、令和6年10月、川崎市立南大師中学校において、中学生の問題発見力やアイデア創造力の向上を目指す「アントレプレナーワークショップ」を開催しました。
対象は2学年約130名。講師はSHI副研究科長で、アントレプレナー教育の第一人者の島岡未来子教授。「常識を打ち破る」「新しいことに挑戦する」「世界を良くしたいという気持ち」「冒険心」「失敗を恐れない気持ち」など起業家精神の大切さについてのレクチャー後、SHIの学生らがファシリテーター役となり、グループワークが行われました。
参加した中学生からは、「アントレプレナーシップという言葉は初めて聞きました。これまで問題を解くために考えたことはありましたが、自分をもとに考える、また、相手から新しいことを知り考えることは、これまでなく、気付きとなる機会でした。今後に生かしていきたい」という声が聞かれました。

グループワークの様子

連節バス「KAWASAKI BRT」の運行が拡充! 〜川崎臨海部⇔川崎駅間の交通がますます便利に
公共交通機関で川崎臨海部へ向かう手段として、多くの方が利用する川崎駅前発着のバス。混雑解消のため、川崎鶴見臨港バス株式会社と川崎市は連携し、令和5年3月からハイブリッド連節バスを使った「KAWASAKI BRT」(BRT:バス高速輸送システム)を川崎駅前~水江町間で導入してきました。令和6年12月23日からは、連節バスの台数を増やし、川崎駅前~エリーパワー前間でも新たに運行を開始しています。
今後も混雑緩和、CO2削減に貢献するBRTを活用した取組を進めていきます。

「KAWASAKI BRT」運行概要
(1)平日朝・夕ラッシュ時間帯は12分間隔→8分間隔に増発。特快と快速を交互に運行
(2)ラッシュ後の午前時間帯、夜間帯に運行を拡大。土曜ダイヤでの運行も新たに開始
※全便川崎駅前21番のりばから発車します
詳細はこちらから https://www.rinkobus.co.jp/info/2024/12/kawasaki-brt-5.html外部リンク
日本橋の有名蕎麦店「日本橋そばよし」の味を再現。 キングスカイフロントにオシャレな蕎麦屋がオープン
キングスカイフロントのリサーチゲートビルディング殿町4に、令和6年10月、「HARENOSOBA Produced BY NIHONBASHI SOBAYOSHI」がオープンしました! 店主へ『HARENOSOBA』の由来を伺うと、『地域の方や周辺で働く方、キングスカイフロントに関わるすべての方に対し、お蕎麦を食べること=日常のことでありながらも、非日常的なオシャレな空間で「特別な一杯」を味わって欲しい。訪れるお客様の毎日が“ハレ(晴れ)の日”になって
ほしい』との願いが込められているとのことです。限定メニューの厚切り豚そばや明太とろろ混ぜそばなどのメニュー開発も行うなど、新たなチャレンジも続けています。
味はもちろん、カフェのような清潔感漂うオシャレな空間も必見です。多摩川沿いのサイクリングやランニングでお腹が空いたときに食べる一杯も良いかもしれませんね。
営業時間 10:00~15:00 定休日 土・日・祝

ランニングに新たな価値を ホテル併設のランニングステーション

多摩川沿いを多くのランナーが行き交う場所に建つ「川崎キングスカイフロント東急REIホテル」に併設のランニングステーション(ランステ)が人気です。
同ホテルは、宿泊だけでなく「体験」に価値を見出すことをテーマとする「ライフスタイルホテル」。スタッフの佐田さんは「ランステとともに当館自慢の大浴場や朝食、コワーキングスペースなどをご利用いただくことで、ランニング+αの体験を提供しています」と話します。
朝食の食材は、CO2フリーの電力を使って栽培したレタスや市内の養鶏場から取り寄せた卵、県内産の旬の野菜など地産地消にこだわり、サステナブル&エシカルを実現。豊かな自然と開けた空が四季折々で姿を変え、何度訪れても楽しめる場所です。
「我々は、地元の方々に愛されるホテルを目指しています。のんびり過ごしたい休日に、ぜひ遊びに来てください(佐田さん)」
詳細はこちらから https://www.tokyuhotels.co.jp/kawasaki-r/facility/99045/index.html外部リンク
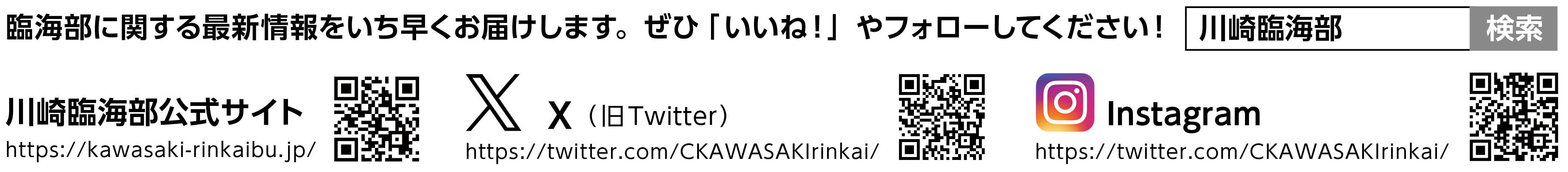
お問い合わせ先
川崎市臨海部国際戦略本部事業推進部
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3738
ファクス: 044-200-3540
メールアドレス: 59jigyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号175291

 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全