長念寺本堂
- 公開日:
- 更新日:
長念寺本堂 1棟(撮影 御堂義乗)
附
棟札 1枚
木銘札 1枚
建築年代
江戸時代〔文政7年(1824)〕
規模
行57.3尺 梁行55.5尺
構造形式
桁行7間(背面9間)、梁行7間、入母屋造・銅板瓦棒葺、正面1間向拝付 側角柱、三斗組(拳鼻付)、中備蟇股
所有者
長念寺(多摩区登戸1416)
指定
市重要歴史記念物 平成2年1月23日指定
解説
長念寺は、大永2年(1522)に法泉坊が創立した寺院で、二代祐念の時、真言宗から浄土真宗に改宗したと伝えられる。三代祐唱の時、秀月禅尼の帰依を受け、禅尼寂後、慶安2年(1649)の一周忌法要のために、菅の領主であった嫡子中根壱岐守正朝より本堂、大門、惣門、無常門、玄関、庫裏が寄進された。その後、元禄16年(1703)に鐘楼が創建された。慶安2年(1649)の本堂は数度の修理を経て文政6年(1823)まで存続し、翌7年に再建された。文政6年正月に、中根家に出した本堂再建のための願上書によると、旧本堂は8間に7間(48尺に42尺程)の規模で、柱は内外とも五寸角、屋根は寄棟造、向拝に軒唐破風を付け、彫刻は欄間だけであった。これは江戸初期の本堂が住宅風の建物であったことを示している。棟札によると、現在の本堂は十世秀善の時、文政7年5月(1824)に上棟された建物で、大工棟梁は地元の小林源三郎と上平間村(川崎市中原区)の渡辺喜右衛門棟暁である。弘化5年(1848)2月に本堂の落慶供養が行われた。なお、本堂は昭和34年(1959)に屋根替が行われ、現状の入母屋造・銅板瓦棒葺に改修された。また同52年に、本堂背面の廊下を増築した。南向きの山門を入ると正面に本堂、その東側に南北棟の庫裏がたつ。3棟とも江戸時代の建物であり、近世寺院の景観を良く留めている。
本堂は、旧本堂よりひとまわり大きい、桁行7間(背面9間)、梁行7間の規模で、屋根はもと寄棟造・茅葺の急峻な勾配をもち、正面の軒唐破風付の向拝は瓦葺であった。軸部、造作材に欅を多用し、内部の柱を建登せ丸柱とし、内外に組物と彫物装飾を用いて仏堂化を進めている。側廻りは角柱を用い、軸部を切目長押、内法長押(正面中央間は差鴨居)、飛貫、頭貫(獅子頭付)、台輪で固める。組物は三斗組(拳鼻付)、中備に板蟇股を置き、軒はもと二軒疎垂木であった。側廻りの柱間装置を復元すると、正面中央間は桟唐戸4本と明障子2本の引分け、正面両脇各3間と東面前5間、西面前4間及び後面中央間は掃出し、東面前より第6間と西面前より第5.6間及び後面東より第3間と7間は窓で、建具はともに遺戸2本と明障子1本の組み合わせ、他は壁となり、背面の廊下増築部を除き、当初の形式をよく保存している。
内部は真宗本堂に特有の構成を持つ。すなわち、前面4間通りは3面の入側を内縁とし、母屋に広い外陣と矢来内をとり、その後方2間通りは上段構えに造り、母屋中央を内陣、両脇を左右余間、左右入側を飛檐の間とする。後面1間は後陣である。外陣は間口を柱間3間に割り、中央列に各2本の丸柱を建て、軸部を虹梁、飛貫で固め、天井は矢来内とも、挿肘木により出三斗を組んで、格天井に造る。外陣内部の飛貫位置に渡した大虹梁による架構は見ごたえがある。三面の内縁は平明な板天井を張り、繁虹梁を見せている。
内陣及び左右余間の正面は真宗本堂の最も意匠を凝らす所であり、当本堂でも巻障子や彫刻欄間を金色に仕上げ、飛貫をすべて虹梁形に造り、組物は出組、中備に彫物蟇股を入れ、内法長押により上の木部に極彩色を施す。内陣及び左右余間の内部は出組斗栱を組んで格天井に造り、格間の板に彩色画を描く。
当本堂は、内陣と余間正面の装飾を凝らした意匠及び外陣の大虹梁架構による広々とした構成が見所であり、それらの構造や細部意匠は幕末期の特徴を示している。
平成26年4月より耐震診断などで修理が必要とされ改修工事に入り、建物ごと油圧ジャッキで持ち上げて基礎部分を補強、また建立当時の部材を生かしながら外陣彩色の装飾を塗り直すなどして復元し、平成29年度に改修工事は終了した。
棟札(縦87cm 横25.3cm 厚さ1.7cm)
銘文・表
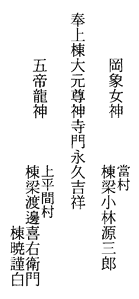
銘文・裏
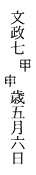
木銘札(縦94cm 横27.2cm 厚さ0.9cm)
銘文・表
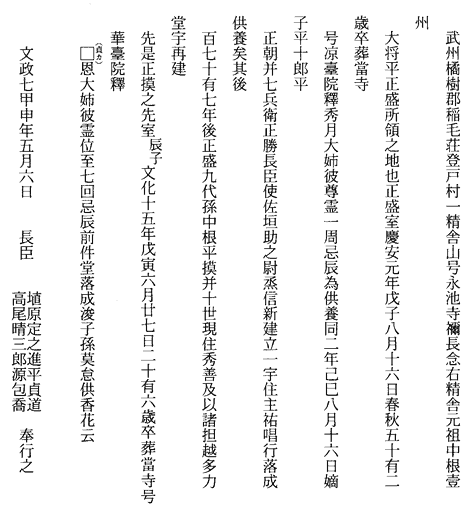
長念寺本堂梁間断面図
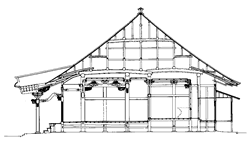
長念寺本堂平面図(現状)
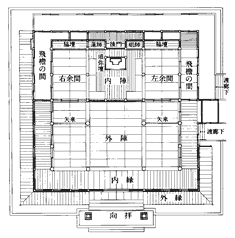
コンテンツ番号259
