木造 不動明王及び二童子像
- 公開日:
- 更新日:

木造 不動明王及び二童子像 3軀
年代
室町時代〔天文22年(1553)〕
像高
(不動)17.0cm
(矜羯羅)15.7cm
(制吒迦)15.8cm
所有者
光明院(多摩区登戸1253)
指定
市重要歴史記念物 昭和60年12月24日指定
解説
寺伝によると光明院はもと王禅寺の末で、室町時代後期に源空法印によって開かれたというが、江戸時代の数度の火災により古記録類は全て焼失し、詳しい寺歴は不明である。
被災を免れ当寺に伝わる本像は、不動明王の両脇に矜羯羅・制吒迦の二童子を配する、いわゆる不動三尊と呼ばれる形式である。
中尊は、頭に莎髻を頂いて弁髪を左肩先に流し、右手に宝剣、左手に羂索をとって、火焔光背を背負い、瑟瑟座様の台座に坐す。眼は左目をやや閉じた天地眼とせず両眼とも大きく見開き、歯牙も左右上下に表さず上の歯牙のみで唇を噛んでいる。このような忿怒の形相は古様で、勿論中世に入ってからも見られるが、不動の造像が始まった平安時代初期の作例に多いスタイルである。
両童子は、中尊寄りの足をやや踏み出し、矜羯羅童子は胸前で合掌し、制吒迦童子は左手で胸前で肩にかけた衣の端を握り、右手を横に下げるという通常の像容をとる。
構造は、三像ともに躯幹部からはみ出した両腕や脚部などを別材で矧ぐ他は全て一材から彫成し、彫眼とする。
光背と台座の背面に次の墨書銘がある。
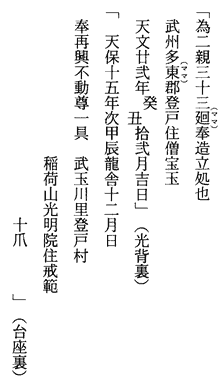
この銘文によって、本像が天文22年(1553)に登戸に住む僧宝玉が両親の33回忌に造立したこと、天保15年(1844)に修理されたことがわかる。
20cmに満たない小像で、さらに天保期のものと思われる厚い後補の彩色に覆われているために彫技も鈍く人形化は否めない。しかし、ずんぐりとした量感ある体躯や簡略ぎみながらゆったりと波打つ衣文には室町時代末期頃の作風をよく残しており、造立年代が明確な基準作として貴重な存在である。
お問い合わせ先
川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3305
ファクス: 044-200-3756
メールアドレス: 88bunka@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号554
