旧山田家住宅
- 公開日:
- 更新日:

旧山田家住宅 1棟
建築年代
江戸時代中期
規模
桁行14.8m 梁行9.5m
構造形式
切妻造、茅葺、一重三階
所有者
川崎市
所在地
多摩区枡形7-1-1
川崎市立日本民家園内
指定
県指定重要文化財 平成9年2月10日指定
解説
当住宅の旧所在地は富山県庄川の最上流、東礪波郡上平村桂で、庄川の支流の奥、岐阜県境に近い戸数5、6戸の秘境であった。
全体の規模は約8間×約5間(14.8m×9.5m)で、合掌造によく見られる張り出し部分もなく、長方形平面の簡明な姿を示す、純粋な切妻造で、いわゆる合掌造の古い例である。
家の入り方は平入りで、茅葺屋根の形は切妻である。間取りには、前部土間からの入口に「しゃし」という飛騨・白川系の合掌造特有の小部屋がある。また、通常この部屋の正面寄りは、出入口としての性格上、半間程度一段床面が低くなっている例が多いが、山田家においては、他の床面と同高である点が異なっている。恐らく出入には、上り台のようなものを置いたのであろう。また、目を引く点として、床が高いことが挙げられる。これは、加賀藩の賦課であった硝煙をつくるためであろうと思われる。二階を「あま」、三階を「そらあま」と二層に小屋組を分けていることや、屋根より突き出た「かんざし」と呼ばれる棟茅をとめる縄をからみつける棒があるのは、他の合掌造と同様である。
「ぶつま」については、時代が新しくなるに従い広くなるのが通説だが、山田家のものは、きわめて狭い。まだ仏壇がなく、壁板に軸等を掛けて拝んでいた時代の間取りであろうと思われる。また、「うすなわ」が低い板張りであることも、飛騨系の特徴であると言える。さらに、「帳台構え」があるのも古い合掌造の特徴である。
旧山田家住宅は、越中・庄川流域に所在しながら飛騨の特徴を有する珍しい存在である。建築年代も17世紀後期から18世紀前期と推定され、合掌造民家の中では最古のグループに属するとみられ、特徴のある貴重な遺構である。
旧山田家住宅平面図
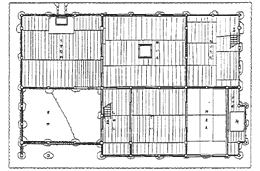
関連記事
- 川崎市立日本民家園
川崎市立日本民家園については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3305
ファクス: 044-200-3756
メールアドレス: 88bunka@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号290
