蚕影山祠堂
- 公開日:
- 更新日:

蚕影山祠堂
宮殿 1棟
覆殿 1棟
附
棟札 1枚
手洗石 1基
建築年代(宮殿)
江戸時代〔文久3年(1863)〕
規模(宮殿)
間口2尺、奥行3.28尺
構造形式(宮殿)
1間社春日造(隅木入)、向拝軒唐破風付、柿葺覆殿
建築年代
江戸時代〔元治2年(1865)頃〕
規模
桁行15尺、梁間9尺
構造形式
正面入母屋造・背面寄棟造、妻入
所有者
川崎市
所在地
多摩区枡形7-1-1
川崎市立日本民家園内
指定
市重要歴史記念物 平成7年(1995)1月24日
解説
この祠堂は養蚕の神「蚕影大権現」を祀る宮殿と、それを安置する覆殿より構成される。もと川崎市麻生区岡上の東光院境内に祀られ、人々の信仰を集めていたが、養蚕の衰退とともにお堂の維持が困難になったため、岡上の養蚕講中より昭和44年に川崎市に寄贈された。翌45年、祠堂を日本民家園に移築し、それを機に覆殿は復原修理された。
宮殿は間口2尺、奥行3.28尺、隅木入りの春日造形式の小規模な社殿で、向拝の正面に軒唐破風を付ける。総欅の素木造りである。軸部は直径2寸の細い丸柱を用い、腰長押・内法長押・頭貫・台輪をまわすが、出組斗栱は中備の組物を省略する。このように、軸部と組物は細身に造り、それらの間の壁面や小壁を豊かな彫物装飾で埋めているのが特徴である。中でも、両側面の板壁と腰壁に嵌め込まれた立体的な浮き彫り彫刻蚕神である金色姫の物語を表わしたもので、その表現には見るべきものがある。
棟札によると、宮殿は文久3年(1863)に再興されたことが判明し、造営には岡上村講中のもの38人が助力した。大工(番匠)の名は字が掠れて読めないが、4字のうち2字目は「海」であり、岡上の大工鳥海氏の先祖ではないかと推察される。
覆殿は桁行15尺、梁間9尺の規模で、正面に入母屋造・茅葺の妻をみせた妻入の建物であり、背面を寄棟造にする。向拝は前面半間を吹放し土間にしたもので、向拝柱間に虹梁を入れ、軒を軽快な四方せがい造にするなど、簡素な建物のなかにも意匠を凝らしているのが窺える。正面は腰高格子戸3枚を引違に建て、側面は柱を3尺間に立てて前9尺を格子窓とする。ほかは板壁で、堅羽目に化粧の目板を打つ。内部の板敷は後6尺の床を一段高く造り、そこに宮殿を安置する。建立年代は宮殿とほぼ同時期と推定されている。
以上のように、蚕影山祠堂は宮殿と覆殿が同時期の建物であり、宮殿は蚕神の説話に因んだ彫物で飾られ、幕末期の特徴をよく示している。また、この祠堂は川崎市内における農村と養蚕について考える上で重要な遺構である。
なお、宮殿背景に取り付けられている棟札は、蚕影山祠堂の建築年代が裏付けられる貴重な資料である。併せて、覆殿前に安置されている手洗石は、銘文から養蚕講中(女人講中)によって造立されたことが窺えることから、関連資料として重要である。
蚕影山祠堂覆殿断面図
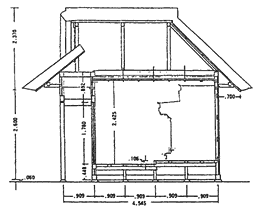
関連記事
- 川崎市立日本民家園
川崎市立日本民家園については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3305
ファクス: 044-200-3756
メールアドレス: 88bunka@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号294
