3月の市民健康デーのお知らせ
- 公開日:
- 更新日:
ページ内目次
毎月第4土曜日は健康について語り、学び、考え、実行する「市民健康デー」です。
3月のテーマは「アルコール」です
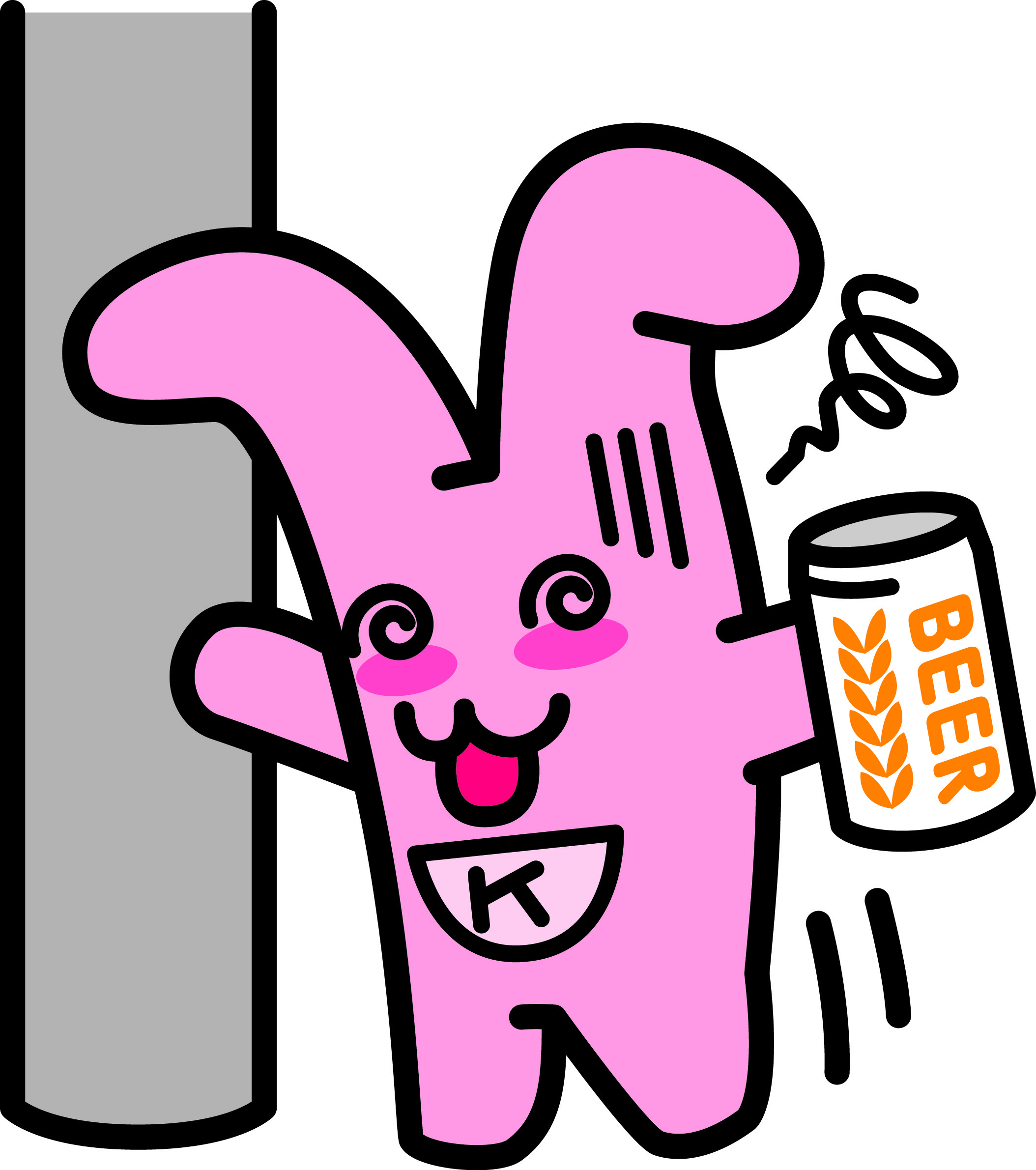
アルコールは適量にしましょう
3月~4月にかけて、歓送迎会が行われ、アルコールを飲む機会が増えるのではないでしょうか。
飲酒は健康だけでなく、さまざまな影響をおよぼします。
一人ひとりがアルコールのリスクを理解し、どのような影響があるか、自分に合った飲酒量を決め、健康に配慮した飲酒を心がけましょう。
お酒の影響を受けやすい3つの要因
年齢
高齢者は、体内の水分量の減少等で、アルコールの影響が強く表れるため、転倒・骨折・筋肉の減少等の危険性が高まります。
性別
- アルコール分解(代謝)酵素の働きが男性より弱い
- 体内の水分量が男性より少ない
- 女性ホルモンにより、アルコールの影響を受けやすい
体質
体内の分解酵素の働きの強弱などが個人によって大きく異なり、顔が赤くなったり、動悸や吐き気を引き起こしたりする可能性があります。
生活習慣病のリスクを高める純アルコール摂取量
生活習慣病のリスクを高めない量を心がけ、週に1~2日は飲酒をしない日を作ることが大切です。

アルコールと肝臓
なかでも肝臓病は最も高頻度で、かつ重篤にもなる病気です。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、よほどのことがない限り音を上げない臓器です。
したがって症状が出てからでは重篤化している可能性もあり、早期発見が大切です。
そのためお酒を常習的に飲んでいる方は、症状がなくても定期的に血液検査を受けるようにしてください。
飲酒するときに気を付けること
飲酒により運動機能や集中力が低下します。飲酒をするときは、けがや事故を起こさないように、行動に気をつけましょう。
関連情報
関連記事
- 厚生労働省 生活習慣病などの情報 飲酒外部リンク
厚生労働省が作成した生活習慣病予防のための健康情報サイトです。
関連記事
- 健康に配慮した飲酒に関するガイドラインについて外部リンク
厚生労働省が定めている「健康に配慮した飲酒に関するガイドラインについて」のページです。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部健康増進課健康づくり担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2411
ファクス: 044-200-3986
メールアドレス: 40kenko@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号173228

 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全